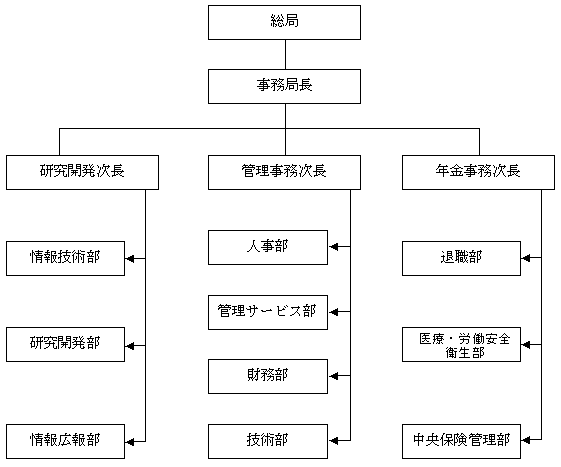|
このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
|
 |
 |
|
|
平成16年度JICAセミナー カントリーレポート(ヨルダン)
資料出所:平成16年度JICA労働安全衛生政策セミナー カントリーレポート(ヨルダン)
(仮訳 国際安全衛生センター)
|
労働安全衛生法令および規則
|
| 1. |
労働安全衛生関係法令 |
|
ヨルダンには労働安全衛生関連法令が多数存在する。
- 2001年法律第19号社会保障法
- 2002年法律第1号環境保護法
- 2002年法律公衆衛生法
- 1999年法律第18号市民防衛法
- 1953年法律第16号職業および産業法
- 1996年法律第8号労働法および修正条項―最重要法令
|
|
| 1) |
1998年規則第7号―労働安全衛生管理者および委員会の形成に関する規則
1996年法律第8号労働法第85条に従って公布
| 第1条 |
|
本規則の名称は、「1998年労働安全衛生管理者および委員会の形成に関する規則」である。本規則は政府広報への発表日をもって施行されるものとする。*
*1998年2月16日発行の政府公報第4263号にて発表。
|
| 第2条 |
|
本規則で使用されている各用語、表現は、特に文脈で示されない限り以下に指定した意味を持つ。
省:労働省
大臣:労働大臣
事業所:産業労働、商品生産、流通等に携わる団体
マネージャー:使用者あるいは使用者の文書上の代理人
委員会:事業所における労働安全衛生委員会
管理者:事業所における労働安全衛生管理者
|
| 第3条 |
|
本規則の定める規定は、大臣の指示により定められた産業区分に属し、労働者が30名を超える全事業所に適用される。
|
| 第4条 |
|
全ての事業所は、事業所の労働力規模および以下に示す表に従い、労働安全衛生に特化した雇用システムを形成しなければならない。
| 労働者数 |
専門管理者数 |
専門技術者 |
安全衛生委員会 |
| 20〜50人 |
|
1 |
|
| 51〜200人 |
|
1 |
1 |
| 201〜500人 |
1 |
2 |
1 |
| 501〜1,000人 |
2 |
2 |
2 |
| 1,000人以上 |
1 |
2 |
1 |
|
| 第5条 |
|
管理者は、職務上マネージャーの直属となり、事業所が従事している作業の性質や職務規準に合致した方法でトレーニングを必ず受けなければならない。大臣は、管理者に必要なトレーニング規準、およびこの目的のために発せられた決議に従って正式に認可される団体を指定する。
|
| 第6条 |
|
管理者の専門職務は以下に挙げる8点である。 |
|
|
| a) |
|
担当事業所における年間必須計画を含む労働安全衛生プログラムを立案する。 |
| b) |
|
事業所の全作業場を定期的に検査の上、危険や害に対して、個人用保護具を提供したり、機械に防御器具を取り付けたりするなどの適切な対応策を実施する。 |
| c) |
|
適切な器具を使用して作業環境によって発生するエラーやミスを測定、特定し、今後の参考や再調査のために特別記録を作成する。 |
| d) |
|
労働災害を明確化し、報告書を作成する。報告書には、今後同じような災害を発生させないための対応策を記載しなければならない。また、作業上での労働災害やけが、通常疾病あるいは慢性の職業性疾病に関する統計を作成する。管理者は3カ月ごとに報告書を省に提出しなければならない。 |
| e) |
|
職業性疾病が発生した作業場を調査する。また、作業環境に関する報告書を作成し、事業所の選任した産業医がいれば相談する。 |
| f) |
|
労働者に火事の危険から身を守る方法や、救急処置用品について説明し、フォローアップを行う。また、負傷者を医務室や病院に搬送しなければならない場合の手段を整備しておく。事業所内の整理整頓、清潔を調査し、フォローアップを行う。 |
| g) |
|
事業所および従業員を危険や労働災害、けが、職業性疾病から保護するために実施する研修プログラムを専門家と協力して作成し、理解度を調査する特別テストに従業員全員が合格できるようにする。 |
| h) |
|
事業所が作業工程に機械や物質を導入する際に意見を述べる。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2) |
労働安全衛生管理者および委員会の形成に関する規則条項の対象となる産業区分に関する指示
1998年規則第7号労働安全衛生管理者および委員会の形成に関する規則第3条条項に従って公布
| 第1条 |
|
本規則の名称は、「労働安全衛生管理者および委員会の形成に関する規則条項の対象となる産業区分に関する指示」である。本規則は政府広報への発表日をもって発効するものとする*。
*1998年9月16日発行の政府公報第4274号にて発表。 |
| 第2条 |
|
本規則の指示は、以下に示す産業区分に属し、従業員が20名を超える事業所に適用される。
| a. |
|
鉱業、採石など、地下からの物質採掘に関する産業
商品の製造、変更、加工、修理、装飾、処理、販売のための準備を行う産業
造船、道具の解体など、物質の造形に関する産業
電力など一般的動力を発生させ、供給および配給を行う産業 |
| b. |
|
建設業 |
| c. |
|
陸運、海運、交通、有線/無線通信業 |
| d. |
|
情報、報道、印刷、出版、流通業 |
| e. |
|
旅行、ホテル、店舗、娯楽施設運営業 |
| f. |
|
搬送、陸揚げ、貯蔵保管に関する産業 |
| g. |
|
農業、獣医業、狩猟業、漁業、協同組合 |
| h. |
|
清掃、警備、港に停泊中の船に対するサービス、ガソリンスタンド、社会事業、健康関連業などのサービス業 |
| i. |
|
石油/ガソリン産業 |
| j. |
|
原子力産業 |
| k. |
|
下水、水道、電気、ガス等の公益事業団体 |
|
労働大臣 モハメド・マハディ・エルファハン(Mohammed Mahdi El-Farhan)博士
|
|
|
|
|
|
|
| 3) |
作業環境の危険に対する事業所および労働者の保護に関する指示
1996年法律第8号労働法第79条条項に従って公布
| 第1条 |
|
本指示、「作業環境の危険に対する事業所および労働者の保護に関する指示」は、1996年法律第8号労働法第79条条項に従って公布され、1998年6月16日の政府公報第4268号の発行と共に施行された。
|
| 第2条 |
|
労働者の使用する個人用保護具は、危険や害を取り除くか、あるいは許容レベルまで減少することができ、それらの危険や害に対して労働者の安全を保証できるものでなければならない。保護具は、適用した技術規格の説明に従って製造された高品質のものでなければならない。また、保護具を装着することにより、就労中の労働者の作業に支障があってはならない。
|
| 第3条 |
|
落下物による危険から頭部を保護するため、労働者にヘルメットを支給しなければならない。また、ヘルメットは、感電や溶けた金属などによる危険、様々な残骸、採掘、空港建設、プール/貯水池建設、歩道建設、港建設、橋梁建設、道路建設、トンネル建設、通信回線工事、下水道網建設、水道や電気工事、採鉱、石切、爆破、石油掘削、積み込み積み下ろし、木材や森林の伐採、消火活動、鉱物の溶融などからも労働者を保護するものとする。
また、屋外で就労する労働者で、塵埃へのばく露や、機械および作動中の工具への毛髪巻き込みの危険性がある者には、それらの危険から身を守るための特別な防御帽を配布しなければならない。保護帽は、正式認可を受けた方法によって製造されたものでなければならない。
|
|
|
|
|
|
|
| 4) |
1998年規則第43号―工具、産業機械、作業場からの保護と安全に関する規則
1996年法律第8号労働法第85条(c)項に従って公布
| 第1条 |
|
本規則の名称は、「1998年工具、産業機械、作業場(の危険性)からの保護と安全に関する規則」であり、政府公報への発表日をもって施行されるものとする*。
* 1998年8月1日発行の政府公報第4295号にて発表。
|
| 第2条 |
|
事業主、あるいは担当マネージャーは、法規則やルール、およびそれらに関する指示に従い、機械、電気、化学物質の危険、あるいは工具、産業機械、作業現場の危険性からの保護と安全のために、あらゆる予防措置を取らなければならない。
|
| 第3条 |
|
機械的危険
| a. |
|
以下に示す工具、機械に関しては、周辺、もしくはその一部を覆うなど必要な予防措置を取らなくてはならない。 |
| 1) |
水平回転軸が露出している場合、シリンダーの回転時を考慮し、軸の上部と下部を覆わなくてはならない。 |
| 2) |
柱状の垂直回転軸が露出している場合、露出部分を全て覆わなくてはならない。 |
| 3) |
ローラー |
| 4) |
150センチ以下の高さにある水平ベルトは、囲いで厳重に覆わなくてはならない。150センチ以上の高さにある水平ベルトの囲いは、ベルトを覆うに十分な高さにするものとし、ベルトは横に加え、底部からも囲いで覆うものとする。 |
| 5) |
縦方向に動作し、傾斜のあるベルト |
| 6) |
歯車は全体を厳重に覆わなくてはならない。 |
| 7) |
はめ歯歯車および鎖 |
| 8) |
のこぎり、切断機の刃、ミシン、せん孔機などの危険部分 |
|
| b. |
|
a項で示された覆いは以下に示すようなものでなくてはならない。 |
| 1) |
従業員や労働者が、作業時間全体を通して身体の一部たりとも危険箇所に触れないようなものであること。 |
| 2) |
危険エリアへの立ち入りを制限するものであること。 |
| 3) |
労働者の作業に支障を来さないものであること。 |
| 4) |
機械や工具、作業に適したものであり、生産の妨げにならないこと。 |
| 5) |
機械や工具の油差し、点検、調節、管理維持を妨げないものであること。 |
| 6) |
危険な形状や尖った角、危険を呈するような裾がないものであること。 |
| 7) |
労働者に向かって破片が飛散しないものであること。 |
|
|
| 第4条 |
|
A. 静電気の危険
|
静電気の危険に対し、あらゆる予防措置を取らなければならない。そのためには、発電機、変圧器、裁断機、巻き上げ機、せん孔機などの電動工具、設備、機械それぞれに技術的、工学的要件を考慮し、アース接続を行う必要がある。また、日常検査と維持管理に努め、常にそれら電気機器や接続が完全で良好な状態にあるようにしなければならない。加えて、作動時には通電しないが、アース接続で帯電する部品は、常に接続されていなければならない。 |
|
|
|
B. 動電気の危険
| 1. |
|
高圧電流に関しては、発電局、変電局、電力搬送ネットワークなど、それぞれの技術的、工学的要件を考慮したあらゆる予防措置を取る必要がある。高圧電流への警戒を呼びかける表示は必ず行わなければならない。高圧電流使用箇所には、専門技術者にのみ立ち入りを許可して維持管理を行うこと。 |
| 2. |
|
全ての電気機器には、電力切断キーを備えておくこと。電源切断キーは、作業場の特性を考慮し、作業の邪魔にならず、かつ緊急時にはすぐに使用出来るような見やすい場所に設置しなければならない。
|
| 3. |
|
電気ネットワークを保護するため、電圧、電流の大きさ、バランス、電力方向、温度上昇などのネットワーク上の危険を監視する機能のある補助用具を使用すること。 |
| 4. |
|
電気ケーブルやワイヤーの固定は、アース接続を行った状態で、適切な方法を使用して行うこと。 |
| 5. |
|
電気設備、工具、結線の固定、修理、維持の管理担当者は、高い技能を持った熟練の者でなければならない。 |
| 6. |
|
電気機器、電気設備、ケーブル、ワイヤー、接続部品、電源切断キーは、認可を受けたもので、作業場の条件に合致した標準仕様を備えたものでなければならない。 |
| 7. |
|
配電盤の前後には、乾燥木材製、あるいはゴム製その他の絶縁シートを取り付けること。 |
| 8. |
|
電気機器および電気設備は、必ず以下に示す技術要件に従って、安全かつ完全な方法で接続されなければならない。
(以下省略) |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
労働監督システム
|
|
| 1) |
1996年規則第56号―労働監督官規則
1996年法律第8号労働法第7条に従って公布
| 第1条 |
|
本規則の名称は、「1996年労働監督官規則」であり、政府公報への発表日をもって施行されるものとする。*
* 1996年11月31日発行の政府公報第4161号にて発表。
|
| 第2条 |
|
本規則で使用されている各用語、表現は、特に文脈で示されない限り以下に指定した意味を持つ。
省:労働省
大臣:労働大臣
事務局長:労働省事務局長
労働監督官:監督を行う権限を有する人物
マネージャー:労働省内の労働監督総局のマネージャー、および地方の労働雇用局のマネージャー
|
| 第3条 |
|
監督の目的
| a. |
労働環境、および就労期間中の労働者保護に関する法律規定の順守状況を確認する。 |
| b. |
事業主、労働者に対し、法律規定順守に関する技術的情報を提供し助言する。 |
| c. |
事業主及び経営者協会と、労働者及び労働組合との協調を推し進め、人間関係の改善および経済発展の実施を促進する。 |
| d. |
就労中の安全衛生の達成を考慮する。 |
| e. |
労働者数、労働者区分、必要な研修、その他の雇用状況など、労働市場の体系化に必要な情報を収集する。 |
|
| 第4条 |
|
| a. |
|
監督権限の取得には以下の条件が必要である。 |
|
1. |
最低限でも大学卒の学歴を保持していること。 |
|
2. |
省が提示するプログラムに従い、研修コースを少なくとも1つ受けていること。 |
|
3. |
労働監督官と共に6ヶ月間の監督活動実習を受けていること。 |
| b. |
|
労働監督官は、省の認可する形態の特別なカードを支給される。 |
|
| 第5条 |
|
労働監督官は作業場において、法律規定を遵守させなければならない。そのために、以下の権限を行使することができる。
| a. |
労働監督官には、就業時間内であればいつでも、単独で、もしくは政府専門官を伴って作業場に強制訪問をする権限がある。また、現場の監視が妨げられるおそれがある場合を除き、事業主もしくはその代理人に、事業所に訪問していることを告げることができる。 |
| b. |
労働監督官は、あらゆる帳簿、明細書などの事業関連書類の閲覧、写真撮影、複写を行うことができる。事業所で使用、生産された物質のサンプルを採取し、当該事業所の労働者の健康と安全への影響を調査の上、適宜事業主に報告することができる。 |
| c. |
労働監督官は、労働者の安全衛生を損なっている備品、計画、作業方法の不備があれば、使用者に必要な対策を取るよう要求することができる。また、適切な期限内に装置、機械、備品、作業方法を修正、改良するように要求することができる。 |
| d. |
労働監督官は、条項および法的手続きの順守違反状況など、事業所訪問の結果を報告書にまとめる権限がある。その他に訪問した事業所の状況や、そこで実施した活動などについても報告書を作成することができる。 |
|
| 第6条 |
|
労働監督官は、本規則に規定された職務を遂行する上で以下について考慮しなければならない。
| a. |
労働監督官は、法律条項違反に関して聞き得た批判に関する秘密を保持しなければならない。 |
| b. |
労働監督官は、職務を遂行する上で知り得た、あるいは開示された産業的、商業的取引やそれに関する情報について、退職後も秘密を保持しなければならない。 |
| c. |
労働監督官は、自分と利害関係のある事業所の監督を行ってはならない。 |
|
| 第7条 |
|
労働監督官として、その職務と矛盾し、職務を遂行する上での権威や中立性を損なうようないかなる責務も指導者に委託してはならない。
|
| 第8条 |
|
事業主は以下を行う責務がある。
| a. |
事業主は、労働監督官の職務遂行上必要なあらゆる便宜を図り、事業所のいかなる箇所についても立ち入りを妨げてはならない。 |
| b. |
事業主は、事業所、事業および労働者に関するあらゆる資料について、労働監督官が閲覧、写真撮影、複写できるようにしなければならない。 |
|
| 第9条 |
|
事業主は、事業所で発生した事故、労働災害、職業性疾病について、省の認可した用紙に記入し、定められた方法に従って労働監督官、および関連団体に報告しなければならない。
|
| 第10条 |
|
| a. |
|
マネージャーは総局内での監督活動について月報を作成し、事務局長に提出する。 |
| b. |
|
省は以下の項目について、ヨルダンで実施された監督活動に関する年次報告書を作成する。 |
|
1. |
労働監督総局の労働者 |
|
2. |
監督の対象となった事業所とその労働者数 |
|
3. |
視察訪問 |
|
4. |
違反とそれに対して課された処罰 |
|
5. |
労働災害、事故 |
|
6. |
職業性疾病 |
|
| 第11条 |
|
大臣は、本規則条項に反対、矛盾しない範囲で、本規則規定の実行上必要な指示を出すことができる。
|
| 第12条 |
|
1963年法律第1号労働監督法は、これを無効とする。 |
|
|
| 2) |
1997年規則第36号―非ヨルダン人労働者の労働許可手数料に関する規則
1996年法律第8号労働法第12条に従って発布
| 第1条 |
|
本規則の名称は「1997年非ヨルダン人労働者の労働許可手数料に関する規則」であり、政府公報への発表日をもって施行されるものとする。*
* 1987年8月2日発行の政府公報第4221号にて発表。
|
| 第2条 |
|
労働許可手数料および年次、あるいは1年以下の期間での更新手数料は、以下の通りである。この手数料は事業主から徴収するものとする。**
| a. |
|
農業以外の産業に従事する非アラブ人―300ディナール |
| b. |
|
農業以外の産業に従事するアラブ人―180ディナール |
| c. |
|
農業に従事する非アラブ人―120ディナール |
| d. |
|
農業に従事するアラブ人―60ディナール
|
** 2000年1月16日発行の政府公報第4406号で発表された「1999年規則第98号―非ヨルダン人労働者の労働許可手数料規則の修正」に従って修正された。
|
| 第3条 |
|
省は、非ヨルダン人の雇用に関する条件、手続き、およびその特殊な形式の労働許可について特別に出す指示など、本規則規定の実施に必要な指示を決定することができる。 |
|
|
|
|
|
| 3. |
労災補償保険スキーム |
|
社会保障組合(SSC)は労働者の労災を補償する機関であり、労災データは全てSSCからの出典である。
2003年には14,000件の労働災害とそれによる75名の死亡がSSCに報告され、600万ディナールにのぼる直接費用が発生した。
(表1)―2001年法律第19号社会保障組合(SSC)法より
|
(表1):SSC労働災害職業性疾病保険加入者に支給される保険金の概要
|
| 労働災害の結果 |
SSC支給の保険金 |
保険金受取人 |
| 一時的労働不能 |
a. 医療費 |
事業主 |
| b. けが人の搬送費用 |
事業主 |
| c. 日当―災害を被った労働者の賃金日額の75%(在宅) |
事業主 |
| 永久一部労働不能(30%未満) |
a.+b.+c.+ |
労働者 |
| d. 慰謝料(一時金) |
|
| =労働不能の割合×75%×労働者の月間賃金×36 |
|
| 永久完全労働不能(30%以上) |
a.+b.+c.+ |
労働者 |
| e. 月間給付金 |
|
| =労働不能の割合×75%×労働者の月間賃金+ |
|
| (その他の援助が必要な場合は25%) |
|
| 死亡 |
■葬儀費用 |
遺族 |
| ■保険金受取人への月間給付金 |
遺族 |
| =60%×月間賃金 |
|
|
| ※労働不能の割合はSSCの医療委員会によって決定される。 |
|
|
|
| 4. |
労働安全衛生機関(OSHI) |
|
労働安全衛生機関(OSHI)は労働安全衛生に関するトレーニングを実施している主要機関である。
OSHIは1983年に設立され、以下のサービスを提供している。
- トレーニングサービス
- 相談サービス
- 研究、実地調査
ヨルダン科学技術大学には、労働安全衛生の学士および修士課程がある。
|
|
|
| 5. |
労働安全衛生に関する問題点および対応策 |
|
労働安全衛生に関する行政政策の実行における主な問題は、以下の通りである。
- 労働安全衛生関連機関の乱立
- 機関間の連携不足
- 労働安全衛生スタッフの不足
- 労働安全衛生予算の不足
|
|
対応策
- 1つにまとまった労働安全衛生団体の設立
- 散在する労働安全衛生法令の一本化
- 労働安全衛生スタッフへの資格付与
- 労働安全衛生戦略の実施
|
|
|
社会保障組合(SSC)組織図
|