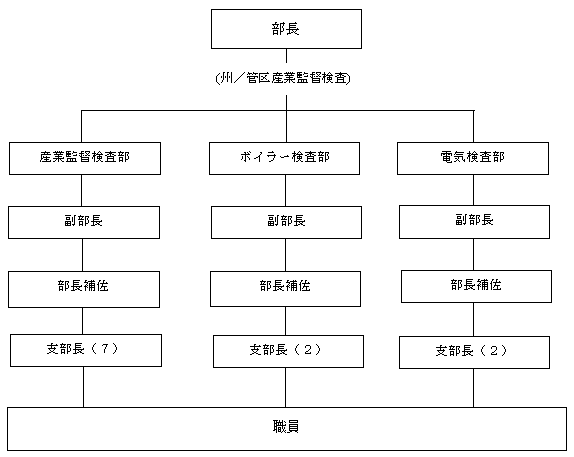|
このページは国際安全衛生センターの2008/03/31以前のページです。
|
 |
 |
|
|
平成16年度JICAセミナー カントリーレポート(ミャンマー)
資料出所:平成16年度JICA労働安全衛生政策セミナー カントリーレポート(ミャンマー)
(仮訳 国際安全衛生センター)
労働安全衛生に関する報告
序文
産業省(1)は、労働者を労働災害や職業性疾病から保護し、総合的安全衛生を向上させることにより、高い生産性で最大限の生産を実現することを目的とした、「労働安全衛生計画」を策定した。労働安全衛生政策における政府の主な役割は、特に産業部門で標準設定、法令の策定、人材の育成、労働安全衛生活動の監督、一般的監視を実施することである。基本原則は以下の通りである。
| (1) |
労働安全手続きの実施を定めた法律の遵守。(1951年工場法)
|
| (2) |
労働災害による負傷および損失を最小限に抑えて生産活動を行う。 |
| (3) |
労働安全衛生プログラムへの経営者、労働者の参加と教育及び、活動への自主的参加の促進。 |
組織
産業監督検査総局(DISI)は、産業省管轄下のサービス提供組織である。DISIの主な任務は以下の通りである。
- 民間企業の需要、事業上の要件をすくい上げ、それに対応することによってその奨励、育成に努めること。及び産業企業法に従って産業企業を管理監督すること。
- ボイラー法に従って蒸気ボイラーを登録、管理すること。
- 電気法に従って、民間、協同組合、公営部門の発電、送電、配電システムを監督、管理すること。
DISIはヤンゴンに本部があり、全州/管区の中心都市に支局を置いている。事務局長が組織の全責任を負い、事務次長の補佐を受けている。
労働安全衛生活動を実施するため、以下の部が各部長の指揮の下、本部に設置されている。
また、州/管区のボイラー検査部は、副部長を長として1州6管区の中心都市に設置されている。一例として、ヤンゴン管区の場合の組織図を本報告書巻末に添付した。
産業企業法
3馬力以上の動力(機械装置の種類は問わない)を使用し、10名以上の労働者を抱える産業企業は産業企業法に従って会社登録を行わなければならない。民間の産業企業の規模は小、中、大に区分されており、会社登録の有効期間は1年間である。
ボイラー法
ボイラー法 (Boilers Law) は、1924年のボイラー法 (Boilers Act) に替わり、1984年3月31日に施行された。本法令の目的はボイラーの爆発と労働災害に伴う損害、人命や資産の損失を防止し、ボイラーをその寿命まで効率的に使用することである。
電気法
電気法は、1937年電気規則に替わり、1984年に施行、1990年に改正されている。
電気法の制定は、一般市民の総合的安全のために、発電、送電、配電、電気使用を管理することが主な目的である。
民間産業企業法の基本原則は以下の通りである。
| (1) |
国内総生産に占める製造業の割合を高め、各営利企業の生産量の増加を計る。 |
| (2) |
産業効率の向上に向けて最新技術のノウハウを獲得し、生産された商品を国内のみならず海外の市場に販売する販路を確立する。 |
| (3) |
産業企業の発展、向上を通じて、地方と都市部の発展格差を縮小する。 |
| (4) |
就職機会を拡大する。 |
| (5) |
環境汚染を引き起こす技術ノウハウの使用を回避、縮小する。 |
| (6) |
エネルギーを経済的に使用する。 |
民間産業企業に会社登録許可を求める際、以下の要素について考慮されなければならない。
| (1) |
火災の危険から安全であること。 |
| (2) |
公害や汚染源にならないこと。 |
| (3) |
民間の産業企業の労働者の健康を害する原因となるものがなく、危険源となりうるものもないこと。 |
| (4) |
現行法を遵守すること。 |
労働者の安全衛生のための基準
| (1) |
労働者の健康増進のためにスポーツ施設を設置しなければならない。 |
| (2) |
労働者が病気の際は、工場の医務室で診療と十分な投薬が受けられるようにすること。医務室がない、あるいは医者が工場にいない場合は、最寄りの病院で適切な診療を受けられるように取りはかること。 |
| (3) |
高温下で働く、あるいは危険な化学物質を扱う労働者には、抵抗力を高めるため栄養価の高い食事や薬を与えなければならない。 |
| (4) |
工場施設および工場の敷地は、清潔で整頓された状態に保ち、便所や排水溝などから悪臭がしないようにすること。 |
| (5) |
工場の生産過程から発生する廃棄物および汚水を適切に処理し、除去すること。 |
| (6) |
工場の生産過程で大量の有害な粉じん、ヒューム、ガスが発生する場合は、ヒュームが室内にこもらないように排気口を設けるなどして、労働者がそれらを吸い込まないような処置を施さなければならない。 |
| (7) |
危険物質は全てに明白なラベル付けを行い、安全に貯蔵所に保管しなければならない。 |
| (8) |
各労働者の作業スペースが500立方フィート以下にならないようにすること。 |
| (9) |
作業場は自然光もしくは人工照明により十分な明るさがあるようにしなければならない。 |
| (10) |
適切な種類の保護眼鏡、面体、マスク、耳栓、耳覆い、手袋、その他作業着を労働者の人数分用意し、使用すること。 |
| (11) |
機械の可動部には全て適切な防御装置を取り付けること。 |
| (12) |
工場では、固定式の器、排水溜め、貯蔵槽、穴、床、開口部、隙間に厳重な覆いをするか、囲いを設置しなければならない。 |
| (13) |
労働者を火災から守るため、避難計画の策定、出口、通路の確保、火災報知器の設置をすること。 |
| (14) |
空気圧が極端に高い、もしくは低い場所で労働者を就労させてはならない。 |
| (15) |
労働者全員が、手軽に清潔な水が十分飲めるよう、効果的な手はずを整えること。 |
ボイラー検査部安全規則(抜粋)
| (1) |
ボイラー所有者は以下のようなボイラーを使用してはならない。 |
|
(a) 検定証が付いていないもの
(b) 検定証は付いているが、有効期限が切れているもの
(c) 検定証は付いているが、失効しているもの |
| (2) |
ボイラー所有者は、以下のことを守ること。 |
|
(a) ボイラーを許容圧力以上の圧力で使用してはならない。
(b) ボイラーの部品、蒸気管、給水管などの付属品の修理、改造、追加、取り替えを行ってはならない。 |
| (3) |
ボイラー所有者は、首席監督官、監督官、あるいは行政区担当ボイラー検査責任者が、検定証の提出を求めた際には、それに従うこと。(工場および一般労働法) |
ボイラー、電気検査部研修プログラム
以下に示す研修コースは、州/管区で10年から30年の経験を積んだ熟練監督官によって指導されている。
| 番号 |
研修コース名 |
期間 |
受講者数(人) |
| 1. |
ボイラー技士コース |
2004年1月19日〜2月27日 |
65 |
| 2. |
熟練電気技師コース |
2004年6月7日〜7月16日 |
65 |
| 3. |
ボイラー技士コース |
2004年8月9日〜12月10日 |
70 |
| 4. |
熟練電気技師コース |
2004年11月1日〜12月10日 |
70 |
研修の目的:
| (1) |
労働災害の頻度及び強度の減少 |
| (2) |
労働条件の向上 |
| (3) |
重大な労働災害の予防 |
| (4) |
労働災害の危険防止に対する労働者の興味、関心の誘発 |
研修の効果:
| (1) |
昨年一年間ボイラー事故による死亡を防ぐことができた。 |
| (2) |
労働災害の減少 |
|
(a) 蒸気によるやけど―10件
(b) ボイラーの重大な破損―5件 |
| (3) |
視覚、聴覚の喪失、電気ショック、火事などのボイラー修理作業による労働安全衛生上の災害が減少した。 |
ボイラー法 (Boiler Act) に関連のない以下のような圧力容器の爆発による労働災害が発生した。(ミャンマーには圧力容器法が存在しない)
| (1) |
米ぬか油工場でのDowthernボイラー爆発により2名死亡。(2001年) |
| (2) |
製紙工場の燃焼排ガス爆発により2名死亡。(2001年) |
| (3) |
製紙工場で乾燥工程作業を行う蒸気ローラーの爆発により2名死亡。(2002年) |
| (4) |
肥料工場の尿素合成炉の爆発により2名死亡。(2004年) |
ヤンゴンにある本部での研修が可能なため、研修を修了した公認ボイラー技士および電気技師の数は過去10年間でおよそ2,500人にのぼる。しかし企業数と比較すると人数が不足しているため、工場監督官部、一般労働法部、そして保健省の労働安全衛生部と合同で研修を行っている。労働災害の原因の概要は以下の通りである。
| (1) |
不注意、怠慢 |
| (2) |
技能の未熟さ |
| (3) |
予防対策の欠如 |
| (4) |
理解の不均衡 |
| (5) |
整備不足 |
| (6) |
労働者に供給すべき設備の不備 |
| (7) |
危険作業 |
| (8) |
修理の遅れ |
| (9) |
業務への注意力集中による安全衛生への認識不足 |
| (10) |
注意力の欠如 |
| (11) |
管理不足 |
労働災害
労働法によると労働災害は、「労働者を負傷させる、またはその可能性のある、計画外、予想外の出来事」と定義されている。労働災害のデータ収集は、工場からの届け出を基本に実施されている。
ボイラー法による労働災害の定義は、「ボイラーあるいは蒸気管の爆発、強度を弱め、爆発の誘因になる可能性のあるボイラーあるいは蒸気管への損傷」である。データ収集には所有者からの届け出だけではなく、その他の情報源を活用した現場調査も必要とされる。
1957年労働者補償法
労働者が業務上の理由、または就労中に発生した労働災害により負傷した場合、事業主は以下の条項に従って補償金を支払わなければならない。
| (1) |
負傷の結果死亡した場合 |
|
月間賃金の36カ月分に相当する金額 |
| (2) |
負傷の結果永久完全労働不能に陥った場合 |
|
月間賃金の1.4倍額の36カ月分 |
| (3) |
負傷により一部労働不能に陥った場合 |
|
下記一覧で特定された負傷により永久一部労働不能に陥った場合、同じ負傷で永久完全労働不能に陥った場合の補償金に、経済的稼得力の損失割合を掛けて算出する。
また、一覧外の負傷による終身一部労働不能も同じように経済稼得力の損失割合を計算の上、算出する。 |
経済的稼得力の損失割合
|
負傷 |
|
経済的稼得力の損失割合(%) |
| (i) |
肘あるいは上腕部からの右腕損失 |
|
70% |
| (ii) |
右腕肘下損失 |
|
60% |
| (iii) |
片目損失 |
|
30% |
| (iv) |
親指損失 |
|
25% |
| (v) |
人差し指損失 |
|
15% |
| (vi) |
足親指損失 |
|
10% |
| (vii) |
人指し指以外の損失 |
|
5% |
| (4) |
労働者は負傷の結果、一時的労働不能に陥った場合、労働災害発生日の16日目から労働不能の期間、あるいは5年間までのどちらか短い期間に、月間給与の半額を、月2回に分けて受け取ることができる。 |
1954年社会保障法
社会保障法は、就労中に労働災害、職業性疾病を被った労働者への給付金の支給を以下のように定めている。この給付金の恩恵を受けるためにも、全事業主および労働者は社会保障理事会(SSB)に加入し、月間賃金額に応じた会費を収めなければならない。SSBの支部は、国内の96町区に設置されている。
| (1) |
労働災害給付金 |
| (2) |
疾病給付金 |
| (3) |
出産給付金 |
| (4) |
葬儀補助金 |
新会費額(2003年)
| 支払い |
月間所得 |
会費 |
合計 |
| (チャット) |
事業主 |
労働者 |
| 最小 |
3000.00 |
75.00 |
45.00 |
120.00 |
| 最大 |
3000.00 〜 |
775.00 |
465.00 |
1240.00 |
新給付金額(2003年)
| 支払い |
一時的労働不能 |
永久労働不能 |
寡婦年金 |
| (チャット/日) |
(チャット/月) |
(チャット/月) |
| 最小 |
76.90 |
2000.00 |
800.00 |
| 最大 |
794.85 |
20666.65 |
8266.70 |
疾病に関してはSSBの診療所において無料で診察が受けられる。また、葬儀補助金は死亡者につき、定額20000.00チャットを受け取ることが出来る。
1951年一般労働法規則および規定(抜粋)
| (1) |
労働時間および休憩時間 |
|
一日8時間、週44時間(生産工程については48時間)を超えないようにすること。十分な休憩時間を与えること。 |
| (2) |
休暇 |
|
公務員は一年間に10日間の臨時休暇と30日間の有給休暇を取ることができる。民間企業の労働者は6日間の臨時休暇と10日間の有給休暇を取ることができる。 |
| (3) |
最低賃金法 |
| (4) |
児童法 |
| (5) |
労働福祉法 |
結論
ミャンマー産業が、市場経済の中で画一性のある商品を全力操業で生産するには、最大限の生産を生み出す高い生産性が必要である。これは、労働者が高いモラルを持って各自の責務を遂行し、欠勤を最小限に抑えることによってのみ達成される。労働安全衛生は、安全衛生の保護だけではなく促進をも意味する。労働安全衛生の向上は、躍動的なプロセスゆえに目標の達成には長い期間を要するが、この目標に向かって大きな一歩を踏み出すためには、国内で発生し得る災害の予防を期して政府と企業が共に協力しあわなければならない。以下は、職場の労働安全衛生が直面している課題である。
| (1) |
法令更新の遅れ |
| (2) |
労働衛生監督および監視政策の不足 |
|
| ・ |
労働環境の監視:現代的かつ適切な労働衛生研究所が無く、技術、設備、専門知識も十分ではない。 |
| ・ |
労働者の衛生に関する監督 |
| ・ |
職業性疾病および負傷の届け出を元にした統計 |
|
| (3) |
教育、研修、情報の不備 |
| (4) |
法実施機関の不足 |
| (5) |
ネットワークシステムの不足 |
組織図
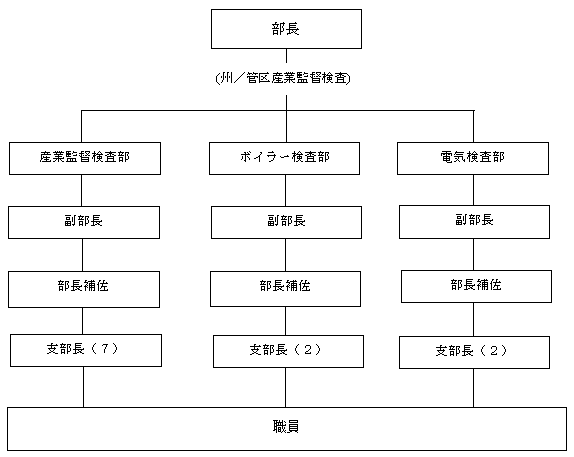
州/管区産業企業監督組織
| 1. |
州/管区産業監督検査担当官 |
|
議長 |
| 2. |
ボイラー検査 |
|
メンバー |
| 3. |
電気検査 |
|
メンバー |
| 4. |
開発委員会 |
|
メンバー |
| 5. |
工場および一般労働法監督部 |
|
メンバー |
| 6. |
社会保障理事会 |
|
メンバー |
| 7. |
内国歳入部 |
|
メンバー |
労働災害の損傷身体部位および性別による分布
| No. |
損傷身体部位 |
労働災害件数 |
| 男性 |
女性 |
合計 |
| 1 |
頭部、頸部 |
19 |
3 |
22 |
| 2 |
目 |
8 |
2 |
10 |
| 3 |
肩、上腕部、腕 |
11 |
4 |
15 |
| 4 |
胴体 |
5 |
- |
5 |
| 5 |
手、指 |
76 |
28 |
104 |
| 6 |
大腿部、膝、脚部 |
14 |
- |
14 |
| 7 |
足、つま先 |
46 |
10 |
56 |
| 8 |
複数部位への負傷 |
12 |
4 |
16 |
|
合計 |
191 |
51 |
242 |
|
|