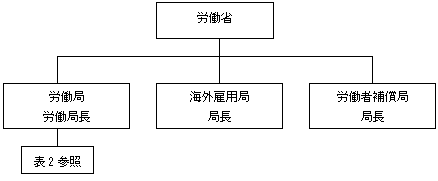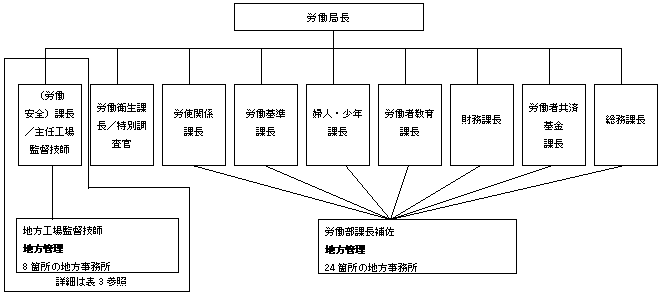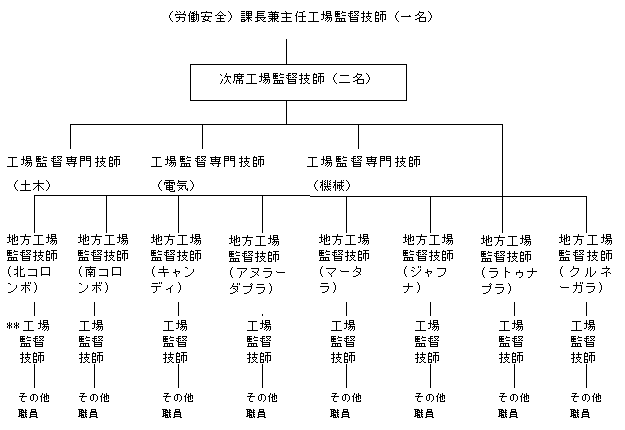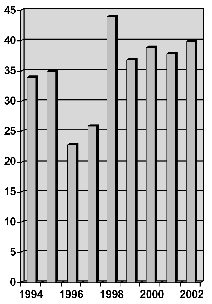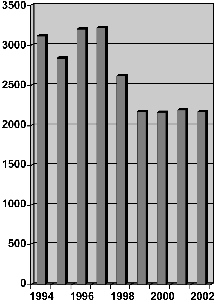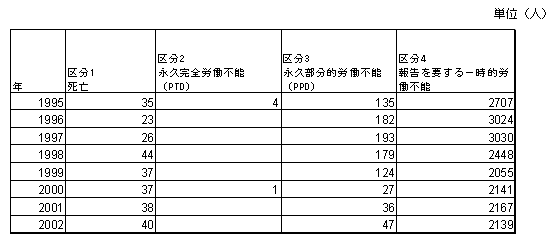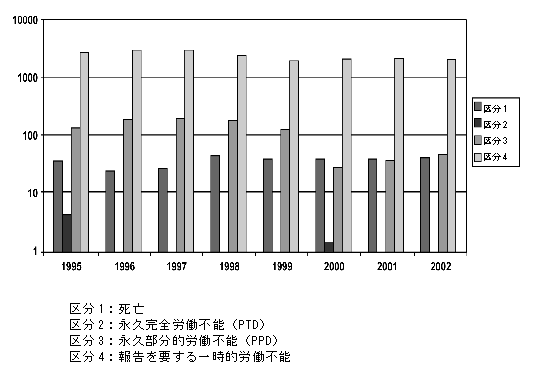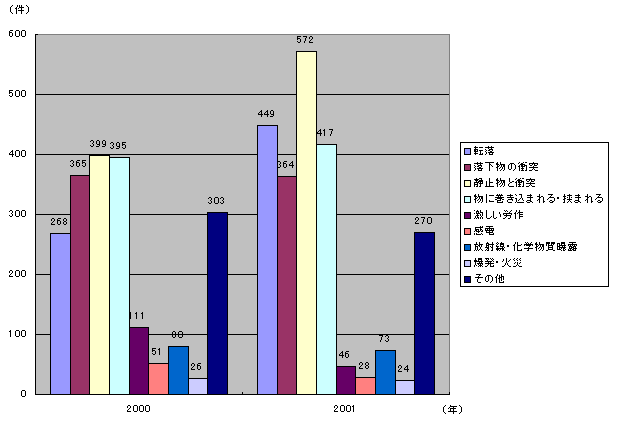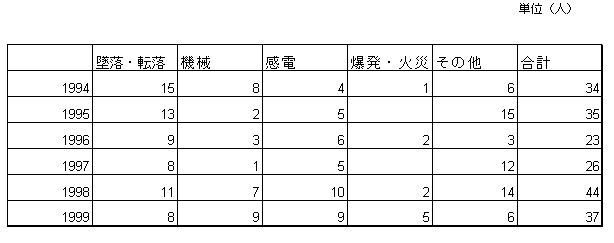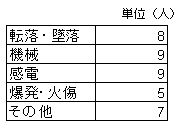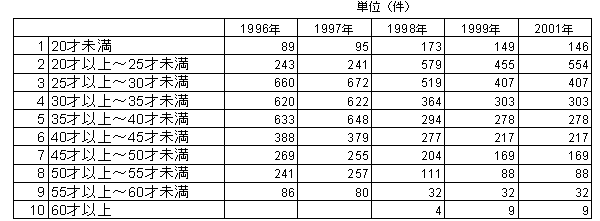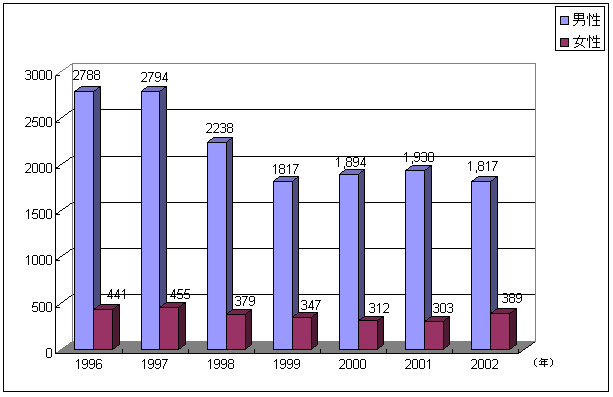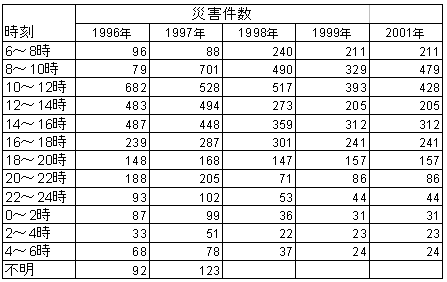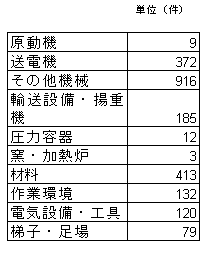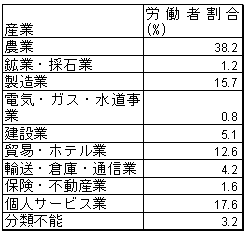国際安全衛生センタートップ >
国別情報(目次) >
スリランカ 平成16年度JICAセミナー カントリーレポート
|
平成16年度JICAセミナー カントリーレポート(スリランカ) 資料出所:平成16年度JICA労働安全衛生政策セミナー カントリーレポート(スリランカ)
1. 労働安全衛生活動の現状 1.1 労働安全衛生関連法令および規則 スリランカ民主社会主義共和国は、インド南岸沖のインド洋に浮かぶ総面積64,000平方キロメートルの島国である。人口は約1,810万人(最近の統計)で、うち600万人近くが労働人口に属する。近年、政府による開発活動が急速に拡大されたため労働人口が増加した。しかし、開発活動の拡大により、労働安全衛生上の問題が目立って発生する結果となった。1896年鉱業および機械保護法第2号が、工場における雇用を規定したスリランカ最初の法令である。 工場法第45号は、1937年の英国工場法を雛形に作成された法令で、1942年に導入された。この工場法第45号と1946年工場法第22号は統合され、1956年法律工場法第5巻第128章にまとめられた。その後1961年工場法改正第54号、1976年工場法改正第12号、1982年工場法改正第18号、そして2000年工場法改正第33号と四度の改正を経ている。 加えてスリランカには工場法に基づいて作られた工場労働者の安全、衛生、福祉に関する規則が存在する。工場法規定の施行を管理する権限が与えられているのは労働局長である。また、この法令の施行を目的に創設されたのが(労働安全)課長、主任工場監督技師を長とする労働安全課である。 工場法の規定は本法が工場と定義するあらゆる施設に適用される。その定義には民間工場に加え国営工場も含まれるが、軍用工場に限り戦時下には工場法の対象から除外するという規定がある。女性や若年者の雇用、職業性疾病の届出などに関する工場法の規定は、工場以外で、鉛作業が実施されている場合にも適用される。 工場法の施行を促進するために多数の規則が作られている。重要規則は以下の通りである。
上記以外にも、研削砥石、製材機械、電気および建築作業、産業騒音に関する規則が制定され、近い将来に法典に収録されることになっている。また、工場法の対象をあらゆる作業場に拡大するため法改正の手続きが進められている。 1.2 労働監督制度 労働安全課 労働安全課の責務は、工場法を施行し、スリランカの工場および建設労働者の安全、衛生、福祉を確保することである。この実施は労働工場監督部労働安全課に委任されているが、この組織の中心部分は1949年に英国工場監督官2名の協力で構成され、以後現在の技師24名、医務官1名の組織に拡大した。スリランカは6つの行政区に分かれており、各行政区の監督業務は1名の地方工場監督技師の主導で実施されている。国全体の統括は主任工場監督技師が次席工場監督技師の助けをかりて行っている。 また、工場監督技師は定期的に企業を監督し、安全、衛生、福祉に関する規定が守られ、効果的な方法で維持されているかを確認している。労働災害発生時には調査のための特別監督を行ってきた。衛生や安全に関する苦情を受けた場合には、優先的に調査している。「監督の際に労働条件や作業工程が有害、あるいは危険であると判断された場合、工場法第44条に基づく措置が採られ、有害要因や危険要因が除去された場合にのみ、工場および建設現場は操業を再開することができる。」と規定されている。 改正法の下では、新工場の建設にはまず工場監督技師からの承認を得なければならない。建設計画、機械の配置、工程、安全対策、火災予防、衛生要件といった初期段階の点検により、安全な労働環境をつくる必要性に対する産業資本家の意識向上を図ることになった。 1.3 労働者災害補償保険スキーム 労働者補償法は1934年に施行され、その後1957、1959、1976年に改正されている。本法は現在労働省の管轄となっており、労働者補償局長により管理されている。1990年の改正では給与の上限が撤廃され、負傷者に対する諸手当の増額のみならず、補償対象の職業性疾病の適用範囲も拡大された。本法は、雇用自体を本質的な原因とする労働災害や職業性疾病の被害者に対し、事業主が補償給付を支払う責任を負うことを原則としている。 労働者補償法で言うところの「労働者」とは、その内容に拘わらず取引や事業を目的として事業主と雇用契約を結んで就職、もしくは働いている人物を指す。その契約内容に関しては、1) 明示されたか、暗示的か、2) 口頭か文書上か、3) 奉仕契約、見習い契約、あるいは労働提供に関する個人的契約か、4) 賃金算定方法が時給制か、出来高制や他の方法か、5)契約の締結が本定義の施行前か後か、に関係なく全て雇用契約であると見なす。しかし、以下の2区分に該当する人物は、本法の定義する「労働者」に含まれない。
労働災害による傷害、あるいは死亡に対する責任を負う民間企業 労働者補償法第3条補則は、民間企業について次のように規定している。 雇用開始以降に労働者の傷害が発生した場合、事業主は法律の規定に従って補償金を支払う責任があるものとする。 事業主の責任が厳しく問われないのは以下の場合である。
補償額 労働者補償法の規定に基づく補償額は以下の通りである。
同一の労働災害から複数の傷害を負った場合、支払われる補償額は各傷害の補償額の合計となるが、その額が各傷害により永久完全労働不能となった場合に支払われる補償額を超えた場合にはその限りでない。
1.4 労働災害データおよび労災データ収集システムの概要 労働災害の報告に関する部分の改正は、1976年法律第12号工場法改正によって行われた。 この改正により、
上記の法律は、全ての製造業者、建設業者、サービス業者に適用される。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001年業種別労働災害統計 |
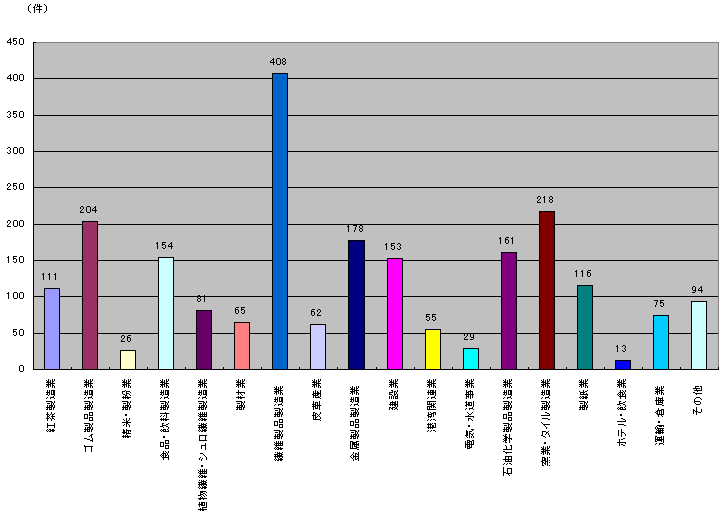 |
長年、感電死と墜落・転落が死亡災害の原因の大部分を占めるという状況が続いている。また、死亡災害の多くは建設業で発生しており、何年もの間一定の割合で確実に発生している。しかし、現行基本法では必要な規則が整備されていないため、これらの原因に対し、何の法的措置も取ることができない。しかし、現状を打開するため建設業における安全と安全な電気使用に関する規則が整備されつつあり、電気及び建設に関する規則が施行されれば大きく改善されるだろう。 工場法対象の作業場で発生した1999年の労働災害による損失労働日数が計算された。
損失労働日数は以下の通りである。
上記の数字は以下の労働災害が除外されている。
上記の統計値は損失の大きさを正確に表したものとは言えないが、スリランカの現在抱えている問題をより明確に理解するための目安である。 1.5 労働安全衛生に関する研修・教育について 有力な企業は、安全法や規則の遵守が十分であるのに対し、比較的小さな企業に関してはそうは言い切れない。主に教育や宣伝によって意識を高め、法律の遵守を徹底する努力が行われている。遵守の説得に失敗した場合、工場監督技師は法的手段に訴えるしかない。しかし、監督技師による起訴の多くが効を奏し、事業主が労働者にとって十分な安全衛生基準を提供するという望ましい結果を生んでいる。 また、工場監督技師は、労働安全衛生に関するセミナーや講義の開講、映画上映の企画運営に多くの時間を割いている。これらのプログラムは国内全域の雇用主、労働者および労働組合員を対象に実施されているが、中には同業種の経営者達を対象に企業ベースで実施されているものもある。そのようなプログラムは業種の実情に沿うように、綿密な計画の上で作成されている。最近工場監督技師は、労働安全衛生についての教育活動の対象を技術系や医学系の大学生にも拡大している。更に労働安全衛生の科目を職業訓練校や工業大学に導入しようという試みも行われている。 このようなプログラムとは別に、工場監督技師は査察以外でも企業の安全衛生や生産に関する問題について経営者にアドバイスしている。アドバイスは、機械の安全装置の設計、工場設備の配置、生産管理、工場の内部環境などに関係している。工場監督技師の医療担当員は、応急処置の方法や職業性疾病の予防についてもアドバイスを行っている。安全に関する展示会、ポスター大会、安全に関する演劇なども定期的に企画されている。コロンボにある労働省の建物内には、産業用機械の作業模型や写真、絵画を展示した安全技術館が常設されており、工場監督技師が実施している安全プログラムの優れた教材となっている。また、産業安全課は機械の作業模型や写真、その他を搭載した移動式の展示設備を使用し、国内全域で教育目的の展示会を開いている。この設備は、企業で使用される以外に公共の場でも展示され、労働安全に関する一般市民の意識向上に一役買っている。 国立経営研究所や、国立開発銀行、スリランカ工学研究所などの特殊機関でも講義が行われており、作業場に掲示するようにと安全ポスターが事業主に配布されている。 スリランカの法令(1942年工場法第45号)では、作業場から粉じん、ヒューム、騒音、熱、温度、換気不足といった危険要因を排除するよう規定しているが、規則として定められているのは採光・照明についてのみである。そのため、実際には「工場」と定義される施設からの要請や労働者からの苦情に対応するため、これらの要因を国際基準に従って測定している。労働安全課は労働衛生課の協力を得て、頻繁に以下の物理的・化学的環境パラメータをモニタリングしている。
2. 労働安全衛生に関する行政政策の実施に関して現在抱えている問題 途上国の多くが労働安全衛生管理に関する多数の問題を抱えている。スリランカにおいても工場監督技師や労働者らは類似した問題に直面している。主な問題の一部は以下のようなものである。 工場監督技師は、労働環境に関する問題の因子を測定する近代的な機器を持ち合わせていない。これら機器の多くは地方では手に入らない上に高価で、全ての地方担当官に十分な数を支給するのは不可能である。同様に、プログラムを実施する上で非常に重要な教材や視聴覚機器が地方担当官には入手できない。 安全センター:実際に使用されている一般的な機械の作業模型があると、労働者に安全衛生の細部まで説明できるため、非常に重宝である。しかし、作業模型の数も数個と限られており、コロンボにある本部の安全センターでしか使用することができない。 労働安全課で利用できる設備は数が限られている上、新人の工場監督技師は基本法令や工場監督、労働災害予防についての全般的な研修を受けなければならないが、職員不足のため着任後すぐに地方工場監督技師事務所に配属されてしまう。担当の地方で業務を行う中で、彼らは安全衛生に関する特殊な問題に数多く遭遇することになる。それらの問題は、工場監督専門技師による高度な調査が必要である場合が多いが、専門技師の数も足りないため労働安全衛生上の問題の改善には遅れが見られる。労働者に関しては、労働者の離職率が高いため、彼らの研修が工場監督技師にとって大きな問題になっている。また都市、農村共に、労働組織に加入していない労働者が多いことも問題を更に悪化させている。 また、工場法に基づく規則が不十分なため、工場法の施行自体に困難が生じている。しかし、この状況を乗り越えるために規則を整備する努力はされている。スリランカ政府は、労働安全衛生問題を初期段階で特定し、効果的な対策を実施できるような監督技師の育成や、問題のある分野を特定し、優先順位に沿った対処を可能にする統計データバンクの創設に関して先進国に支援を要請することも検討している。 最後に、折に触れて国際的なセミナーで意見を交換し、討議のフォローアップを行うことは価値あることだと申し上げて結びとしたい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||