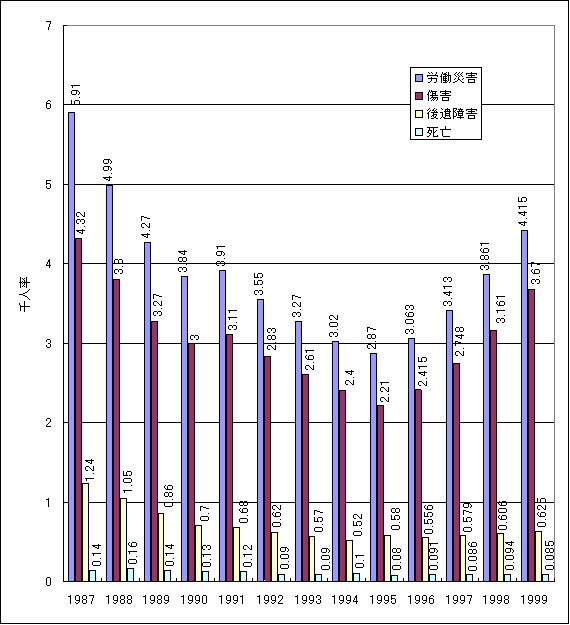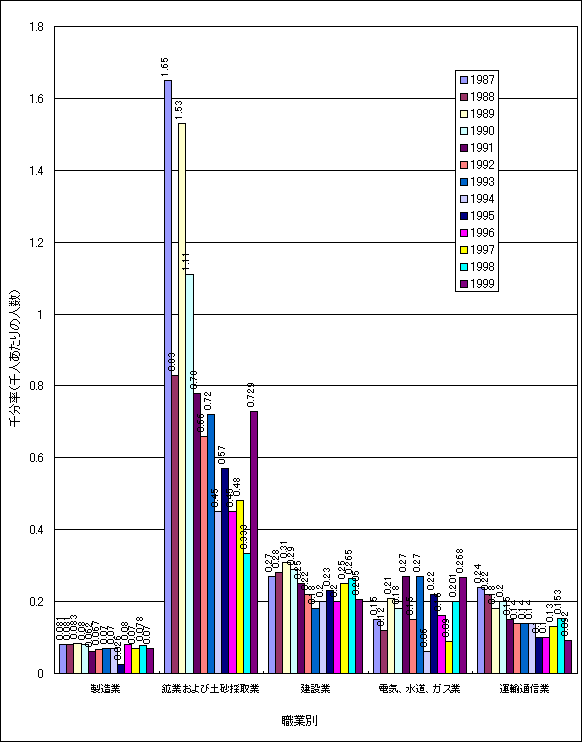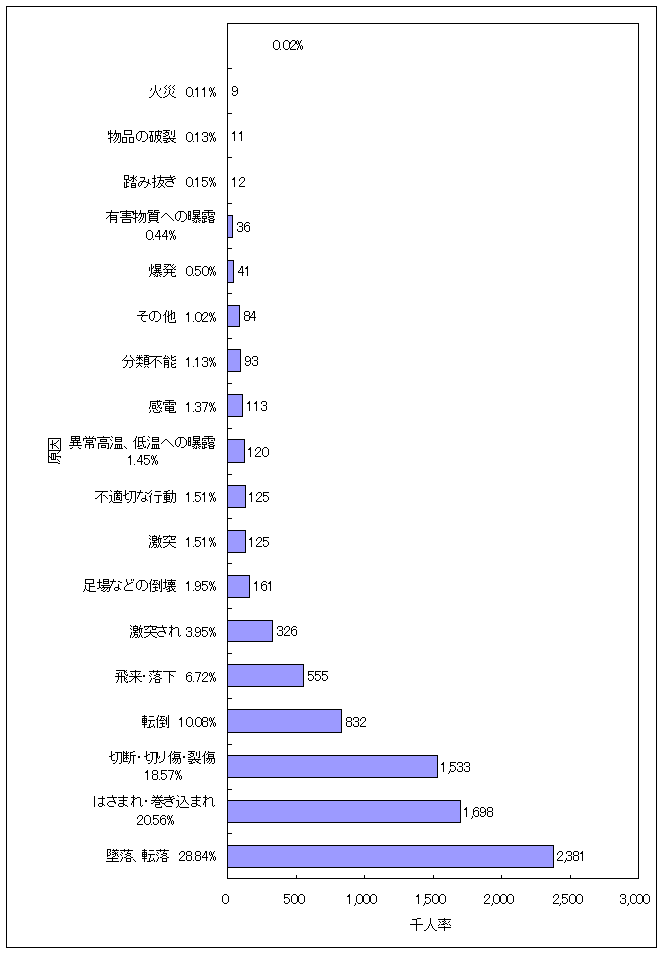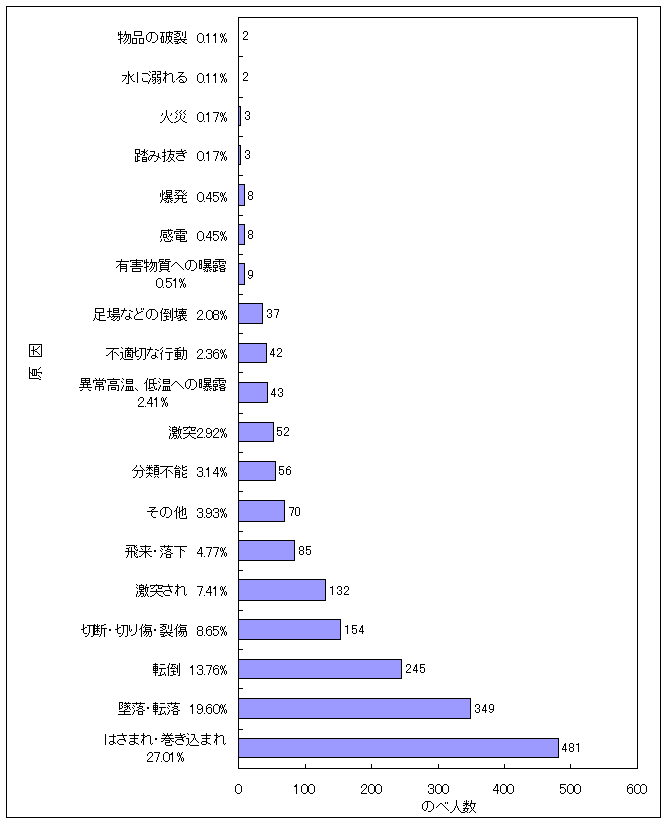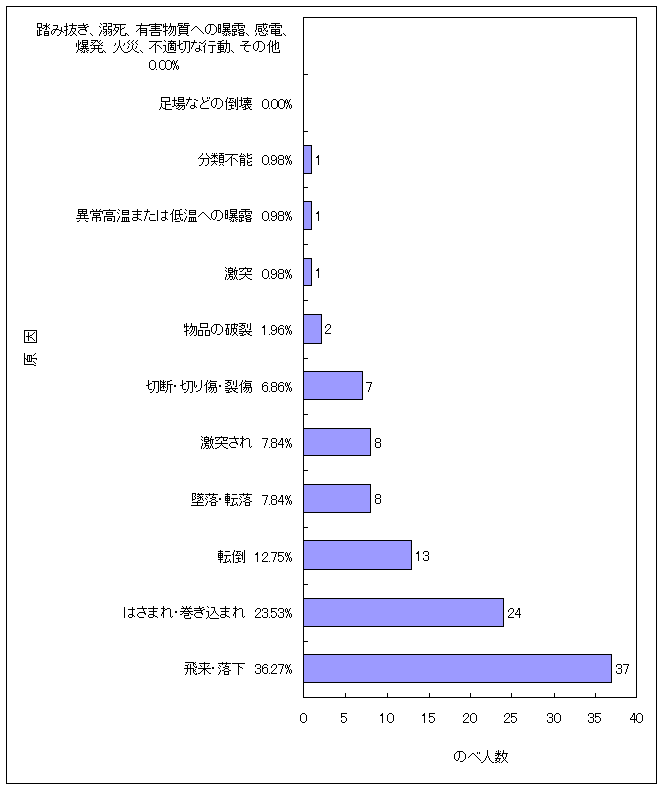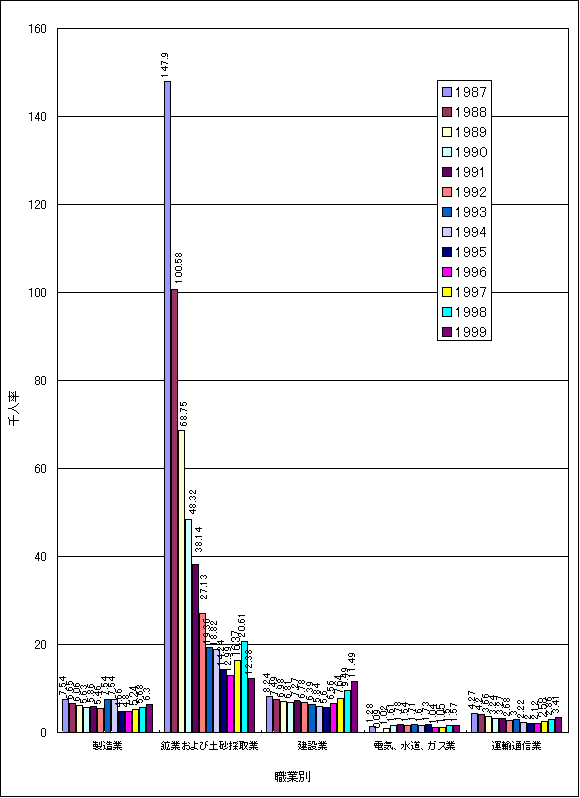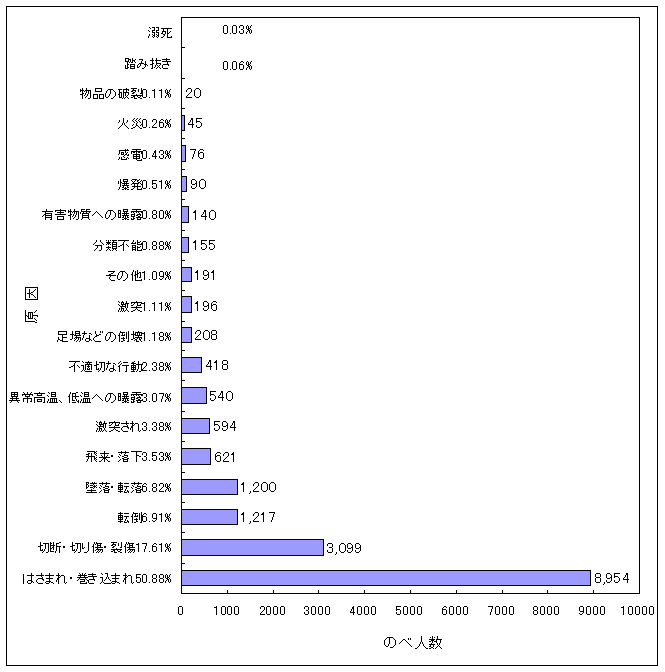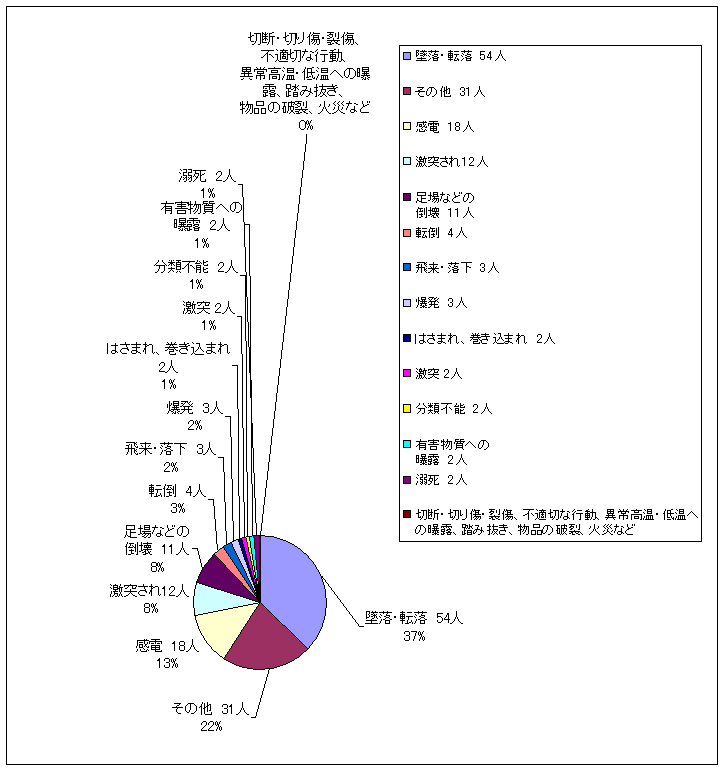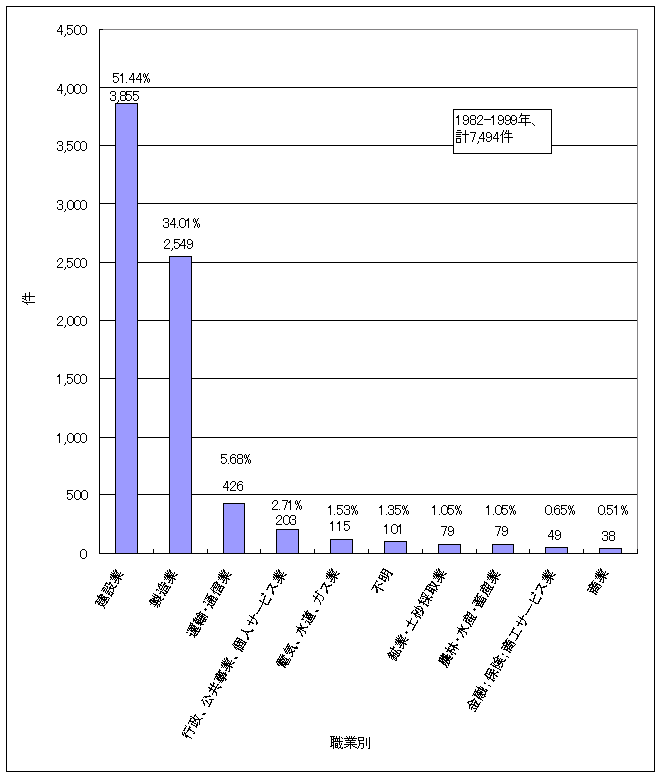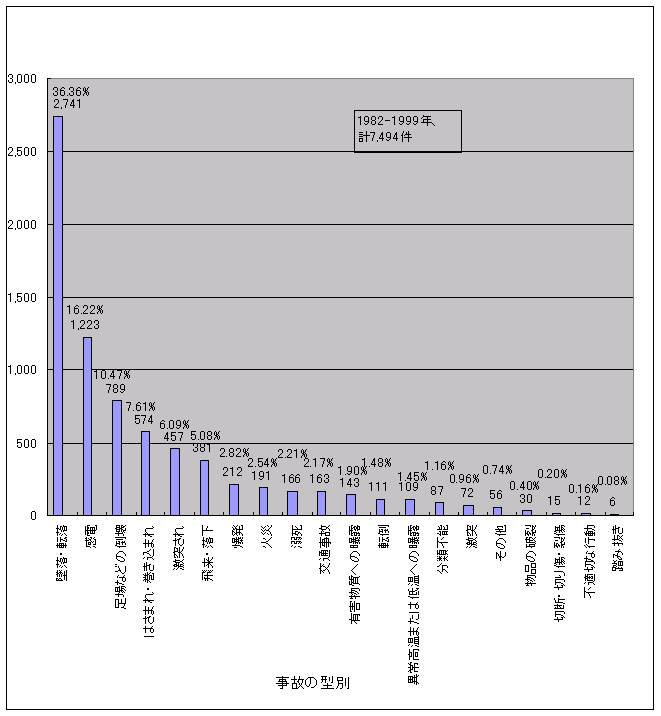■ 論文・翻訳 ■
中華民国における労働災害の概況
資料出所:中華民国工業安全衛生協会発行「月間工業安全衛生」2000年10月号
(訳 国際安全衛生センター)
蘇徳勝
1、 労働災害の概況
わが国における労働災害は、政府の努力と労使双方の協力により毎年減少の傾向にある。特に1987年以来各種の職業において労働災害の著しい減少が観察されている。ここに過去13年間における労働災害の概況と1999年度の労働災害の概況を分析してみよう。
一、過去13年間における労働災害の概況
わが国の全産業労働災害の状況は下の図1に示されている。これは過去13年間の労働災害の発生率を千人率であらわしたものである。これによると全産業の労働災害発生率は1987年の5.91が1999年には4.41に減少しており、減少率は25.38%である。傷害の千人率は4.52から3.69と18.36%の減少、後遺障害千人率は1.24から0.63と49.19%の減少、死亡の千人率は0.14から0.085と39.28%の減少となっている。ただし1995年からは増加の傾向にある。
図2には職業別に見た労働災害の千人率が示されている。これを見ると過去13年の間にどの職業分野においても著しい減少が見られることがわかる。製造業は7.54から6.30と16.44%の減少、鉱業および土砂採取業は147.90から12.38と91.62%の減少、運輸、通信業は4.27から3.41と20.14%の減少、ただし電気、水道、ガス業は1.28から1.51とわずかに増加(増加率は17.18%)、建設業は8.24から11.49と39.44%の増加を見ている。
図3は職業別に見た死亡の千人率である。製造業と電気、水道、ガス業が1999年にそれぞれ0.078、0.268とわずかな増加を見ているのを除いて、その他の運輸通信業、建設業などは減少している。
|
|
| 注: |
1. 資料提供:行政院労働委員会労災保険統計年報 |
|
2. 「労働災害千人率」は「傷害」「後遺障害」「死亡」を含む。(ただし交通事故は含まない) |
|
|
図1 わが国の過去13年間における全産業労働災害千人率の変化図
|
| 注: |
1. 資料提供:行政院労働委員会労災保険統計年報 |
|
2. 交通事故は含まない |
|
| 図2 過去13年間における職業別労働災害千人率の変化図 |
|
|
| 注: |
1. 資料提供:行政院労働委員会労災保険統計年報 |
|
2. 交通事故は含まない |
|
| 図3 過去13年間における職業別労働死亡者千人率の変化図 |
|
二、1999年における労働災害の概況
(一)全産業の労働者の傷害、後遺障害、死亡発生件数
1999年の労働災害の実際発生件数は下記の表1に示されているとおりである。これによると労災保険被保険者平均総数7,634,927人のうち仕事場で災害にあった者がのべ33,709人、交通事故者が11,093人であった。仕事場で災害にあった者33,709人のうち死亡者数が650人で、平均毎日1.78人の労働者が仕事場で死亡していることになる。また後遺障害者は4,815人で、平均毎日13.19人労働者が仕事場での災害により後遺障害者になっている。恒久的な後遺障害に至らない傷害者は28,244人で、平均して毎日77.38人(一時間につき3.22人)の労働者が仕事場で傷害を被っていることになる。一方労働中の交通事故による死亡者数は417人で、これは死亡者総数1,067人のうち39.08%を占め、無視できない比率である。
表1 1999年労働災害の概況
| 労災保険被保険者平均総数:7,634,927人 |
| 仕事場における災害:33,709人 |
| 交通事故による災害:11,093人 |
| 項 目 |
仕事場における災害 |
交通事故による災害 |
合 計 |
| 傷 害 |
28,244 |
10,099 |
38,343 |
| 後遺障害 |
4,815 |
577 |
5,392 |
| 死 亡 |
650 |
417 |
1,067 |
| 合 計 |
33,709 |
11,093 |
44,802 |
(二)製造業における労働者の傷害、後遺障害、死亡原因の分析
図4は1999年の製造業における傷害、後遺障害、死亡の原因を分析したものである。これは交通事故者数4,117人を除いた17,600人の傷害者、後遺障害者、死亡者だけを対象にしている。これによると主要な災害の原因ははさまれ・巻き込まれが50.88%と最高で、次に切断・切り傷・裂傷が17.61%、その後に転倒、墜落・転落、飛来・落下と続く。
|
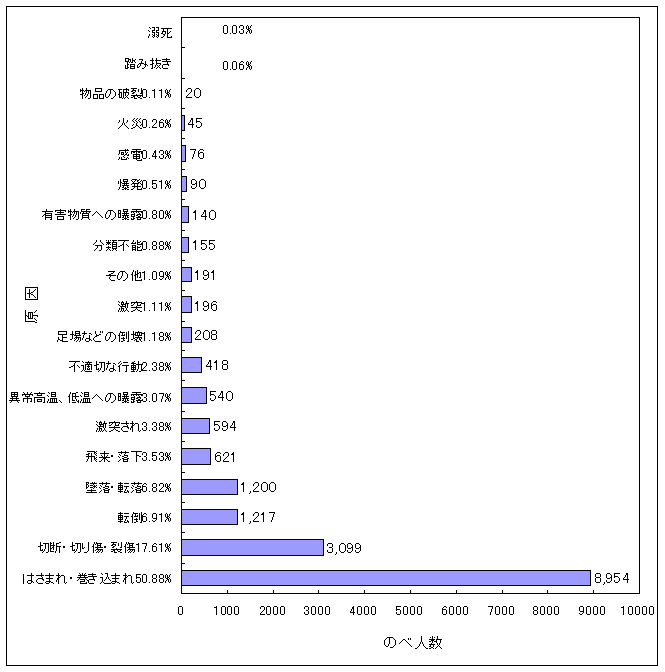 |
| 注: |
1. 資料提供:行政院労働委員会労災保険統計年報 |
|
2. 製造業労働災害者(のべ人数)の17,600人を対象。(ただし交通事故者4,117人は含まない) |
|
| 図4 1999年製造業労働災害の原因分析 |
|
(三)製造業における労動者の死亡原因の分析
図5は1999年の製造業における死亡の原因を分析したものである。これは交通事故者数106人を除いた219人の死亡者だけを対象にしている。これによると死亡の主な原因は墜落・転落の15.53%、はさまれ・巻き込まれが12.33%、作業場所(足場など)の崩壊によるものが10.96%、その後に激突され、転倒、爆発と続く。
|
 |
| 注: |
1. 資料提供:行政院労働委員会労災保険統計年報 |
|
2. 製造業労働災害者219人を対象。(ただし交通事故者106人は含まない) |
|
|
| 図5 1999年製造業労働災害における死亡原因の分析 |
(四)建設業における労働者の傷害、後遺障害、死亡原因の分析
図6は1999年の建設業における傷害、後遺障害、死亡の原因を分析したものである。これは交通事故者数1,773人を除いた8,257人の傷害者、後遺障害者、死亡者だけを対象にしている。これによると主要な災害の原因としては、墜落・転落の28.84%、はさまれ・巻き込まれが20.56%、切断・切り傷・裂傷が18.57%、転倒の10.08%などがあげられる。
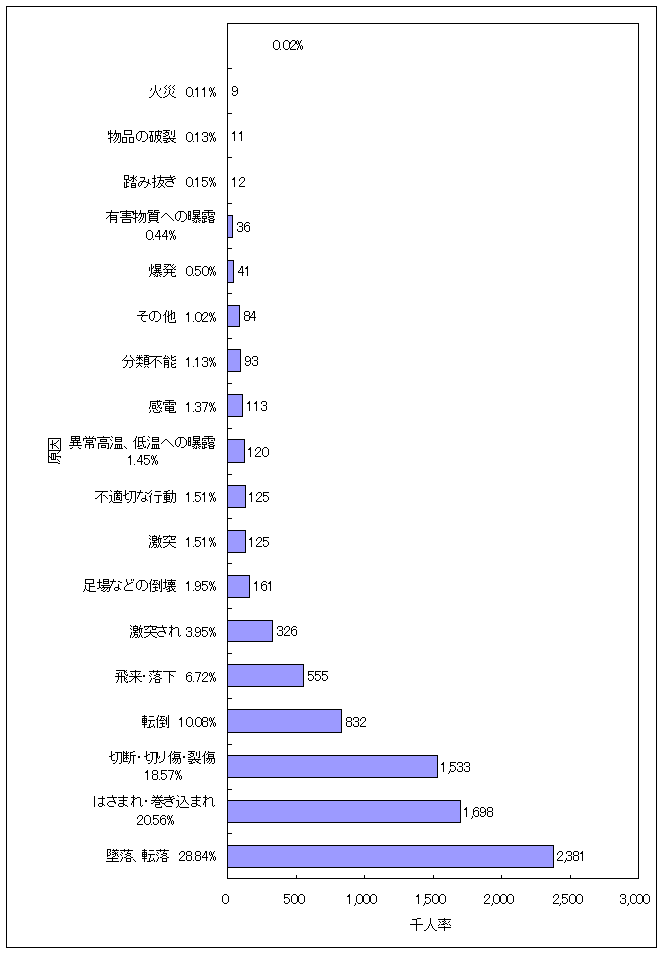 |
| 注: |
1. 資料提供:行政院労働委員会労災保険統計年報;千人率による |
|
2. 建設業労働災害者(のべ人数)8,257人を対象。(ただし交通事故者1,773人は含まない) |
|
|
| 図6 1999年建設業労働災害の原因分析 |
(五)建設業における労働者死亡原因の分析
図7は1999年の建設業における死亡の原因を分析したものである。これは交通事故者数58人を除いた146人の死亡者だけを対象にしている。これによると主要な災害の原因としては、墜落・転落が36.40%、その他の21.43%、感電の12.44%などがあり、激突され、足場などの倒壊、転倒がそれに続く。
|
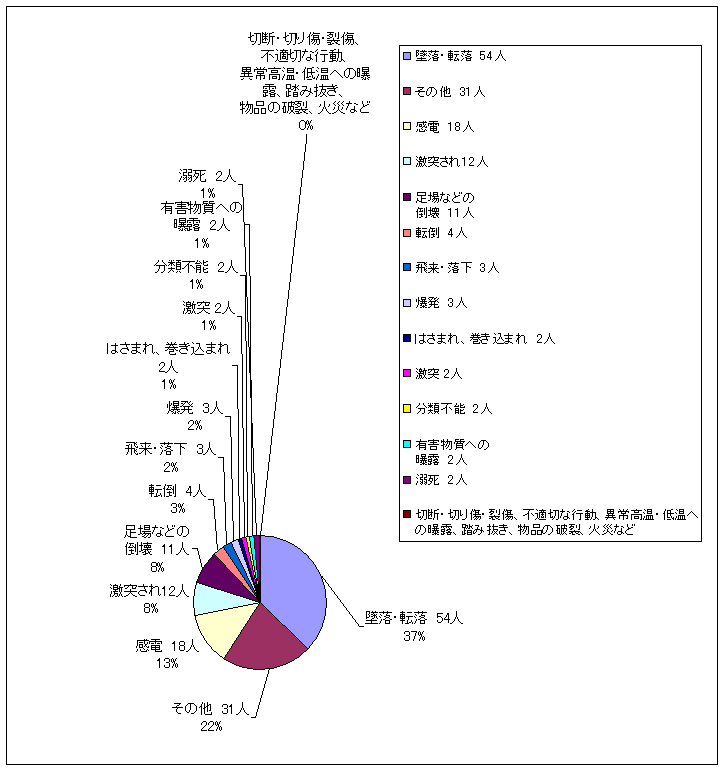 |
| 図7 1999年建設業労働災害における死亡原因の分析 |
|
(六)省略
(七)運輸通信業における労働者の傷害、後遺障害、死亡原因の分析
図9は1999年の運輸通信業における傷害、後遺障害、死亡の原因を分析したものである。これは1,781人の傷害者、後遺障害者、死亡者を対象にしている。これによると主要な災害の原因としては、はさまれ・巻き込まれが27.01%、墜落・転落が19.60%、転倒が13.76%、切断・切り傷・裂傷が8.65%となっており、激突され、飛来・落下、激突、異常高温または異常低温への暴露、などの理由がそれに続く。
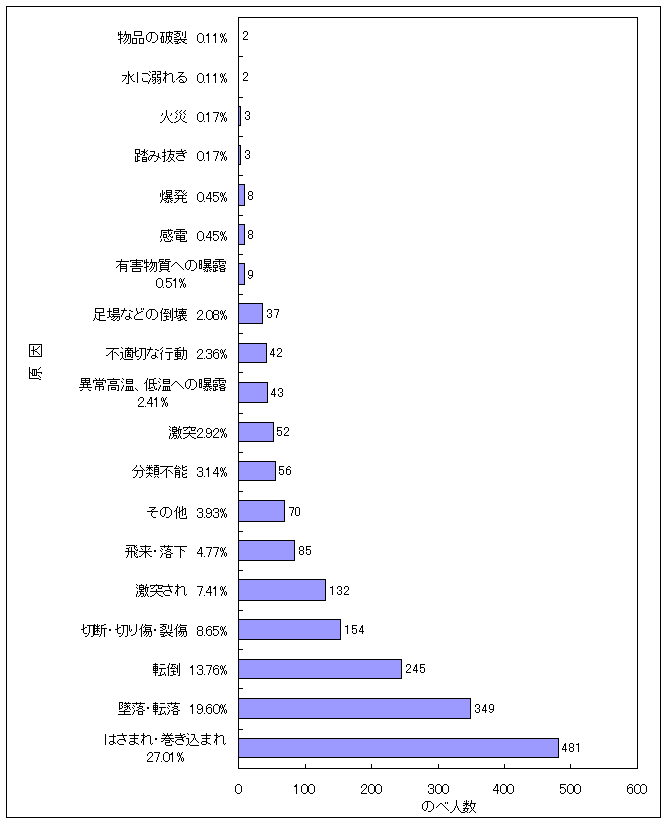 |
| 注: |
1. 資料提供:行政院労働委員会労災保険統計年報 |
|
2. 運輸通信業労働災害者(のべ人数)1,781人を対象。(ただし交通事故者1,008人は含まない) |
|
|
| 図9 1999年運輸通信業労働災害の原因分析 |
(八)鉱業および土砂採取業における労働者の傷害、後遺障害、死亡原因の分析
図10は1999年の鉱業および土砂採取業における傷害、後遺障害、死亡の原因を分析したものである。これは交通事故者数23人を除いた102人の傷害者、後遺障害者、死亡者だけを対象にしている。これによると主要な災害の原因としては、飛来・落下が36.27%、はさまれ・巻き込まれ23.53%、転倒の12.75%があり、墜落・転落、切断・切り傷・裂傷などの理由がそれに続く。
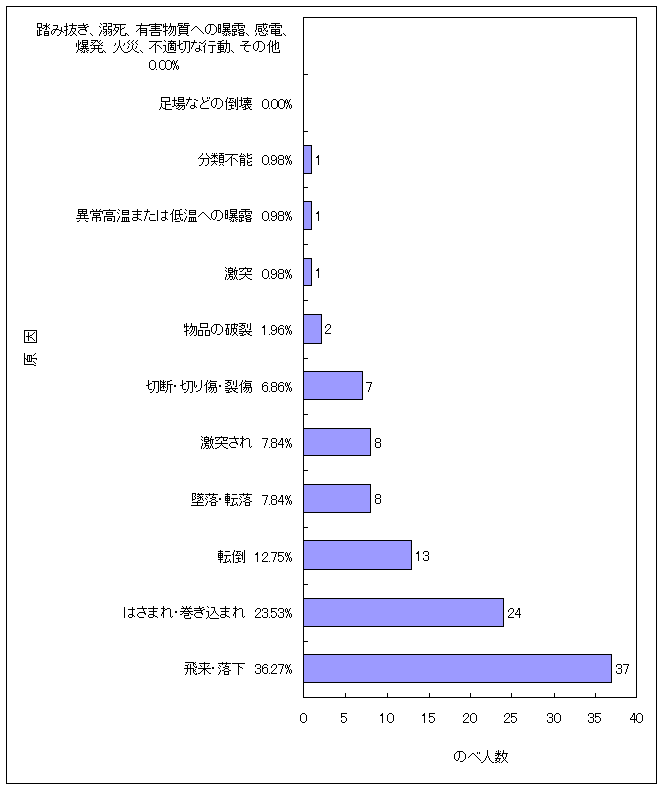 |
| 図10 1999年鉱業および土砂採取業労働災害の原因分析 |
(九)職業性疾病の概況
わが国は目下、職業性疾病の治療にあたる医師の養成に力を入れている。これにより職業性疾病の早期発見につとめ、被災者の利益を守るためである。労災保険と労働者健康定期検診の統計資料による職業性疾病の概況は下記のとおりである。
- 労災保険による職業性疾病の統計:表2は過去13年間労災保険が支給した職業性疾病の統計である。これによると:じん肺3,116件、聴力損失61件、鉛中毒23件、酸欠4件、職業性腰痛156件、職業と関連した癌24件、頭肩腕72件、異常気圧39件、放射線被爆8件、バイオハザード19件、石綿肺9件、職業性皮膚疾患26件、これらにその他の職業性疾病を加え合計4,050件。
- 労働者健康定期検診による職業性疾病の統計:労働者定期検診機構は1999年に、特に健康に有害な環境と見られる1,711の職場において健康検診を実施した。その結果、治療が必要または保護が必要と診断されたものが7人いた。
表2 過去13年間、労災保険が職業性疾病に適用された件数の統計(1987年から1999年)
資料提供:労災保険局
(図中の用語:「成因」とは「原因」を意味します。)
|
合計 |
原因
1 |
原因
2 |
原因
3 |
原因
4 |
原因
5 |
原因
6 |
原因
7 |
原因
8 |
原因
9 |
原因
10 |
原因
11 |
原因
12 |
原因
13 |
原因
14 |
原
因
15 |
原因
16 |
原因
17 |
原因
18 |
原因
19 |
原
因
20 |
| 総計 |
4050 |
9 |
8 |
39 |
|
61 |
156 |
8 |
72 |
4 |
23 |
16 |
19 |
1 |
9 |
3116 |
6 |
9 |
26 |
24 |
444 |
| 1987年 |
157 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
152 |
|
|
|
|
|
| 1988年 |
111 |
|
|
1 |
|
2 |
|
|
|
4 |
6 |
10 |
1 |
|
|
87 |
|
|
|
|
|
| 1989年 |
81 |
|
|
2 |
|
1 |
|
|
|
|
11 |
2 |
|
|
|
65 |
|
|
|
|
|
| 1990年 |
46 |
|
|
1 |
|
7 |
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
|
35 |
|
|
|
|
|
| 1991年 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
| 1992年 |
27 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
23 |
|
|
|
|
|
| 1993年 |
19 |
|
|
2 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
| 1994年 |
14 |
|
2 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
| 1995年 |
31 |
|
|
1 |
|
6 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
| 1996年 |
47 |
|
|
1 |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
1 |
| 1997年 |
150 |
|
|
6 |
|
5 |
15 |
|
10 |
|
|
|
|
|
1 |
106 |
|
|
|
|
7 |
| 1998年 |
543 |
1 |
|
12 |
|
12 |
61 |
|
23 |
|
|
|
|
|
6 |
261 |
|
|
1 |
|
166 |
| 1999年 |
2797 |
9 |
7 |
11 |
|
15 |
80 |
8 |
38 |
|
|
2 |
13 |
1 |
2 |
2280 |
6 |
9 |
25 |
24 |
270 |
| 原因番号: |
1眼科の疾病 2放射線被爆 3異常な気圧 4異常な温度 5騒音による聴力損失 6職業性腰痛 7振動による疾病 8頭肩腕傷害 9酸欠 10鉛とその化合物 11その他の重金属とその化合物 12バイオ・ハザード 13職業性喘息、アレルギー性肺炎 15じん肺とその合併症 16珪肺とその合併症 17石綿肺とその合併症 18職業性皮膚疾患 19職業と関係したガン 20その他職業による疾病または障害 |
|
|
三、重大な労働災害の調査
職場において労働者が一人死亡、または三人以上の傷害者を出すような災害が発生した場合、これを重大な労働災害と認定する。表三は、過去十数年(1982年から1999年)にわたって労働調査機構によってなされた調査の結果を示すもので、件数にして合計7,494件、被災人数にして9,908人を対象にまとめたものである。
(一) 災害の原因分析
過去十数年(1982年から1999年)にわたってなされた重大な労働災害の調査の結果をまとめた表3が示すとおり、不安全行動によるものが2,981件で39.72%、不安全な設備によるものが2,114件で28.17%、不安全な設備および行動によるものが2,179件で29.04%、原因不明のものが220件で4.37%であった。
(二) 雇用労働者人数による分析
重大な労働災害7,494件のうち、雇用労働者が100人以上の事業場で起きたものが1,329件で17.71%、30人以上99人以下の事業場で起きたものが1,138件で15.31%、29人以下の事業場で起きたものが5,027件で66.98%であった。
(三) 労働者の経歴による分析
重大な労働災害罹災者9,908人のうち、職場での経験が1年未満の者が5,397人で54.47%、1年以上5年未満の者が2,249人で22.70%、5年以上10年未満の者が817人で8.25%、10年以上の者が1,091人で11.01%であった。
(四) 労働者の安全・衛生の教育および研修との関係
重大な労働災害被災者9,908人のうち、職場での安全・衛生の教育や研修がなされていなかった者は7,685人で77.56%を占めていた。
表3 過去12年間における重大な労働災害調査の分析
分析と
類別 |
災害の原因 |
|
労働者の人数 |
合計 |
| 不安全な行動 |
不安全な設備 |
不安全な行動
および設備 |
不明 |
100人
以上 |
30人−
90人 |
29人
以下 |
設置 |
未設置 |
| 災害件数 |
2,981 |
2,114 |
2,179 |
220 |
1,329 |
1,138 |
5,027 |
3,361 |
4,133 |
7,494 |
| 比率(%) |
39.72 |
28.17 |
29.04 |
4.37 |
17.71 |
15.31 |
66.98 |
44.78 |
55.78 |
100 |
分析と
類別 |
仕事の経験年数 |
|
年齢の分布 |
1年
未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年
以上 |
15歳以上
16歳未満 |
16歳以上
20歳未満 |
20歳以上
40歳未満 |
40歳以上
60歳未満 |
60歳以上 |
不明 |
| 災害件数 |
5,397 |
2,249 |
817 |
1,091 |
79 |
638 |
5,168 |
3,409 |
513 |
101 |
| 比率(%) |
54.47 |
22.70 |
8.25 |
11.01 |
0.84 |
6.44 |
47.98 |
34.40 |
5.18 |
1.02 |
分析と
類別 |
教育、訓練の有無 |
|
合計 |
| すでに実施 |
まだ実施せず |
| 災害件数 |
2,223 |
7,685 |
9,908 |
| 比率(%) |
22.44 |
77.56 |
100 |
|
|
(五) 職業別による分析
図11は、過去十数年(1982年から1999年)にわたる労働災害件数を職業別にまとめたものである。これによると建設業が3,855件で51.44%、製造業が2,549件で34.01%、運輸通信業が426件で5.68%であった。
|
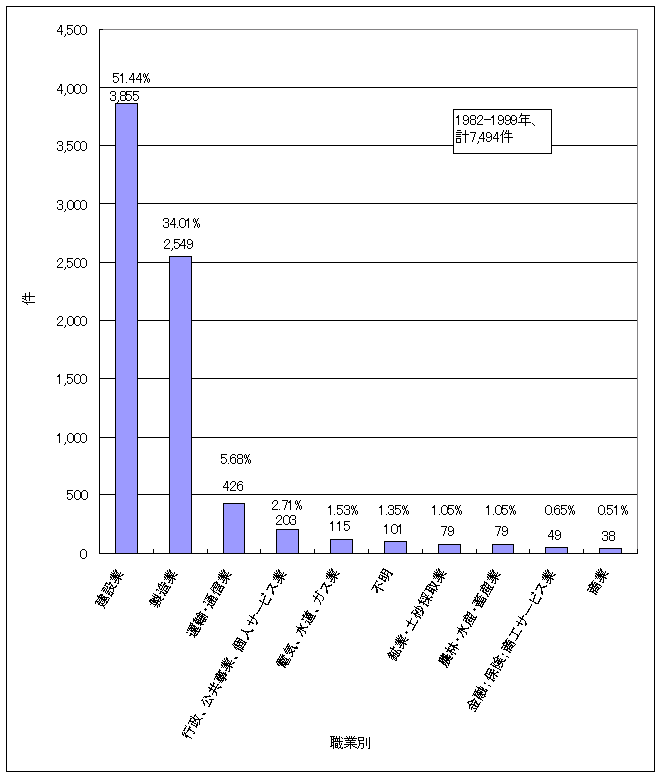 |
| 図11 過去18年間における重大な労働災害の職業別分析 |
|
(六) 事故の型別による分析
図12は、過去十数年(1982年から1999年)にわた労働災害件数を事故の型別にまとめたものである。これによると墜落・転落が2,741件で36.36%、感電が1,223件で16.22%、足場などの倒壊が789件で10.47%、はさまれ・巻き込まれが574件で7.61%、激突されが457件で5.60%、飛来・落下が381件で5.05%、爆発が212件で2.81%、火災が191件で7.53%と続く。
|
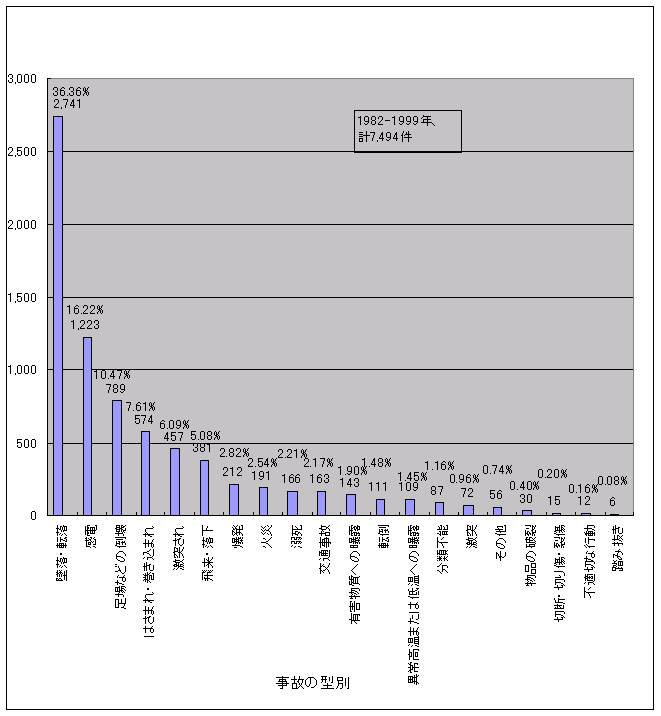 |
| 図12 過去18年間における重大な労働災害の事故の型別分析 |
|
2、労働災害の総合的分析
上記の労働災害の現況を分析してみると、下記のような問題点や結論が引き出せる。
- 各職業の労働災害は1987から1999年の全期間を通じて減少の傾向にあるが、ここ4年間では、ある職種には停滞、または増加さえ見られる。またこれらの千人率は先進諸国に比べるとまだまだ高く、何らかの積極的な対策を講じる必要がある。
- 1982から1999年の重大な労働災害を分析してみると、建設業の災害が3,855件発生しており、製造業の2,549件をはるかにしのぐ数となっている。建設業に携わる労働者の数が製造業の5分の1以下であることを考えると、建設業界における安全の管理および監督、また検査にいっそうの改善が求められる。
- 労災保険局の統計によると、交通事故で死亡した労働者が1999年に417人いた。これを仕事場での死亡者数650人と比較してみると、かなり大きな数であることがわかる。今後通勤の際の交通安全教育にも力を入れていくべきである。
- 災害のタイプを分析してみると、はさまれ・巻き込まれ、切断・切り傷・裂傷などが特に多い。機械設備の安全化が期待されるところである。また、転倒、墜落・転落などの事故は工場内の整理整頓、また高所作業での危険防止措置によって減らせるものである。この点でも将来の改善が期待されよう。
- 製造業における労働者の傷害部位を分析してみると、指、足、手などの傷害が頻発している。これは設備の安全化だけでなく、労働者の管理と教育にもさらなる注意が必要とされるところである。よりよい管理によって労働者各自に保護具の使用を徹底する必要がある。
- 1982年から1999年の重大な労働災害の種類を分析してみると、墜落・転落が最も多く全体の36.36%を占めている。これは、高所作業において安全ベルトや安全ネットなどを使用していないためである。各職場において自主検査やチェックを行ったり、安全衛生のための保護具の使用を奨励したりする必要があることが明らかである。次に多いのが感電で16.22%であるが、各職場における電気系統の安全検査の必要性を示唆している。また爆発と火災が全体の5.34%を占めている。これらの災害が起こる頻度は必ずしも多くないが、いったん起これば被害が甚大なものとなる。ゆえに危険物の管理や化学設備の安全化、また予防対策を強化する必要が認められる。
- 重大な労働災害を分析すると、安全教育や研修を受けていない労働者が起こした災害件数がそれを受けた者の3.45倍になっていることを明らかにしている。各企業や会社が安全教育と研修を怠ったために、労働者が作業の際に危険な行為や動作をとり、それが災害の原因になっていることは明らかである。この統計は、労働者の衛生と安全の教育および研修がいかに重要かを裏付けている。また、被災者の大多数は中小企業に雇用されているが、これらの中小企業は資金不足から労働者の安全教育への投資を渋る傾向にあるのも現状である。このような問題を解決するためには、政府の上級機関による検査や補導がさらに強化される必要があると言える。
- わが国の職業性疾病の症例は決して多いとは言えないが、労働者に対する定期検診の統計から明らかなのは、有害化学物質の影響下にさらされる環境を無視できないということである。今後、このような職場環境を有する企業に対する検査や補導をより効果的に行い、安全設備の徹底化や、定期健康診断の実施を促し、職業性疾病の予防に努めるべきである。
3、労働災害予防のための今後の重点活動
わが国の労働災害の発生比率は、現時点では先進諸国に比べてまだまだ高く、改善が求められている。労働災害の発生を予防するため、本会では現在の台湾における実際の状況と必要を考慮しつつ、下記の安全と衛生向上のための活動を行っている:
一、 わが国における安全および衛生標準の法制化と国際化
労働安全衛生法修正案は1991年4月30日に立法院を通過し、同年5月17日に総統令によって公布された。この修正案には安全・衛生の設備や措置の増加を求める条文が多数盛り込まれていた。この修正法に基づいて関係する法規の見直しと検討がなされ、修正案にある要求に合致するように改定がなされた。それらの関連法規やガイドラインには「有機溶液による中毒予防に関する規則」「特定の化学物質による危害予防の標準」「年少および女性労働者の従事が不適格である労働の認定基準」「作業環境点検の実施方法」「港湾労働の安全・衛生施設の標準」「労働安全衛生組織の管理および自主検査のガイドライン」「機械、器具の安全確認の標準」「各企業および関係する団体に対して安全・衛生を奨励し援助するためのガイドライン」「危険物および有害物質に関する規定」「花火、爆竹製造業の安全・衛生措置に関する標準」「行政院労働雇用委員会職業性疾病鑑定委員会の組織規程」「指定の医療機関が労働者の身体検査および健康検査を行うためのガイドライン」「労働安全衛生情報センター設置に関するガイドライン」「建設土木安全衛生措置に関する規定」「労働安全衛生措置に関する規定」「エレベーター、リフト、起重機などの安全規定」「危険を伴う機械と施設に関する安全規定」「ボイラーと圧力容器に関する安全規定」「精密作業に従事する労働者の視力保護に関する標準」「労働者の作業環境内で許容される空中有害物質の濃度標準」「異常気圧が及ぼす危険に関する予防標準」「鉛中毒を予防するための規定」「労働者の健康を保護するための規定」「高所作業者を保護する措置に関する標準」「労働者の安全・衛生に関する教育と研修のための規定」「鉱業労働者の安全措置に関する標準」「酸欠症予防に関する規定」「4−アルキル鉛中毒を予防するための規定」「重労働に従事する労働者を保護するための措置標準」「紛じんによる害を予防するための標準」「労働安全衛生標示設置に関する規則」「オートメーションとロボットによる危険を予防するための標準」「機械と器具を検査する機構を指定するためのガイドライン」などがある。これらの関連法規やガイドラインは現代社会の必要に応じたもので、国内の現状を踏まえて作られており、国際的にも受け入れられるものである。
二、 安全衛生に関する各種制度の制定
本会は下記のさまざまな制度の制定を促進してきた:労働災害報告統計制度、機械と器具の検査および安全表示制度、中小企業が安全装置を購入するよう指導、援助するための制度、危険性のある機械のメンテナンスおよび管理の制度、危険標識の掲示制度、作業環境の検査制度、労働者の健康管理制度、労働災害の報告制度、重大な労働災害の報告制度、危険な作業環境の事前審査および検査の制度、および職業性疾病の判定、診療、報告に関する制度。
三、 安全と衛生向上の呼びかけと推奨
本会はまた、各企業体に対して安全・衛生を考慮した経営理念を採用するよう提唱してきた。この理念によれば、労働者自身が安全衛生に関する提案を行うことを奨励したり、労働組合が積極的に労働者の健康促進運動に携わるよう指導するなど、労働者自身の安全衛生の意識を向上させ、労働者という人的資源を最大限に活用することを目的にしている。また各地において防災や安全衛生に関与する団体や機関を設立したり、相互の交流を図ったりするための活動も活発に行ってきた。たとえば林園工業区をはじめとする13地区の防災組織に対する指導、また安全・衛生を促進するその他の団体への技術指導、そして国際的な安全衛生団体との交流などがその一部である。
四、 労働安全検査人員の有効運用と安全検査の推進
- 健全な労働安全検査の法制化と実施の推進。
- 労働安全検査の目標設定と目標達成の確認;安全検査の効果改善。
- 「建設業における労働災害予防措置」の実施と建設業の監督、検査の強化。
- 危険な機械や設備の安全検査を代理機関に委託したり、ボランティアの協力を得るなど、社会の人的資源を活用することにより、一層広範囲また徹底的な検査活動を促進する。
- 安全と衛生の検査を各項目に分けて集中的に行う。特に危険な職種や場所についてはこのような検査を綿密に行う。
- 安全と衛生の検査を各地域に分けて集中的に行う。必要に応じて監督範囲を広げ、検査する企業や会社の基本資料を十分に把握する。
- 職業性疾病の予防検査の実施を強化する。
- 危険な職場の審査や検査の実施を確認する。特に事前審査と改善後の確認検査が確実になされるようにする。
- 各企業や会社が自主検査の制度を設け実施するよう援助する。この自主検査により往々に危険が予知でき、多くの災害を事前に予防できるからである。
五、 安全衛生の教育の強化と、安全衛生文化の形成
- 中学、高校、大学、また各種職業学校における安全衛生教育を推進し、安全衛生に対する正しい態度を育成する。
- マスメディアを通して安全衛生に関する知識の普及を図り、大衆の参加を呼びかける。
- 高度の危険性を有する職場において、事業者が労働者に安全衛生と危険の予防に関する訓練を施すよう指導と援助を行う。
- 職場経験の浅い者、職場での部署が変更になった者、安全衛生の係員、高度の危険を有する職場で働く作業員などに安全衛生に関する訓練と教育を施し、災害の予防を奨励する。
- 地域内、また組織内において安全衛生団体が縦横の関係を強化し相互間での連絡と協力をより密接なものにするよう指導する。
- 労働者、事業者の双方における職業性疾病予防に関する認識を高める。
- 労働者の安全衛生の管理に関して特に成績優秀な地域を選抜し表彰するなどして、全国的な安全と衛生の意識の強化を図る。
- 労働者の安全と衛生に関する証明書、許可証発行の制度が設けられるよう努力する。
六、 ゼロ災運動の推進と各職場における徹底
- 人間を重視したゼロ災運動の推進により、労働者が職場における潜在的危険を絶えず認識するように助ける。職場単位で安全衛生グループなどを組織し、危険に対する無知を一掃し、予防の教育運動を展開する。先手は必勝の秘訣である。
- ゼロ災運動の指導員を育成する。十分に資格を備えた者がその任にあたるようにする。
- 中小企業における安全と衛生の運動を強化する。
- 一般のボランティアが安全と衛生の教育普及運動に参加するよう協力を求め、制度化する。安全衛生の概念が社会の各階層に浸透することがこの目標である。
- 建設業など特に危険な職場での現場教育を徹底し、潜在的な無知を一掃する運動を推進する。
七、 自主管理と自主検査の推進
- 各企業、団体における安全衛生組織、人員または管理制度の健全化を図り、真の安全衛生管理がなされるよう見届ける。
- 各企業、団体に、安全と衛生に関する各種自主検査のガイドラインを提供し自主検査実施の際の参考にする。
- 建設業者が自主管理体制を設立するよう指導して、建設現場における安全の管理に努めるように促す。
- 事業単位による安全と衛生の自主管理実施のガイドライン」を制定し、各企業、団体が積極的に労働者の安全衛生に注意するよう奨励する。
- 建設における工程検査または完成検査の際に、検査にあたる機関が安全衛生の内容や費用について確認を行うような制度を導入する。またそのためのガイドラインを制定する。
- 安全衛生の評価基準を定める。管理制度の優良な企業や団体に対して五段階からなる等級による評価点を与え、この運動推進の励みとする。
- 政府の財政部台北市財産保険商業組合と協力し「自主管理の優良な企業や団体の保険料引き下げに関するガイドライン」を制定し、各企業や団体が自主的に人力、財力を投入して安全衛生を改善し、労働災害発生の危険を減らすための助けとする。
八、 安全衛生に関する科学技術開発の促進
- 建設現場における墜落・転落事故や足場などの倒壊事故を予防するための技術研究や、より安全な施工方法の開発研究を強化する。また災害予防や安全施工法に関するガイドブックなどを発行し、その普及に努め、技術の交流をも図る。
- 特に危険な機械や設備に関する法規、標準、または安全評価の基準などを定める。また国内における高圧ガス設備の検査技術を確立し、国内の事情に合った機械や設備の安全監視システムを開発する。
- 国内すべての化学工場または関連施設において、毒性を有する高圧ガスの使用、貯蔵、処理状況の調査を実施する。また危険な化学物質の保管や運送に関する安全評価を行う。さらに半導体工場または関連施設における有毒ガスに関する研究を推進する。
- 感電防止に関する研究を進め、改善策を具体的に打ち出す。また電気施設の爆発や火災を予防するための技術を確立し、そのためのガイドラインを制定する。
- 国内国外の安全と衛生に関する保護具や機器の比較研究を行い、国内の現状に適合した性能テストの標準を定める。また台湾での使用に合った保護具や機器の安全標準を定める。
- 建設土木会社による安全管理、また請負人による安全管理の方法を示したガイドラインを制定する。これらは安全な施工を行う方法を具体的に示した規範となるべきである。
- 国内国外の職業性疾病や労働災害に関する資料を集め研究する。また国内における職業性疾病や労働災害の観察、追跡体制を強化する。
- 危険な環境で働く労働者の実態調査を行う。また労働が労働者の筋肉や骨格に及ぼす影響の研究を強化する。労働者の潜在的危険の実況を知るためである。
- 人間工学の概念を応用して、よりよい労働環境の推進を行う。
- インターネットによる「安全と衛生に関するディスカッションルーム」などを設け、情報の提供や意見の交換を促進する。
4、将来の展望
労働者の安全と衛生を向上させるためになすべきことはまだまだ多くあり、多くの分野にわたっている。この活動は、最終的にはわが国の産業そのもののレベルアップや生産力の増強、また企業の健全な経営やひいては利潤の増大など計り知れない益をもたらすものである。これらの事実をふまえて、本会は上記の活動に加え、これから行うべきこととして下記の活動や運動の実行を目標にしている:
| (一) |
労働災害に遭った労働者の保護:「労働災害被害者保護法」の制定。これは現行の労働基準法や労災保険による補償の不足分を補うためのものであり、被災者およびその家族に対する補助をいっそう実質的なものにし、後遺障害のある者に対して再就職のための援助を行うことを目的としている。 |
|
| (二) |
高圧ガスを扱う工業、爆竹工場、農薬工場など、特に危険な職場における安全評価と改善を徹底化させる。労働者自身に潜在的危険を認識させ、人的原因による事故や災害を予防する。 |
|
| (三) |
労働災害の通報システムを強化する。労働災害の実況を絶えず把握できるようにする。 |
|
| (四) |
各企業や特に危険な職場における安全と衛生に関する教育訓練に加え、全国民に対する普遍的な安全と衛生に関する国民教育を推進する。これは政府の教育部の協力により、大学から小学校にいたる各種の教育機関においてなされるようにするべきである。このような教育により、将来の労働人口が安全や衛生に関する基本的な知識を身に付けることになるからである。また各種の安全や衛生に関する検定試験、技能試験、免許の取得などの制度を制定する。 |
|
| (五) |
各会社や団体が安全や衛生の自主管理システムを備えるよう積極的に運動する。自主管理システム優秀者に対する表彰や褒賞などの方法により、いっそうの徹底を図る。また各企業経営者による座談会の主催、大企業に対する自主管理の指導、請負会社に対する安全・衛生管理の指導などを通して、労働災害の防止に努めてゆく。 |
|
| (六) |
労働者の安全や衛生を促進する団体、グループの拡大と組織を援助する。また責任監督制度を導入し、各会社や団体の相互援助、安全管理の経験や技術の交換などが一層円滑になされるようにするとともに、全体的な知識と技術の向上に努める。 |
|
| (七) |
労働者自身が危険を認識するための運動を引き続き推進する。作業環境の測定制度、労働者の定期検診制度などの徹底化により労働者の健康管理を重視し職業性疾病の発生を予防する。 |
|
| (八) |
全国における危険な職業環境に関する資料を十分に把握し、インターネットによる情報の提供と交換のシステムを確立する。労働者の安全と衛生に関する科学技術や情報交換の効果的な方法に関する研究を促進する。 |
|
| (九) |
特殊な職種ごとの災害の予防と管理に関する研究を強化する。 |
|
|