国際安全衛生センタートップ >
国別情報(目次) >
チュニジア 平成16年度JICAセミナー カントリーレポート
|
平成16年度JICAセミナー カントリーレポート(チュニジア) 資料出所:平成16年度JICA労働安全衛生政策セミナー カントリーレポート(チュニジア) はじめに ここ数十年に渡り、チュニジアの産業は貴重な発展を遂げた。また、チュニジアは健康と環境の安全性も重要視しており、複数の部がこの分野に関連した業務を行っている。そのひとつが産業エネルギー省の安全部である。安全部は、産業の急速な発展と安全衛生の尊重という二者間のバランスの保持に尽力している。 1) 安全部 安全部は産業エネルギー省に属し、産業安全課と、エネルギー・鉱業安全課を統括している。 安全部の主な業務
2) 組織図 産業省の任務の固定に関する1995年5月22日のデクレ95-916号、および省組織に関する1995年5月22日のデクレ95-917号によれば、安全部は以下のように組織されている。 |
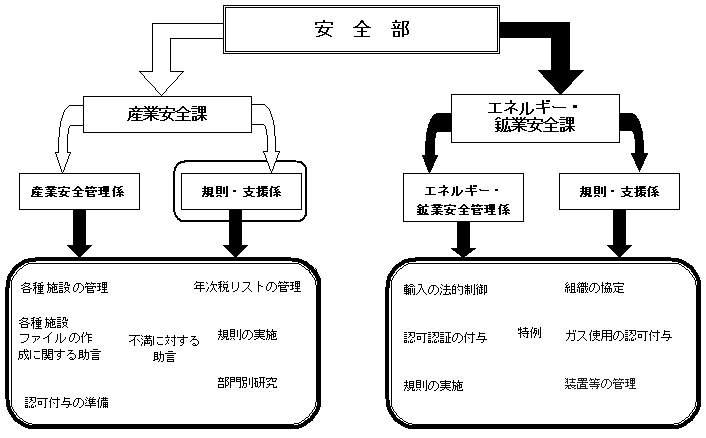
チュニジアにおける労働安全衛生 はじめに チュニジアの産業は一万社以上の企業によって構成されている。伝統的分野の他、エレクトロニクス、自動車の組み立て、化学などの産業が急速に発展している。チュニジアの主要な産業セクターとしては、繊維、皮革製品製造(靴など)、食品、機械、エレクトロニクス、化学が挙げられる。また、これら産業のGDPに占める割合は1999年の時点で33.3%であった。 チュニジアは産業構造の強化を目的とし、総合プログラムを開始した。この計画の下で、技術の熟達度を高め、質、安全性、環境の向上および労働力の強化を図る。 1) チュニジアにおける労働安全衛生活動の現状 (a) 労働安全衛生関連法令の一覧および概要 安全に関する限り法令は非常に重要であるため、19世紀初頭には事故を予防する目的のため国際的なレベルで数多くの法令が作成された。法令や規則は複数の国で急速に発展した。チュニジアにおける主な労働安全衛生関連規則の一覧は以下の通りである(完全ではない)。
安全部は、法律文を修正し、新たな法律文に関する意見が常に反映されるよう考慮する。 (b) 労働監督制度の概要 チュニジアにおける労働監督は、複数の組織間で分担され、共同で運営されている。以下のスキームを使用してこの分野の問題解決に当たっている。 (c) 労働災害補償保険スキームの概要 チュニジアにおける社会保障の運営は、公共部門を担当するCNRPSと、民間部門を担当するCNSSという2つの基金によって分担されている。社会問題・連帯省(Ministry of Social Affairs and Solidarity)は、運営の権限を持つ管理協議会を通じて、重要な選択に関する主なガイドラインを提供している。 チュニジア国家年金社会保障準備基金 (CNRPS) は、公的部門の労働者に対する社会保障の提供を担当する社会保障機関である。関係者は必ずCNRPSに加入しなければならない。CNRPSは退職年金、疾病保障、遺族年金、孤児に対する一時年金など、一般的な社会保障の分野を担当している。 CNRPSは、およそ50万人にのぼる加入者へのサービスを行っている。加入者の家族を考慮すると、およそ280万人がCNRPSの社会保障による恩恵を受けていることになる。公的社会補償基金(CNSS)は、CNRPSの対象外にある国民に対する社会保障を提供する制度である。 CNRPSによる社会保障は、性別、国籍に関係なく公的部門で就業する全ての労働者を対象としている。外国籍の契約労働者も、チュニジア国民と同じ便宜を受けることが出来る。 社会保障スキーム
a. CNRPSによる年金および遺族スキーム
遺族配偶者年金 遺族配偶者は、死亡した夫/妻の退職年金か、あるいは死亡した日に夫/妻が働いていたならば受け取ることが出来た金額の75%を受け取ることが出来る。親がかりの子供がいる場合には50%まで引き下げられることがある。 孤児に対する一時年金 この年金は、以下ような孤児に対して支払われる。
死亡給付金は、遺族からの請求に応えてCNRPSから死亡した加入者に対し給付される補償金である。 疾病補償スキーム CNRPSは、加入者の疾病に対し、疾病に関する補償の責任を取る、あるいは民間/公立病院でかかった医療費を払い戻すという形式で総合的な疾病補償を提供している。この疾病補償には、強制スキームと選択スキームの2種類のシステムがある。 チュニジア公的社会保障基金(CNSS)は、民間の性質を持ち、独立採算制を採る公共の機関である。この基金は理事長と中央運営部や労働組合、事業主および労働者組織の代表の12名の運営代表者によって構成されている。CNSSの組織は、中央組織と地方組織に分かれている。 CNSSは、民間部門で就労し、国民保険に出資している労働者を対象に、様々な社会保障スキームを展開している。2002年の時点で、1,439,647人の出資者を抱えており、その出資者らは以下のスキームにそって区分される。
また、CNSSは海外12か国との間で社会保障に関する二国間協定を結んでおり、この協定に基づいてサービスを提供している。 CNSSは公立大学に入学した学生に対しても社会保障サービスを行っている。社会保険の加入者とその家族は、スキームに基づき、以下に挙げる分野の社会サービスを受けることが出来る。
労働災害 他の国々と同じようにチュニジアも多数の労働災害に頭を悩ませてきたが、近年は、政府、労働環境の技術的管理、労働者、事業主、監督官の尽力によりその数が減少した。 また、民間/公共部門における労働災害補償に関する1994年2月21日の法律28号の施行、そして1996年の労働法典の改訂以降、事故による死傷者の数も減少傾向にある。 労働災害データは1995年分から取得可能である。ここでは1995年から3年間のデータを掲載する。
事故のコスト 労働災害は、社会、事業所、そして労働災害を被った本人にとって経済的に深刻である。労働災害の社会レベルでのコストも甚大だが、これらの災害は医療保険システムや保険会社の様々な違った分野で処理されているため、はっきりと数値で表すのは困難である。 個人レベルで考えると、労働災害によりいくつもの大きな困難が被害者に降りかかるのは火を見るより明らかである。そこで、多くの国々では、就業中に負傷した被害者に対し、伝統的に補償的な保険金が支払われてきた。 産業災害(大規模) 産業災害は大きな注目を集めており、また、心理的な重要度も高い。これらの産業災害は、社会にとって受け入れられない事柄や危険を代弁していると考えられる。 苦い経験を糧に、危険な産業活動に関する規則は変更、強化された。また、産業災害は危険をともなう活動に関する安全分析の必要性を際立たせ、安全分析にも組織的問題を織り込むことの重要性を示している。 残念ながらチュニジアでは産業災害に関するデータを入手することが難しい。そこで、筆者は、産業災害をまとめたデータベースが完成すれば、関連行政機関、事業主、労働者、ひいては社会全体にとって有用な情報を提供するが出来ると、データベース構築プロジェクトに取りかかった。 筆者はこのプロジェクトを、チュニスの科学研究所、特に筆者が学位取得科目として2つのプロジェクトを監督したコンピュータ学部と共同で進めた。コンピュータ学部の学生は、データベースの情報化に関する部分を担当してくれた。しかし、このプロジェクトは、数多くの問題を抱えていた。 経済的問題
(e) 労働安全衛生に関する研修/教育制度 専門教育や、工学系の学校における研修プログラムを除けば、労働安全衛生に関する教育プログラムは、教育基本制度上皆無である。しかし、学生に安全について知ってもらおうと、安全を教育基本制度の中に取り入れようとするプロジェクトがいくつかある。 2) 労働安全衛生に関する行政政策実行上の問題点及び個人的見解から見た対応策 法令の実施における問題 我々は以下のような問題を抱えている。
筆者の個人的な観点から見ると、工場の管理や関連規則の実施に従事している職員の知識を向上させるため、安全部がより一層の努力を行い、他の先達の経験から学ばなければならない5つの大きな分野がある。 1) 法律 産業安全に関連する法律や規則を更新しなければならない。実際、環境影響研究に関する1991年3月13日のデクレ91-362号以外は、1975年以前に発布されたものである。特に、各種事業所に関する法律文や、高圧施設に関する法律文の発布は、それぞれ1932年と1955年である。 チュニジアは経済を自由化し、徐々に国際経済に組み入れていこうというプログラムを実施している。このような選択の前で、産業は競争という問題に直面することになるであろう。今後発生が考えられる競争に備え、チュニジアの産業を準備させるには、管理組織を刷新し、近代的な規則や手続きのコンピュータ化など、決定を行うのに効果的なツールを提供することが必要である。 つまり、現在の産業や技術の進歩に対応した規則を実施していくには、法律文の作成が必要である。 2) リスク評価と危険研究 工場の内部および外部の安全度を評価する新しいコンセプトのひとつに、リスク評価アプローチがある。安全部はこのリスク評価研究を重要視しており、現在まだチュニジアでは義務化されていないリスク分析研究と緊急対策に必要な法的背景を確立するため、この分野における先達の経験を知りたいと考えている。 3) 工業地域 工業地域は急速に発展している。工場と人間の健康の安全性を保証するため、工業地域における発展は最も効果的な方法で行われなければならない。 この分野に関し、筆者は以下の目的達成に向けた努力が必要であると考えている。
都市部と工業地域の混在は世界的に見られる現象である。両者の混在は、工業地域の周辺で都市建設が拡大することによって発生する。この現象に対処するために当局は複数の対策を講じている。都市部と工業地域がお互いに悪影響を及ぼし合わないように、更なる対策を講じる必要がある。この分野における日本の経験は、我々が都市部と工業地域の混在に対応する適切な対応を行う上で大いに参考になると考えられる。 5) 産業災害と事故に関するデータベース 主な事故をどのように防止するか、またそのリスク、悪影響をどのように最小化するかについて更に追究するためにも、産業災害データベースの構築が肝要であると思われる。データベースが出来上がれば、以下の項目が可能になる。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||