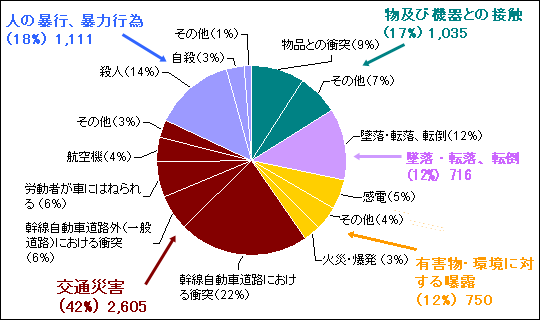|
労働災害(死傷)および業務上疾病の概要 資料出所:NIOSH発行「Worker Health Chartbook 2000年度版」 労働災害(死傷)および業務上疾病の責任 労働災害(死傷)は、事業場または作業中に発生したことが通常は明白であるため、業務に関係すると分類することが、疾病と比較して一般に容易である。しかし、疾病が業務に起因すると特定することは、疾病の進行がしばしば長期を要し、年齢、遺伝または喫煙や非職業性の騒音暴露といった業務外の要因の影響を受ける可能性があるため、それほど単純ではない。例えば、老齢で判明した癌は、何年も前に行った仕事と関連づけることが非常に困難な場合がある。すべての業務上疾病に由来する死亡を記述する単一のデータ・システムはないが、複数のデータ・システムが、あらゆる労働災害(死傷)を原因とする死亡を記述している。従って、労働災害(死傷)の責任は、業務上疾病の責任よりも明白である。
|
| 図1-9 1997年の死亡労働災害の数と事故の要因及び暴露の分布 これに追加して動作の反動、無理な動作を含む他の事故及び暴露に起因する21の死亡がある。(出典 : 1999年度 SOII ) |
致命的な疾病
最も死亡率の高い業務上疾病についての監視データは存在しない。データがない一つの理由として、大部分の業務上疾病は、事業場における暴露以外の要因によって発生しうることが挙げられる。喘息、結核(TB)、呼吸器癌、および慢性閉塞性肺疾患(COPD)のような肺疾患は、このような疾病の例である。ただし、肺疾患のごく一部を占めるじん肺は、完全に業務に起因すると決定することができる数少ない疾病の一つである。1968年以来、じん肺を根本的な、または潜在的な死亡原因とした死亡者数は114,000人を超える(図1-10)。死亡者数は、1972年の5,500人超を最高として、1996年には3,100人強となっている。石炭労働者じん肺(CPW)による死亡が、こうした数字の50%を超える原因となっている。じん肺のうち、石綿肺による死亡のみが増加を続けている。
 |
|
図1-10 15歳以上のアメリカ国民で、じん肺を根本的な、または潜在的な死亡原因として記録されたじん肺による死亡者数(1968年から1996年)(出典:NSSPM [1999年]) |
負傷災害および疾病1997年に民間部門事業者に関してSOIIが報告した610万の傷害および疾病のうち、570万(93%)が傷害である。疾病および傷害の総事例における傷害の割合は、SOIIによる業界区分によって異なる。製造業では、全事例数の87%が傷害で、建設業ではほぼ99%が傷害となっている(図1-11)。 1973年から1997年の間に、傷害および疾病の記録可能総事例は、常勤労働者100人当たりの災害発生率で11.0から7.1事例に減少した(図1-12)。最大の変化は、労働損失日以外の事例について生じており、1973年の7.5から1997年には3.8に減少している。労働損失日事例の場合、1997年における災害発生率(3.3)は、労働損失事例の総数が1973年の190万から1997年には290万に増加したにも関わらず、1973年の数値と類似している(3.4)。 |
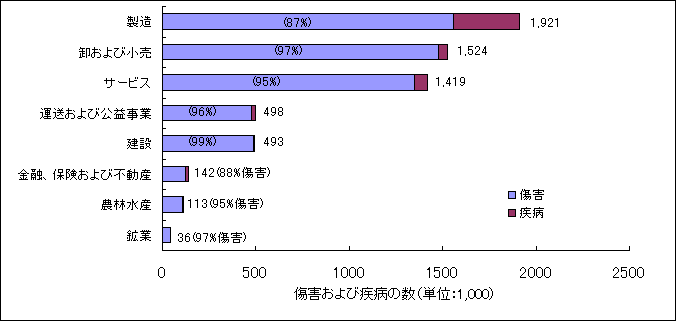 |
|
図1-11 民間部門における負傷労働災害および疾病事例、1997年。各業界部門に対する総数に占める%としての傷害をかっこの中に示す。(出典:1999年度SOII) |
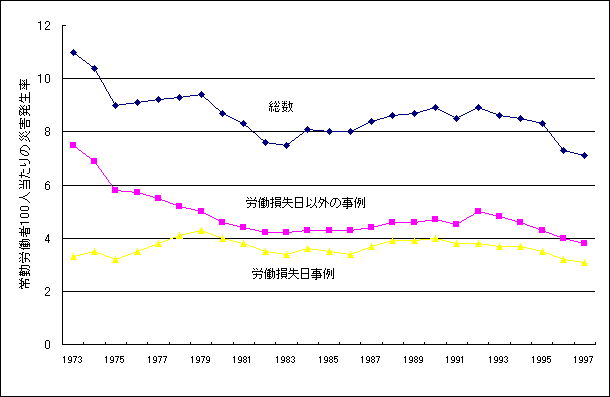
|
図1-12 民間部門における労働傷害および業務上疾病の事例に対する災害発生率、1973年〜1997年。(労働損失日以外の事例および労働損失日事例は、それぞれ事例全体の一部を構成する)(出典:1999年度SOII)
|
|
前述のように、労働損失日事例には、就業不能日事例と、就労制限事例(すなわち、労働者が制限された職務に配置される場合)の両方が含まれている。1988年から1997年の間に、就業不能日事例の割合の減少と、就労制限事例の割合の増加が見られた(図1-13)。 傷害および疾病事例が全体的に減少した理由の一つは、災害発生率の高い部門(製造)から災害発生率の低いその他の部門への労働時間の移行が挙げられる。製造業における労働時間は、1973年の総労働時間に対し35%から1997年には総労働時間に対し17%まで減少している。サービス産業の労働時間は、この間に18%から23%に増加している。図1-14では、1973年から1997年までの実際の傷害および疾病の災害発生率を、1973年の労働時間の業界分布に基づく災害発生率(すなわち修正後の発生率)と比較している。全年度を通じて、この率は、製造業における労働時間が1973年同様に高かった場合には、上昇するものと思われるが、経時的な減少はそれでも明らかであり、製造業からの移行は、傷害および疾病の災害発生率が減少した原因のすべてではないことを示唆している。労働損失日事例に対する災害発生率について実施した同様の分析の結果を図1-15に示す。ここでも、もし製造業の労働時間が1973年と同じである場合には、比率が増加するものと思われる。ただし、実際の率および修正後の率について、図1-15では、経時的な減少は明らかではない。 民間部門における負傷労働災害および疾病全体について、州ごとの1997年の災害発生率(あてはまらない州もある)は、常勤労働者100人当たりで最も低いニューヨーク州の4.4から、最も高いウィスコンシン州の10.0まで幅がある(図1-16)。全国平均では、常勤労働者100人当たり7.1件となっている。就業不能日を伴う負傷労働災害および疾病事例の比率は、常勤労働者100人当たりでジョージア州の1.4から、アラスカ州の3.5まで幅がある(図1-17)。労働損失日事例の全国平均は、常勤労働者100人当たり2.1である。負傷労働災害および疾病の就労制限事例は、ニューヨーク州の常勤労働者100人当たり0.3件から、メーン州の2.3件までとなっている(図1-18)。就労制限事例の全国平均は、常勤労働者100人当たり1.2である。 |
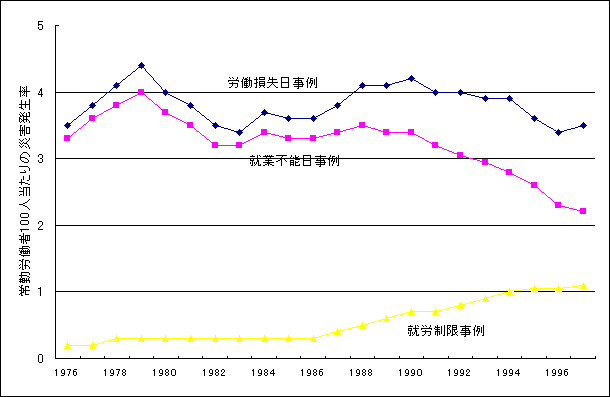 |
|
図1-13 民間部門における負傷労働災害および疾病に関連する労働損失日事例の災害発生率、1976年〜1997年。(就業不能日事例および就労制限事例は、それぞれ労働損失日事例全体の部分を構成する)(出典:1999年度SOII ) |
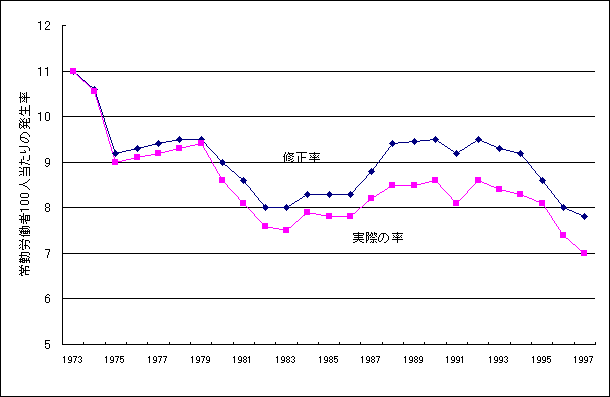 |
|
図1-14 民間部門における傷害および疾病の災害発生率:1973年の時間に対して修正した比率と比較した実際の率、1973年〜1997年。(出典:1999年度SOII) |
労働者と就業不能日を伴う傷害および疾病の特徴
|
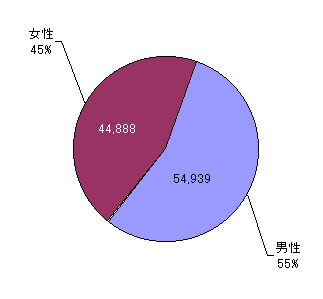 |
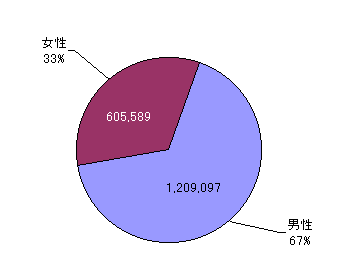 |
| 民間部門での雇用(千人) | 就業不能日を伴う負傷と疾病 |
|
図1-19 16歳以上の労働者の性別による民間部門での雇用、および、就業不能日を伴う負傷労働傷害および疾病事例の分布、1997年。労働者の性別が報告されていない事例は除外。就業不能日を伴う傷害および疾病に関する総事例は1,833,380であった。(出典:1999年度CPS、1999年度SOII) |
|
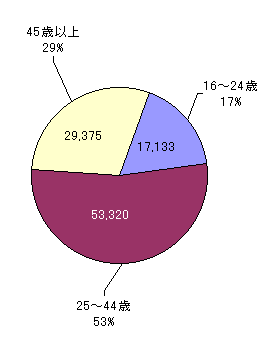 |
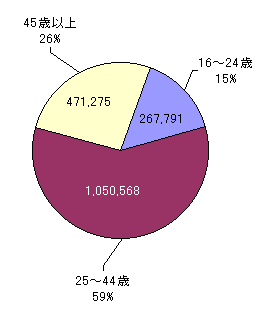 |
| 民間部門での雇用(千人) | 就業不能日を伴う負傷と疾病 |
|
図1-20 労働者の年齢による民間部門の雇用、および、就業不能日を伴う負傷労働傷害と疾病事例の分布、1997年。労働者の年齢が報告されていない事例は除外。就業不能日を伴う傷害および疾病に関する総事例は1,833,380であった。(出典:1999年度CPS、1999年度SOII)
|
|
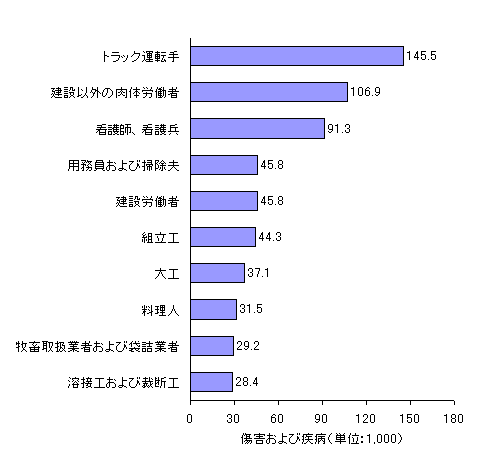
|
図1-21 就業不能日を伴う傷害および疾病が最も多く発生した10種類の職業、1997年。就業不能日を伴う傷害および疾病の総事例は1,833,380であった。(出典:1999年度SOII)
|
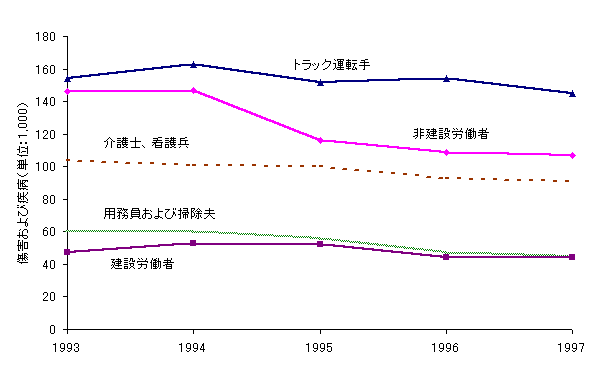 |
|
図1-22 選択された職業についての就業不能時間を伴う労働災害(死傷)および疾病数、1993年〜1997年。(出典:1999年度SOII)
|
傷害および疾病1997年における就業不能日を伴う負傷災害および疾病の31%は、新規労働者(すなわち、その事業者に雇用されて1年未満の勤続年数の労働者)の間で発生している。新規労働者のこの比率は、鉱業(44%)、農林水産業(43%)、建設(41%)および卸小売業(34%)でさらに高くなる(図1-23)。就業不能日を伴う傷害および疾病事例の2/3近くが、その事業者に対して勤続年数が5年以内の労働者の間で発生している。 捻挫および筋違えは、最も頻繁に発生する傷害の症状であり、就業不能日事例の799,012件(43.6%)を占めている。打撲傷は165,800件(9.0%)、切傷および刺傷はさらに156,700件(8.5%)を占める(図1-24)。労働災害によって最も影響を受ける身体の部分は腰である(図1-25)。肉体的反応および労作、物や機器との接触、それに墜落・転落、転倒が、就業不能日を伴う労働災害(死傷)および疾病につながる頻度のもっとも高い災害または暴露であった(図1-26)。 疾病または傷害の程度は、就業不能日数から推し量ることができる。あらゆる種類の傷害および疾病に対する就業不能日数の平均は5日である。手根管症候群(CTS)、骨折、切断、腱炎、複数の傷害、および捻挫・筋違えは、あらゆる傷害および疾病を合わせた5日の平均値よりも就業不能日数の平均値が長い(図1-27)。 |
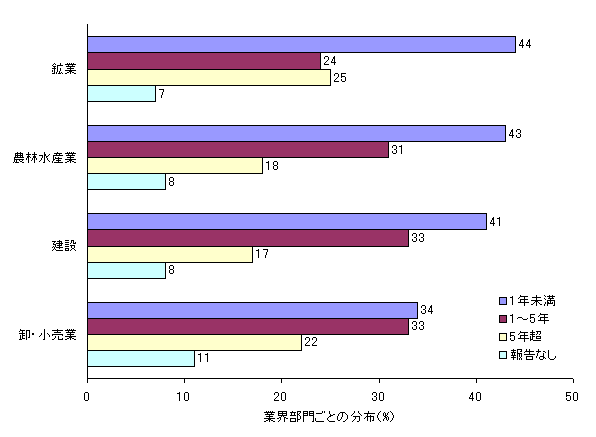 |
|
図1-23 事業者に対する勤続年数による、選択された民間業界部門における就業不能日を伴う負傷災害および疾病の分布、1997年。(出典:1999年度SOII)
|
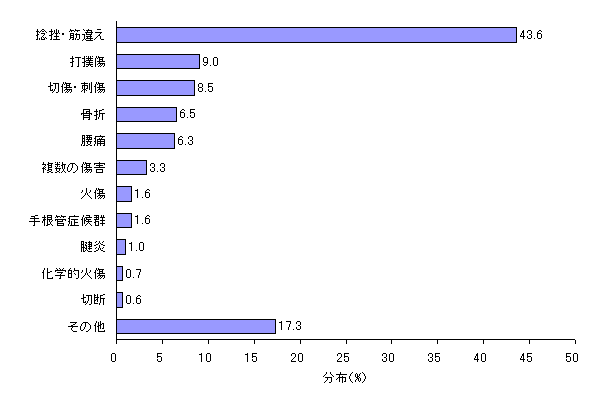 |
|
図1-24 民間部門における、就業不能日を伴う負傷災害および疾病の傷害または疾病の性質による分布、1997年。就業不能日を伴う傷害および疾病の総事例は1,833,380であった。(出典:1999年度SOII)
|
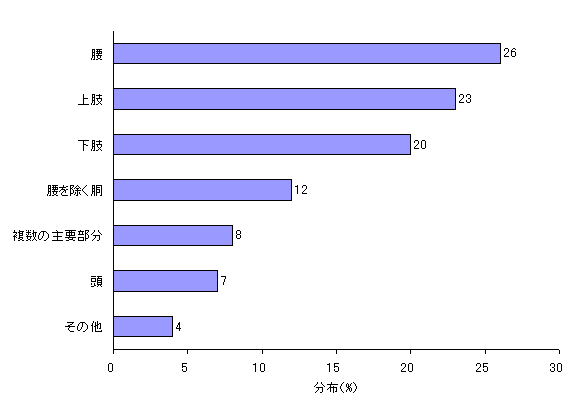 |
|
図1-25 民間部門における、就業不能日を伴う負傷災害および疾病の、影響を受けた身体の部分による分布、1997年。就業不能日を伴う傷害および疾病の総事例は1,833,380であった。(出典:1999年度SOII)
|
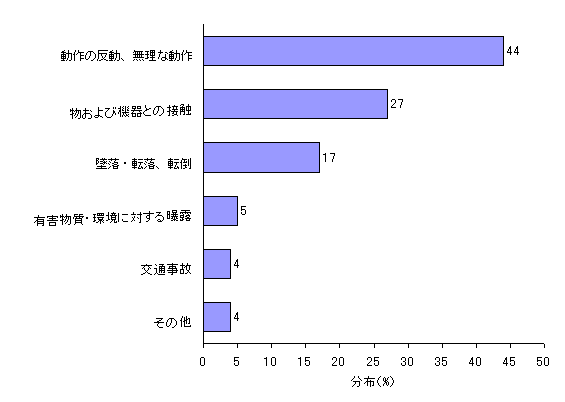 |
|
図1-26 民間部門における、就業不能日を伴う負傷労働災害および疾病の事故または暴露の種類による分布、1997年。就業不能日を伴う傷害および疾病の総事例は1,833,380件であった。(出典:SOII [1999年])
|
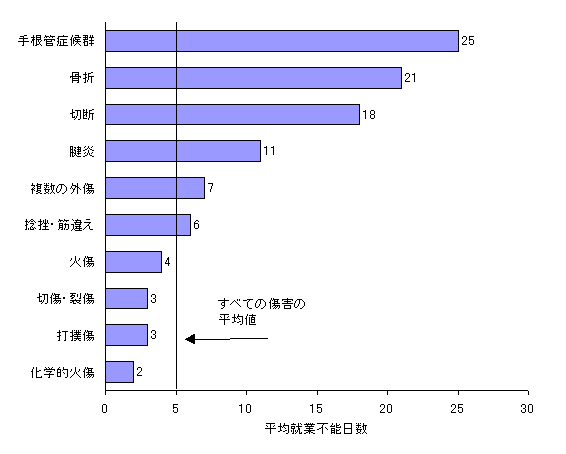 |
| 図1-27 民間部門における、負傷労働災害または疾病の選択項目による平均就業不能日数、1997年。(出典:SOII [1999年]) |