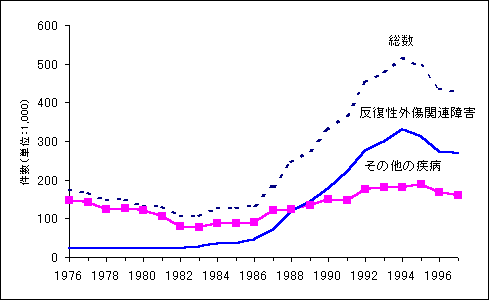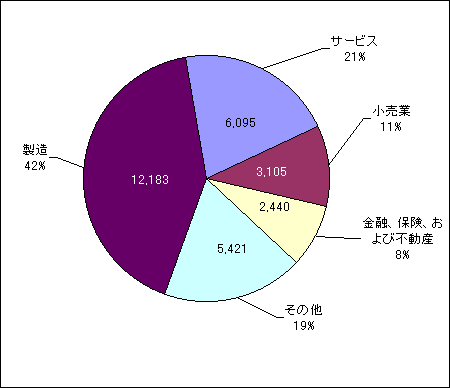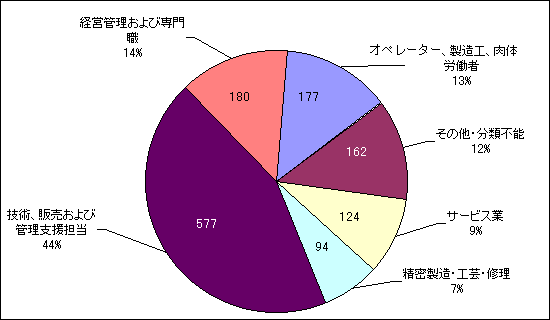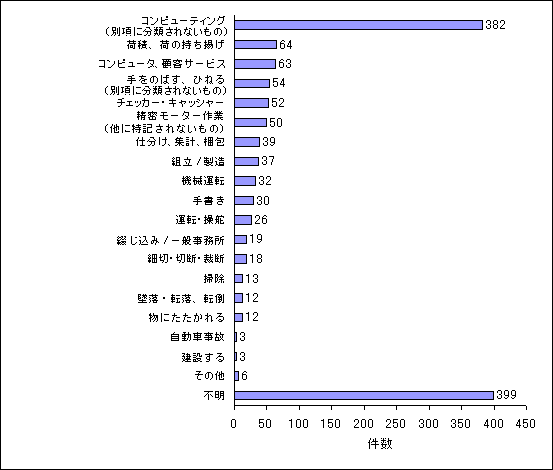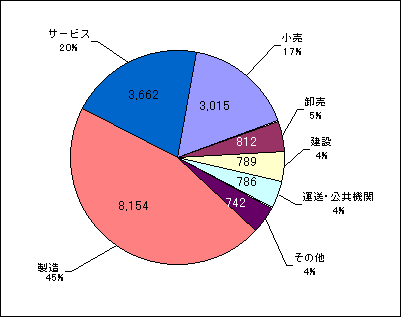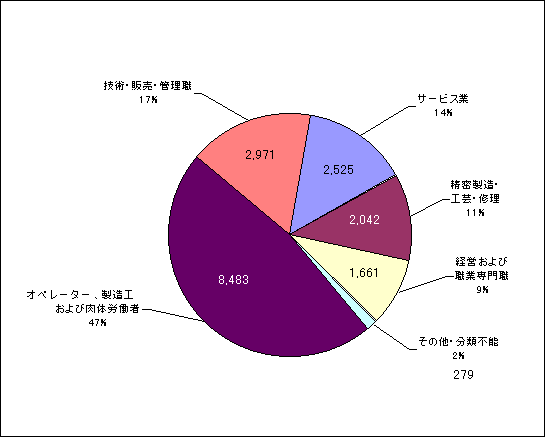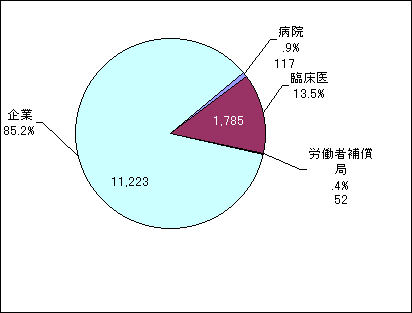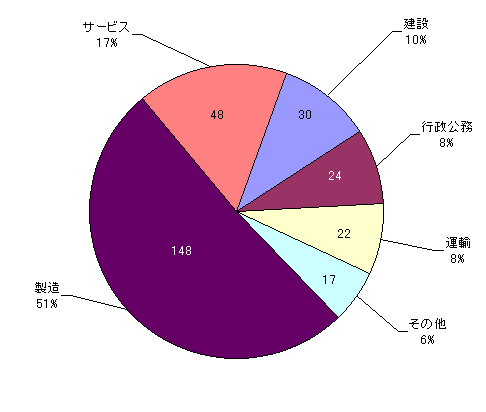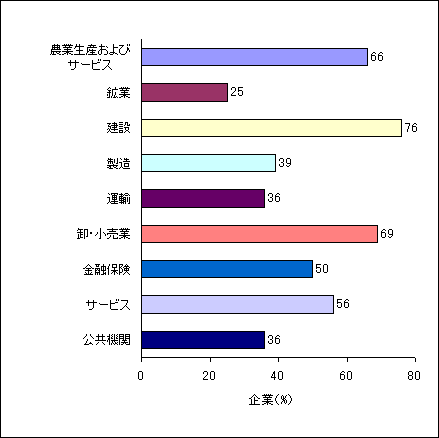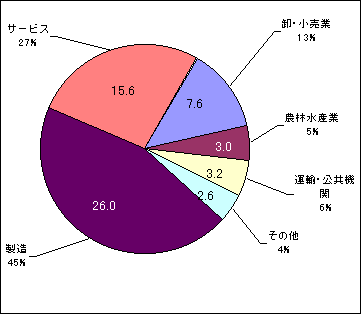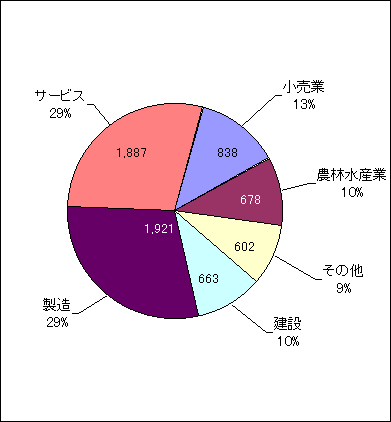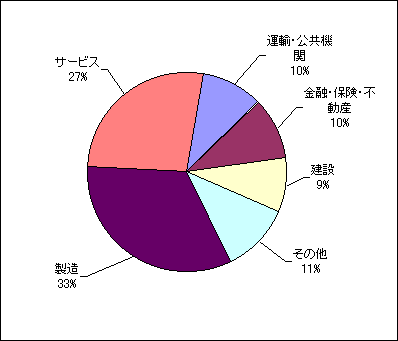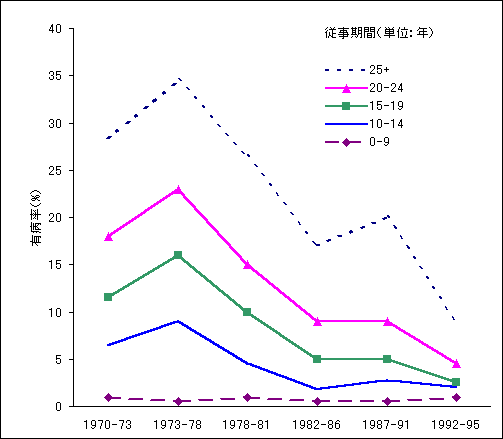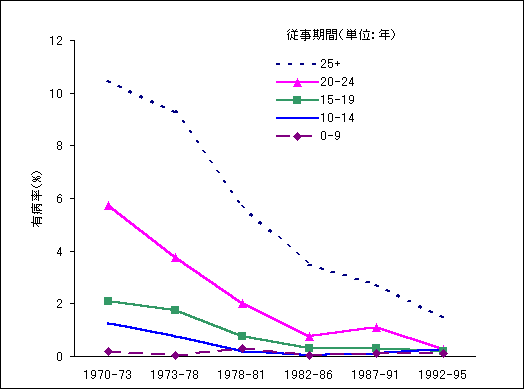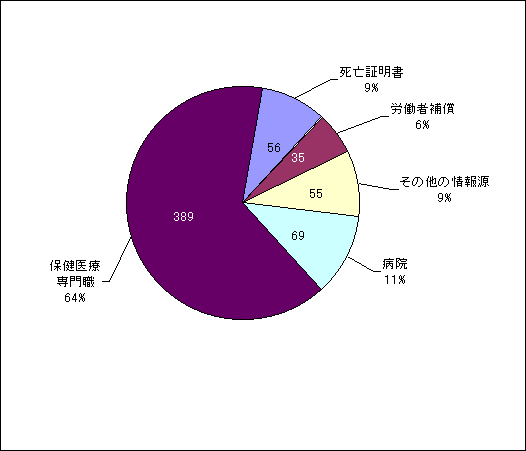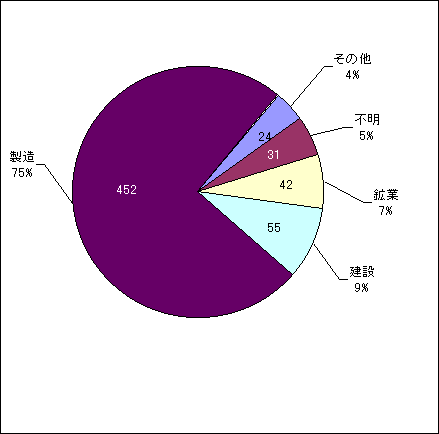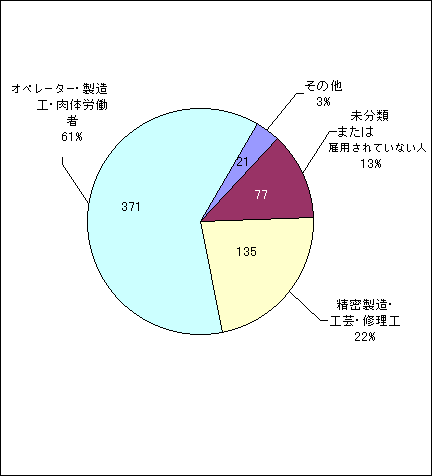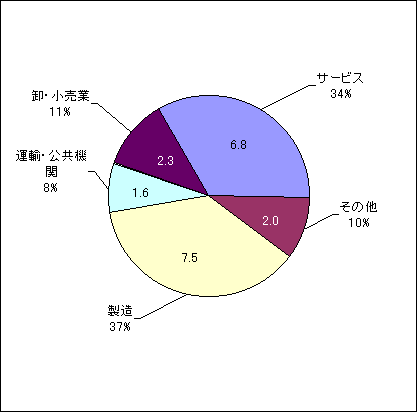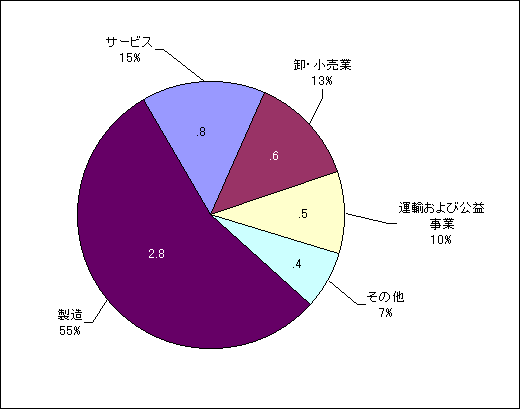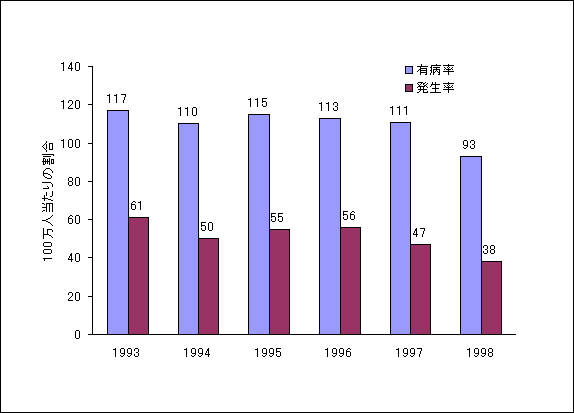致命的でない疾病資料出所:NIOSH発行「Worker Health Chartbook 2000年度版」 (訳 国際安全衛生センター) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 致命的ではない疾病疾病はしばしば傷害に比べて業務に関連づけることが困難である。職業性の暴露に関連づけられる疾病(例、結核[TB]、癌、中枢神経失調、喘息)は、職業性の暴露がない場合と差がないように見える。疾病における業務関連の側面は、一部の疾病における暴露と発症の間の潜伏期間が長いために、あるいは保健医療専門職が業務関連の疾病を認識または報告できなかったり、患者の職歴に関する情報を得ることができなかったりといった多くの理由のために見逃される場合がある。 労働統計局(The Bureau of Labor Statistics : BLS)は、事業者が保管する記録からのデータを使用して、労働災害(死傷)および業務上疾病に関する調査(SOII)で致命的ではない業務上疾病に関する情報を記録している。SOIIに報告される疾病は、最も容易かつ直接的に職場での業務に関連づけることができるものである。職場との関連が直ちに明らかであるとは言えない疾病は、SOIIではかなり実際より少なく数えられている。その他の疾病監視システムは、防止への取り組みを目指して疾病を記録および分類するために、異なったアプローチを採用している。ここで示すデータは、SOII、および職業性リスク監視・発生通知システム(SENSOR:Sentinel Event Notification System for Occupational Risk)、第3回国立衛生栄養試験調査(Third National Health and Nutrition Examination Survey:NHANES III)、石炭労働者X線監視プログラム(Coal Workers' X-Ray Surveilance Program(CWXSP)、成人血中鉛疫学監視プログラム(Adult Blood Lead Epidemiology and Surveillance Program)、米国病院保健医療労働者監視システム(Hospital Health Care Workers:NaSH)、ならびに、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)および後天性免疫不全症侯群(AIDS)、ウイルス性肝炎、および結核(TB)に関する各種の報告システムを含むその他のシステムによるものである。監視システムおよび情報に関する連絡先の詳細を付録Aに示す。 民間産業における業務上疾病の発生1997年に新たにSOIIが記録した、致命的ではない業務上疾病事例の総数は429,800であり、報告のあった疾病については1994年の500,000強を頂点として、3年連続で減少している(図5-1)。反復性外傷関連の障害は、1994年から1997年の間の減少幅のほとんどを占めている。1997年に報告されている致命的ではない業務上疾病の60%は製造業で発生している(図5-2)。同年の全体としての災害発生率は、常勤労働者10,000人当たり49.8人で、最も発生率が高いと報告があったのは、労働者数が1,000人以上の施設である(図5-3)。業界区分で最も高い発生率は、製造業に見られる(図5-4)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
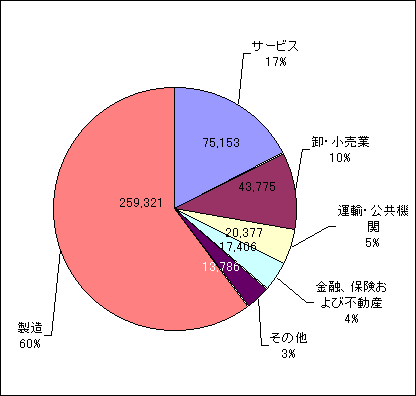
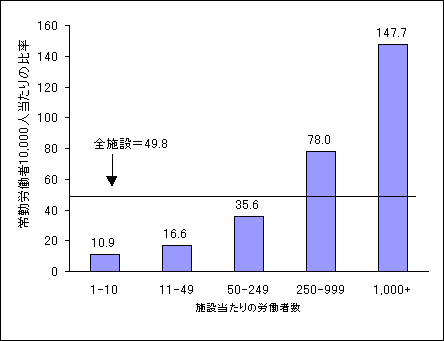
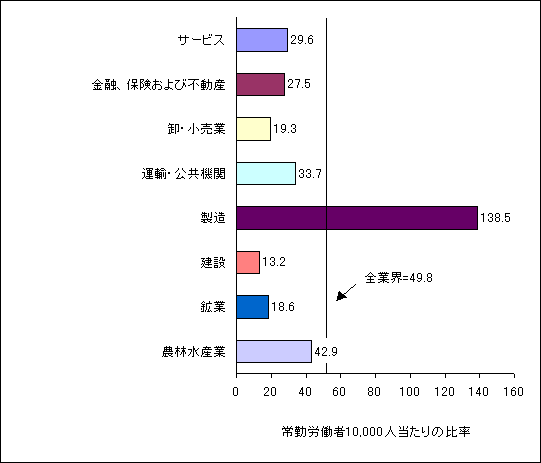
反復性外傷障害反復性外傷障害は、1997年にSOIIが記録した致命的ではない業務上疾病事例全体の64%(276,600事例)を占める。このカテゴリーに含まれるものとしては、手根管症候群(CTS)、腱炎、および騒音性難聴がある。反復性外傷障害は、1976年から1997年の間にSOIIが記録した致命的ではない業務上疾病の増加の大部分を占めている(図5-1)。1997年における民間産業における事例の72%は製造業が占める(図5-5)。反復性外傷が関わる致命的ではない業務上疾病の発生率が最高だった産業は、梱包工場(労働者10,000人当たり1,192人)、自動車および車体(労働者10,000人当たり741人)、および家禽屠殺加工業(労働者10,000人当たり523人)であった。 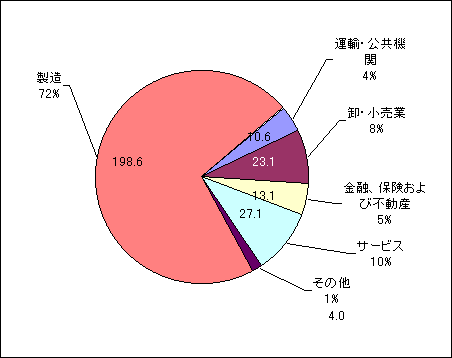
手根管症候群(CTS)SOIIが記録した事例CTSは、1997年にSOIIが記録した就業不能日を伴う致命的ではない業務上疾病で29,000事例を超える。このような事例の70%は女性が占め、CTS全体の半数を超える事例で25日以上の欠勤を伴っている。1997年には、CTS事例の大部分が製造(42%)およびサービス(21%)の各業界(図5-6)、そしてオペレーター、製造工および肉体労働者(39%)、技術者、販売員および管理支援担当者(30%)で発生している(図5-7)。CTSに関するSOII事例の大多数(98%)は、反復的な動作を必要とする作業に帰因するものである。
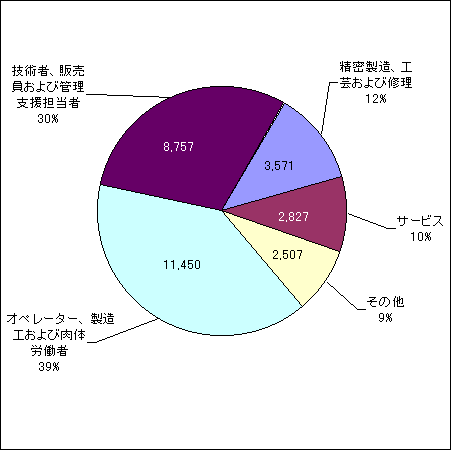
SENSORが識別した事例国立労働安全衛生研究所(NIOSH)の協力のもと、カリフォルニア州衛生省は、州労働者の補償システムを通じて償還を求める医師が登録する初期報告を使用して、CTSに関するSENSORプログラムを実施している。SENSORに関するCTSの事例定義には、(1)手、または手首の苦痛、火傷、または無感覚などの症状、(2)診療または電気診断試験による客観的な証拠、および(3)既知のリスク要因の一つを含む職歴が含まれている。1998年にカリフォルニア州SENSORプログラムが識別した約1,300のCTS事例のうち、最も事例が多かった業界は、サービス(30%)、製造(17%)、そして卸売(15%)であった(図5-8)。大部分の事例は、技術、販売および管理支援担当者(44%)および経営管理および職業専門職(14%)で発生している(図5-9)。傷害に関わる活動または暴露が発生した事例のうち、49%がコンピュータを使用していたと報告している(図5-10)。 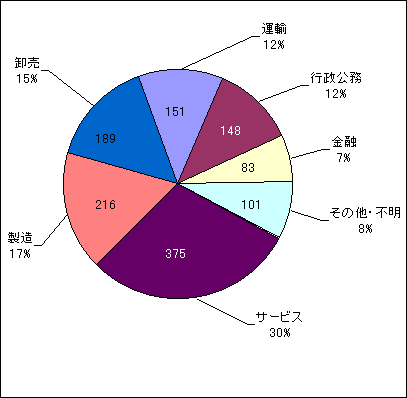
腱炎SOII は1997年、腱炎によりほぼ18,000事例が就業不能日数を要したと記録している。このような事例の60%強は女性であり、70%を超える事例で、該当する身体部分は上肢であった。大部分の事例は、製造業(45%)およびサービス(20%)の各業界(図5-11)の、オペレーター・製造工および肉体労働者(47%)、および技術・販売および管理職(17%)で発生している(図5-12)。労働者の動作または姿勢が、事例のうち事象あるいは暴露の73%を占めた。
騒音性難聴騒音性難聴から労働者を保護するためのSENSORプログラムは、1992年にミシガン州で開始された。このプログラムにおける職業性の騒音性難聴に関する事例の定義では、騒音性難聴に一致する聴力測定器による測定結果および聴力損失を発生させる上で充分な職業上の騒音に対する暴露経歴が必要となる。この事例定義には、(1)企業の聴力維持プログラムによって報告された標準的閾値移動を経験した労働者、および(2)医師により診断された永久的騒音性難聴が含まれる。1992年から1998年の間に、企業、聴覚学者、耳鼻咽喉科医、労働者補償局、および病院が、13,177の騒音性難聴を報告している。このような事例の85.2%を企業が占める(図5-13)。SENSORプログラムでは、医師により永久的騒音性難聴を受けたと認められた労働者に対する聞き取り調査を行っている。1998年における、このような事例の大部分は製造業関連であった(図5-14)。製造部門における事例の60%は、自動車製造を含む交通機関製造業と関係していた。 患者に対する聞き取り調査によれば、主要業界部門企業の25%から76%は、労働者が騒音に暴露した時点で聴力検査を行っていない(図5-15)。企業による報告のあった聴力損失患者(報告の85%強)は、保健医療専門職により報告のあった聴力損失患者より若年だという傾向がある(図5-16)。性別が示された事例のうち、89%が男性であった。
皮膚疾患または障害皮膚疾患または障害は、1997年にSOIIが報告した疾病の総事例のうち、13%(57,900)を占めた。このような障害には、アレルギー性および刺激性皮膚炎、皮膚癌などの条件が含まれる。1997年における民間部門の皮膚疾患または障害の45%は製造業で発生している(図5-17)。報告された災害発生率が最も高かったのは、魚の缶詰、燻製及び海産物産業である(労働者10,000人当たり181人)。職業性の皮膚疾患または障害が最高率であったその他の業界としては、食肉缶詰工場(労働者10,000人当たり104人)、ボール/ローラー・ベアリング製造(労働者10,000人当たり92人)、製革・仕上業(労働者10,000人当たり86人)がある。皮膚疾患および障害のサブカテゴリーである皮膚炎は、1997年におよそ6,600の就業不能時間を伴う事例に関係していた。3日間の就業不能日数の中央値は、皮膚炎に関係していた。化学物質および化学製品に対する暴露が、職業性の皮膚炎事例の53%を占める。就業不能日を伴う皮膚炎事例で最も多いのは、製造およびサービス産業部門(各29%)である(図5-18)。最も多く皮膚炎が発生した職種は、オペレーター、製造工および肉体労働者(36%)、および精密製造、技能・修理工(18%)である(図5-19)。
呼吸器障害粉じんによる肺の疾病1997年にSOIIが記録した致命的ではない業務上疾病のうち、粉じんによる肺の疾病が占めるのは1%未満(2,900)である。このような疾病には、珪肺、石綿肺、および石炭労働者じん肺(CWP)が含まれる。1997年に、業務上の粉じんによる肺の疾病の大部分は、製造業(33%)およびサービス業(27%)で発生している(図5-20)。最も肺の疾病の災害発生率が高かったのは、アルミニウムのシート、板およびフォイル製造(労働者10,000人当たり33人)、無煙炭採掘(労働者10,000人当たり30人)および造船・修理(労働者10,000人当たり12人)であった。
石炭労働者じん肺(CWP)CWPの有病率および強度は、石炭労働者X線監視プログラム(Coal Workers' X-ray Surveillance Program:CWXSP)で調査が行われた。CWPは、国際労働機構(ILO)の"Guidelines for the use of ILO International Classification of Radiographs of Pneumoconioses(「じん肺レントゲン国際分類使用に関するガイドライン」)"[ILO 1980年]を使用した肺異常(グレード1/0以上)(*)のX線による証拠を有するものとして定義されている。地下での勤務が25年以上にわたる労働者の間で、CWPカテゴリー1/0以上の有病率は、1970年〜1973年の28%強から1992〜1995年の10%未満まで減少している(図5-21)。同じ任期集団において、より重度のCWPカテゴリー2/1以上の有病率は、1970年〜1973年の10%強から1992〜1995年の2%未満まで減少している(図5-22)。有病率の減少はまた、地下採掘に従事した期間がより短い集団においても明白である(図5-21および5-22)。
珪肺珪肺は、珪酸粒子の吸入により生じる肺の慢性炎症状態である。この状態は、ほぼ例外なく職業性暴露により発生する。珪肺の有病率は、SENSORプログラムを通じて検査できる。SENSORの目的では、珪肺の事例は、空気中の珪酸粉じんの職業性暴露歴、および(1)珪肺に一致すると解釈される胸部放射線写真(またはその他の画像技術)、または(2)珪肺に特徴的な病理学的調査結果の片方または両方が要求される。 1993年から1995年の間、7州がSENSOR珪肺プログラムに参加した。7州全体で、604の珪肺事例が識別されており、これは主に病院(64%)、保健医療専門職(11%)、および死亡証明書(9%)からの報告によるものである(図5-23)。このような事例は主に、製造業(75%)、建設(9%)、および鉱業(7%)で発生している(図5-24)。オペレーター、製造工、および肉体労働者が、事例の過半数(61%)を占める(図5-25)。 聞き取り調査を行った珪肺患者の大部分が、暴露後10年以上経過してから症状が現れる慢性障害に罹患していた。大気中の高濃度の珪酸に対する暴露は、数年以内の発病の原因となり得る。また(きわめてまれな)急性珪肺は、強度の職業性暴露から数カ月以内の死亡のおそれがある。聞き取り調査の対象となった労働者の多くは、20年を超えて職業性の暴露を受けているが、8%の暴露経歴は10年未満であった。
毒性物質に帰因する呼吸器障害作業環境における毒性物質に帰因する呼吸器障害は、1997年にSOIIが記録した症例の5%(20,300)を占める。このような障害としては、アレルギー性および刺激性喘息、慢性気管支炎、および反応性気道機能不全(喘息のような症候群)が含まれる。1997年に最も多くの事例を報告した業界部門は製造(37%)およびサービス(34%)である(図5-26)。SOIIは、皮革製造・仕上業(労働者10,000人当たり77人)、オートバイ・自転車および部品(労動者1000人当り50人)、他に分類されない小火器を除く弾薬(労働者10,000人当たり36人)、造船・修理(労働者10,000人当たり36人)、および楽器製造(労働者10,000人当たり34人)で最も高い発生率が報告されている。
喘息および慢性閉塞性肺疾患 NHANES III 喘息および(慢性気管支炎や肺気腫のような)慢性閉塞性肺疾患(COPD)に関する労働者の有病率は、NHANES
III(図5-27および5-28)に記録されている。このような症状は、職場での暴露により発生または悪化する場合があるが、NHANES
IIIでは、特に職場の要因に帰するとはしていない。異なった産業労働者(特に非喫煙者)間の有病率変動は、場合により職業性の関連があることを示す場合もある。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図5-33 主要な産業分類別の民間部門での中毒件数(単位1,000)および分布、1997年。(出典:1999年度SOII) |
鉛中毒
ABLESは、成人(16歳以上)における血中鉛レベル(BLL)の上昇を監視している。1998年の段階で27州がこのプログラムに参加しており、地域の衛生部、民間の保健医療専門職、および民間・州の報告を行っている試験所からBLLデータを収集している(図5-34)(*)。同年、このうち25州の成人の中で合計10,501人のBLLが25μg/dL以上であったと報告されている。ただし、(任意の年度に報告されたすべての対象者に基づく)25μg/dL以上の有病率が、1993年から1998年の間の明白な傾向を示すものではなく、また(任意の年度に報告された新たな事例に基づく)災害発生率についても同様である(図5-35)。その一方、ABLESに参加する10州における50μg/dL以上のBLLについての有病率および発生率は、1993年から1998年にかけて減少している(図5-36)。
(*)訳注−−−図5-34は省略。
|
|
| 図5-35 BLLが25μg/dLを超える16歳から64歳の成人における有病率および発生率(出典:1999年度ABLES) |
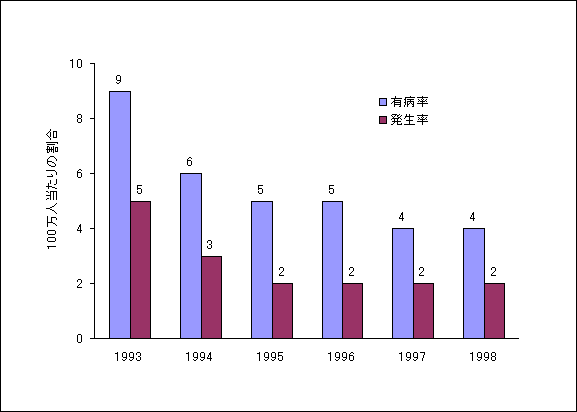 |
| 図5-36 10州(カリフォルニア、コネチカット、アイオワ、メリーランド、マサチューセッツ、ニュージャージー、ニューヨーク、オレゴン、テキサス、ユタ)でのBLLが50μg/dLを超える16歳から64歳の成人における有病率および発生率(出典:1999年度ABLES) |
農薬および殺虫剤中毒
数種類の監視システムが、農薬に関する急性の職業性疾病および傷害についての追跡を行っている。このうち2システムは全国を、残りのシステムは個別の州を対象としている。毒性暴露監視システム(The Toxic Exposure Surveillance System : TESS)は、アメリカ毒物管理センター協会(The American Association of Poison Control Centers : AAPCC)が管理している。1993年から1996年の間、アメリカ国民の約81%が加盟毒物管理センターの対象者となっていた。この間、職場で発生した6,300件を超える農薬中毒がTESSに記録されている。このような中毒の大部分は殺虫剤が関わるものであった(図5-37)。このような事例のうち、41%は有機リンが、29%はピレスリン/ピレスロイドが関わっていた。
SOIIは、労働損失日数に関わる農薬中毒についての情報を収集している。1992年から1996年の間、農薬に関係する致命的ではない職業性疾病および傷害の1年当たりの総数は、504件から914件までの幅があった(図5-38)。このような疾病の大部分は、殺虫剤に対する暴露が関係していた。SOIIの記録は、労働損失時間を伴うものに限られているため、他の監視システムで記録されているものよりも、より重度のものである可能性がある。
31州が農薬関連の疾病および傷害についての報告義務を定めているが、この条件に応じた監視を実施しているのは8州に過ぎない。カリフォルニア、フロリダ、ニューヨーク、オレゴンおよびテキサスでは、農薬に関する急性の職業性疾病および傷害についての監視活動は、環境保護庁(EPA)の部分的支援のもとに、SENSORプログラムの一環として行われている。事例報告を表にまとめるほかに、このようなシステムは事例確認を目的とする徹底的な調査の実施、患者の職場における他の労働者のスクリーニング実施、および目標を定めた現場介入を展開している。5年間(1992年〜1996年)のニューヨーク、オレゴンおよびテキサス各州における1年当たりの発生件数は、72件から170件に渡っている(図5-39)。多くの場合、殺虫剤に対する暴露が関係している。さらに、このうち33%は、農薬の混合、充填、および使用を含む農業上の暴露が関わっている。
農薬関連の疾病は、1971年以来、カリフォルニアで報告対象となる条件とされている。カリフォルニア農薬規制省(CDPR)は、このような報告の収集および評価に関する責任を負っている。事例の60%から75%が労働者の補償報告書により判別されている。残りの大部分は、医師による報告である。カリフォルニアにおける年間の農薬が関わる急性の職業性疾病および傷害は、656件から979件の幅があった(図5-40)。殺虫剤は、このような事例発生の最大の原因となっていた。殺虫剤のうち、殺虫剤の混合および有機リンが最も一般的な原因である(図5-41)。報告のあったうち半数を超えた(56%)事例が農業で発生している。サービスおよび公共機関は合わせて28%であった(図5-42)。
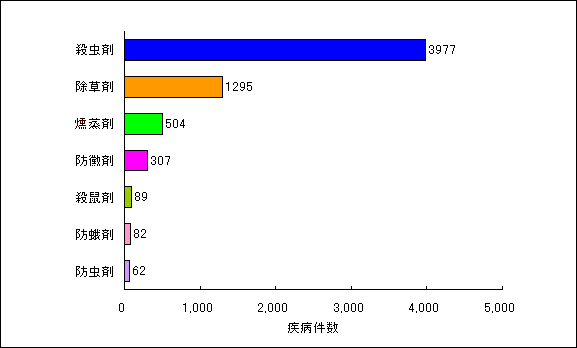 |
| 図5-37 (抗菌剤を除く)農薬カテゴリー別の、農薬に関する急性の職業性疾病の件数、1993年〜1996年(出典:1998年度TESS) |
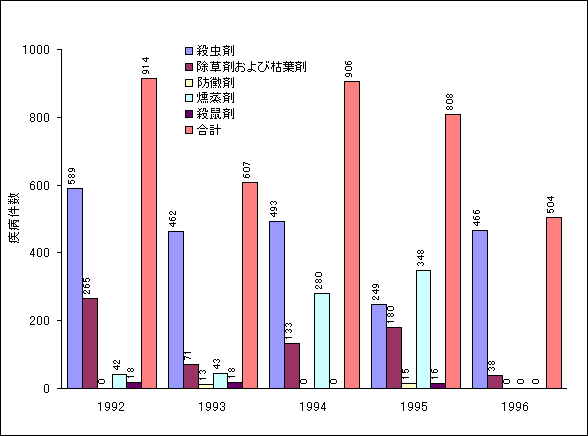 |
| 図5-38 農薬カテゴリー別の民間産業における就業不能日を伴う農薬関連職業性疾病の件数、1992年〜1996年(出典:1999年度SOII) |
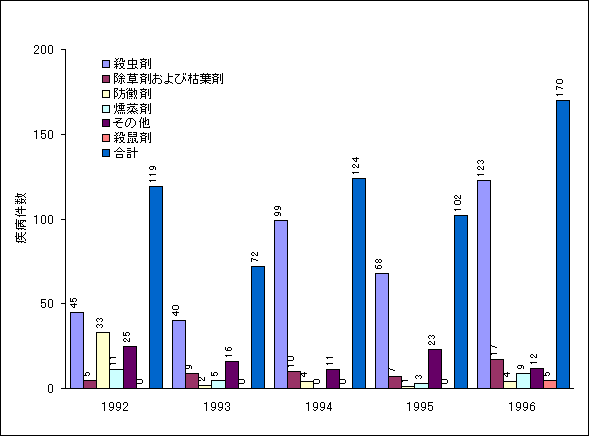 |
|
図5-39 農薬カテゴリー別のニューヨーク、オレゴン、およびテキサスにおける農薬関連職業性疾病の件数、1992年〜1996年(出典:SENSOR − ニューヨーク州保健省、1999年、オレゴン厚生部、1999年、PEST、1999年) |
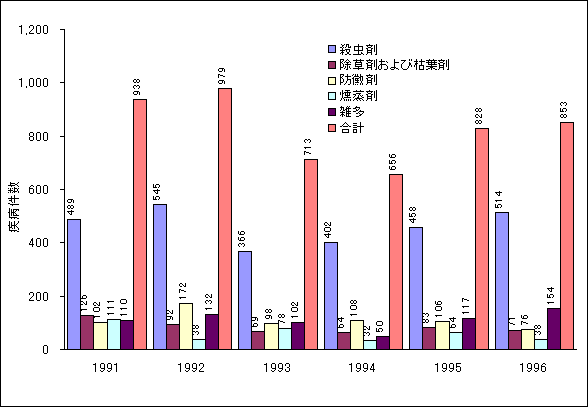 |
| 図5-40 (抗菌剤および不明の薬品を除く)農薬のカテゴリー別のカリフォルニアにおける農薬関連職業性疾病の件数、1991年〜1996年(出典:1999年度CDPR) |
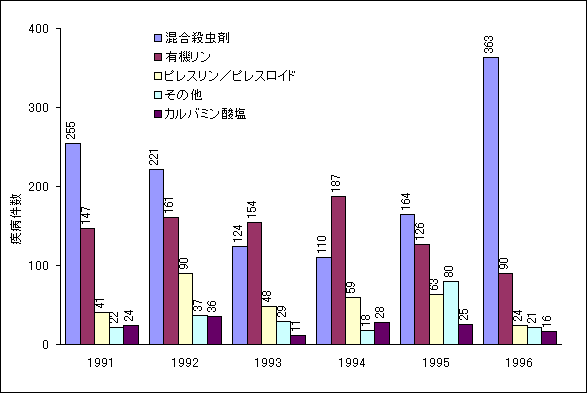 |
| 図5-41 殺虫剤カテゴリー別のカリフォルニアにおける殺虫剤関連職業性疾病の件数、1991年〜1996年(出典:1999年度CDPR) |
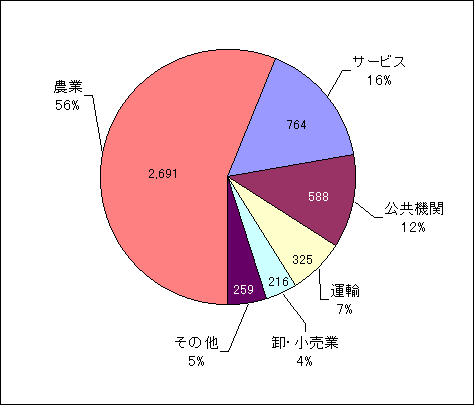 |
| 図5-42 カリフォルニアにおける、業界分類別の(抗菌剤および不明の薬品を除く)殺虫剤関連職業性疾病の件数および分類、1991年〜1996年(出典:1999年度CDPR) |
保健医療労働者の感染
米国の1,000万人の保健医療労働者は、労働者全体の約8%に当たる。保健医療労働者は、反復性の外傷、毒素、および各種の感染性物質を含む様々な職業性の危険有害要因に暴露する可能性がある。このような労働者の感染に関する監視データは、4種類の連邦衛生データベースに含まれている。
-
NaSHは、結核(TB)、ワクチンにより防止可能な疾病、および血液性の病原体を含む、数種類の原因物質に対する暴露および感染について追跡調査している。
-
ウイルス性肝炎監視プログラム(The Viral Hepatitis Surveillance Program : VHSP)および急性ウイルス性肝炎監視郡調査(The Sentinel Counties Study of Acute Viral Hepatitis)は、肝炎感染を追跡調査している。
-
保健医療労働者のAIDSおよびHIV感染の事例は、CDCが管理するHIV/AIDS報告システム(HARS)などの複数の情報源により確認されている。
-
staffTRAK-TBは、厚生省TB管理プログラムによって、その医院および関連機関における労働者の皮膚試験(*)を監視するために用いられている。
(*) 訳注−−−ツベルクリン反応のことと思われる
1995年6月から1999年10月の間に、60の参加NaSH病院が、血液または体液に対する暴露の事例6,983件を報告している。この多くは、看護師(43%)および医師(29%)で発生している(図5-43)。血液または体液に対する暴露件数は、患者(30%)および手術室・処置室環境(29%)において最も多い(図5-44)。暴露の主要な経路は、経皮(刺傷/切傷)である(図5-45)。
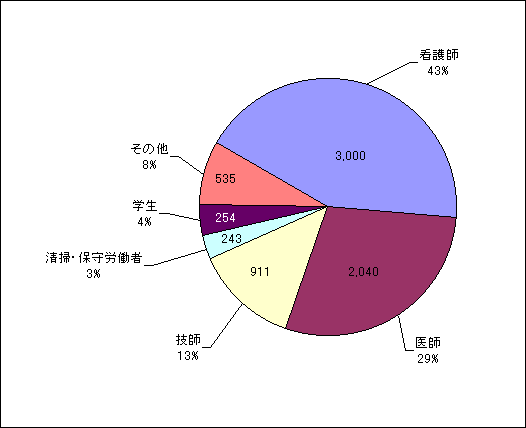 |
|
図5-43 60の参加病院において報告のあった血液または体液に対する保健医療労働者の職業集団別の暴露の件数および分布、1995年6月〜1999年10月(出典:1999年度NaSH) |
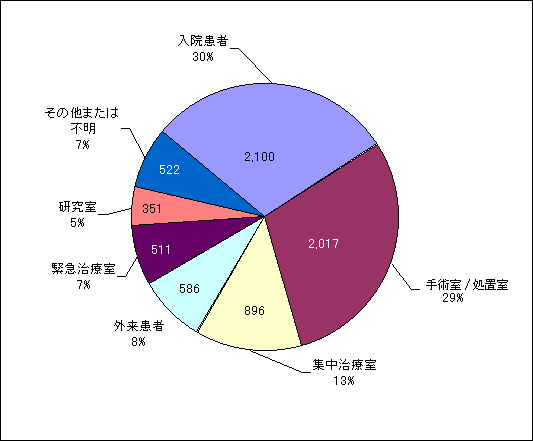 |
|
図5-44 60の参加病院において報告のあった血液または体液に対する保健医療労働者の作業場所別の暴露の件数および分布、1995年6月〜1999年10月(出典:1999年度NaSH) |
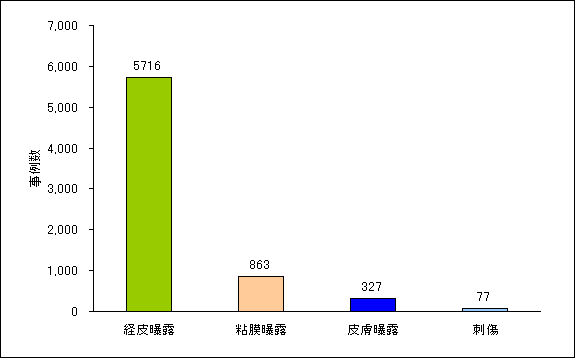 |
| 図5-45 暴露種類別の60の参加病院において報告のあった血液または体液に対する保健医療労働者の暴露の件数および分布、1995年6月〜1999年10月(出典:1999年度NaSH) |
血液暴露の結果
B型肝炎ウイルス
10年間にわたるVHSPおよび急性ウイルス性肝炎監視郡調査は、保健医療労働者のB型肝炎感染が、1985年の12,000件から1995年の800件まで、93%減少したことを示している(図5-46)。また、感染はこの時期に一般市民の間でも減少しているが、これほど劇的ではない。保健医療労働者間の感染がこれだけ減少したのは、体液に対する暴露の全体的な予防措置の採用とB型肝炎に対するワクチンによる可能性がある。
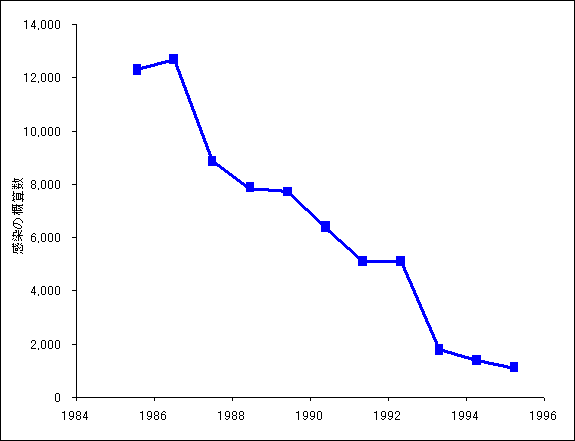 |
| 図5-46 米国保健医療労働者のB型肝炎感染の概算件数、1985年〜1995年(出典:1999年度VHSP、1999年度NCID) |
C型肝炎ウイルス
C型肝炎ウイルス感染は、アメリカにおいて最も多く見られる慢性血液感染である。保健医療労働者のC型感染ウイルスの有病率は、一般市民のそれ(1%〜2%)に近いが、保健医療労働者は注射針を誤って刺してできた刺傷による職業性の危険が高い。職業性のC型肝炎感染を受けた保健医療労働者の数は不明である。ただし、アメリカにおける急性感染の約2〜4%は、職場で血液に対し暴露した保健医療労働者の間で発生している。C型肝炎に暴露した労働者の大部分は医師または看護師である(図5-47)。
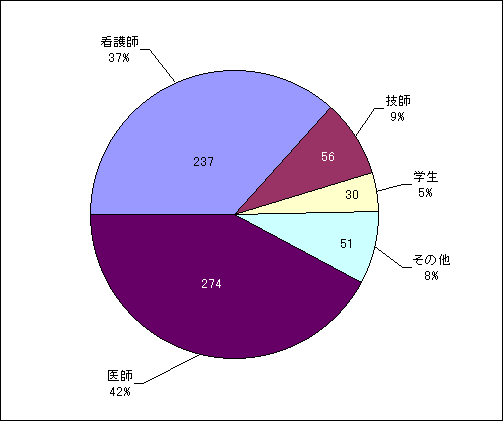 |
| 図5-47 C型肝炎に暴露した保健医療労働者の職業集団別の暴露の件数および分布、1995年6月〜1999年10月(出典:1999年度NaSH) |
ヒト免疫不全症ウイルス(Human Immunodeficiency Virus : HIV)
1999年6月までに、記録された55件および可能性のある職業性のHIV感染136件がHARSに記録されている。職業性の暴露に続くHIV血清変換の記録された事例のうち、85%は経皮暴露、93%は血液または視覚的に血液状の液体に対する暴露が関わっている。職業上のHIV感染の記録に残された事例の大部分は、看護師(42%)および研究室労働者(35%)の間で発生している(図5-48)。
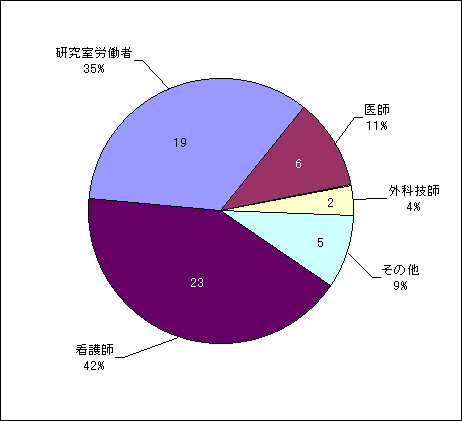 |
| 図5-48 1999年までに記録された保健医療労働者のHIV職業性感染事例の職業別件数および分布(出典:1999年度CDC-HARS) |
結核(TB)
保健医療労働者は、長年にわたりTBと接触する危険にさらされてきた。この危険は、米国におけるTBの再発と、これに続くAIDS流行の間の薬物抵抗性TBバクテリアの増勢に伴って1980年代に増加した。1994年から1998年の間、50の州、コロンビア特別区、およびプエルトリコから、staffTRAK-TB経由で、米国疾病対策予防センター(CDC)に保健医療労働者に対するTBが2,732件報告されている。1994年から1998年の各年における保健医療労働者における災害発生率を図5-49に示す。このような率は、情報が入手できないため、特に職業性の暴露に関係づけられてはいない。保健医療労働者の事例は、TB発生件数全体の3%に当たる。
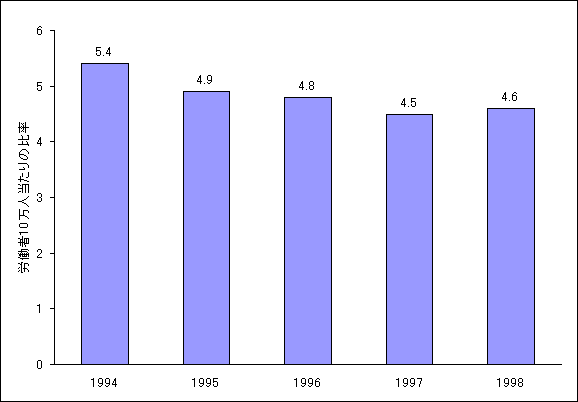 |
| 図5-49 保健医療労働者におけるTBの災害発生率、1994年〜1998年(出典:1999年度staffTRAK-TB) |
物理的因子
物理的因子による障害は、1997年にSOIIが記録した致命的ではない業務上疾病事例全体の4%(16,600)を占める。物理的因子が原因である障害には、熱射病、日射病、暑気当たり、およびその他の環境熱、凍傷、電離放射線(アイソトープ、X線、ラジウム)、および非電離放射線(溶接光、紫外線、マイクロ波、および日焼け)などが含まれる。毒物暴露による疾病は除外している。業界別では、製造業が1997年における民間産業での物理的因子による障害の55%を占めている(図5-50)。個別の産業については、最も発症率が高かったのは、金属衛生器具(労働者10,000人当たり294件)、一次アルミニウム(労働者10,000人当たり89件)、造船および修理(労働者10,000人当たり79件)、および(電気工を除く)配管および暖房(労働者10,000人当たり73件)である。
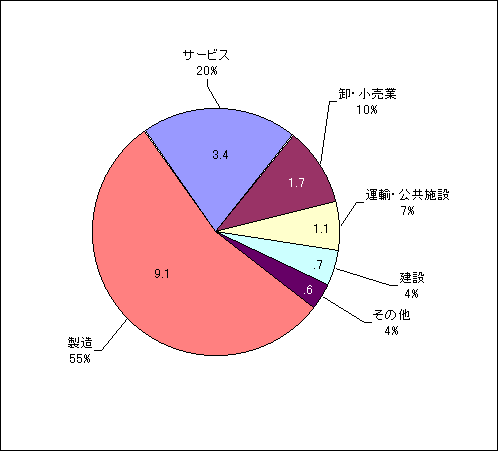 |
| 図5-50 民間産業における物理的因子による主要業界別の障害の件数(単位:1,000)および分布、1997年(出典:1999年度SOII) |
不安、ストレスおよび神経障害
1997年にSOIIが記録した就業不能時間を伴う不安、ストレス、または神経障害は約5,300件である。これは、報告されている致命的ではない業務上疾病発生件数全体の1%に当たる。就業不能時間を伴う不安、ストレス、または神経障害の事例では、女性が全体の60%を超える。このような障害発症例の半数は、23日以上の就業不能日数を要し、このような失調を患ったうち40%を超える労働者が、31日を超える就業不能日数を要した。大部分の事例を占める業界部門は、サービス(35%)、卸・小売業(20%)、および製造業(20%)である(図5-51)。この種の障害を最も頻繁に経験する職業集団は、技術・販売・管理職(47%)、およびオペレーター・製造職・肉体労働者(18%)である(図5-52)。不安、ストレス、または神経障害に最も関係の深い暴露は、有害物質(30%)および暴行または暴力的行為(13%)である(図5-53)。
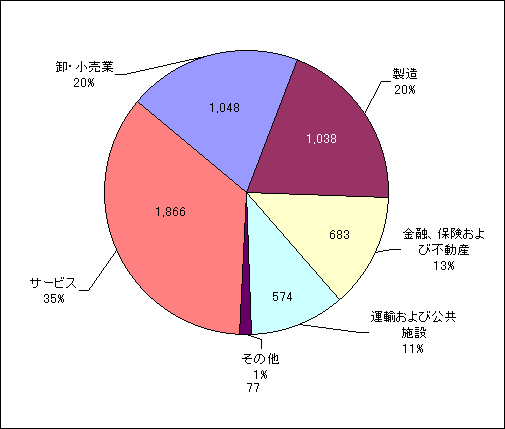 |
| 図5-51 民間産業における、業界部門別の就業不能日を伴う不安、ストレス、または神経障害事例および分布、1997年(出典:1999年度SOII) |
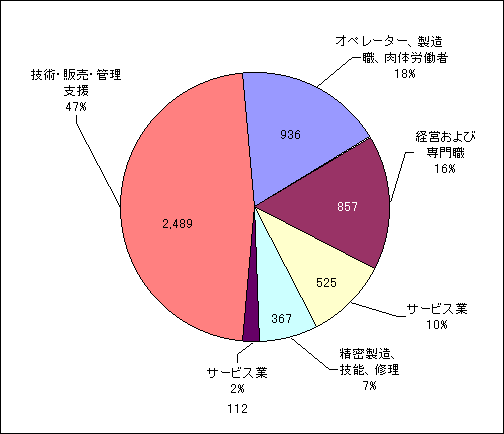 |
| 図5-52 民間産業における、職業集団別の就業不能日を伴う不安、ストレス、または神経障害事例および分布、1997年(出典:1999年度SOII) |
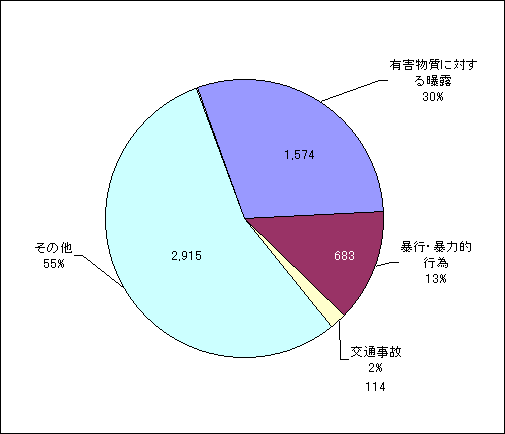 |
| 図5-53 民間産業における、災害または暴露別の就業不能日を伴う不安、ストレス、または神経障害事例および分布、1997年(出典:1999年度SOII) |
その他の致命的ではない業務上疾病
その他の致命的ではない業務上疾病は、1997年にSOIIが記録した病例全体の12%(50,400件)を占める。このカテゴリーは、炭疸、ブルセラ病、B/C型肝炎、HIV症、悪性および良性腫瘍、食中毒、ヒストプラズマ症、およびコクシジオイデス症のような疾病を対象としている。1997年におけるこのような発症例が最も多く見られたのは、サービス業(41%)および製造業(29%)である(図5-54)。最も高い災害発生率が報告されているのは、荷物取扱い(労働者10,000人当たり163件)、非鉄金属の二次精錬・精製(労働者10,000人当たり120件)、プレハブ金属建物(労働者10,000人当たり66件)、および鉄・鋼鉄鍛造(労働者10,000人当たり61件)であった。
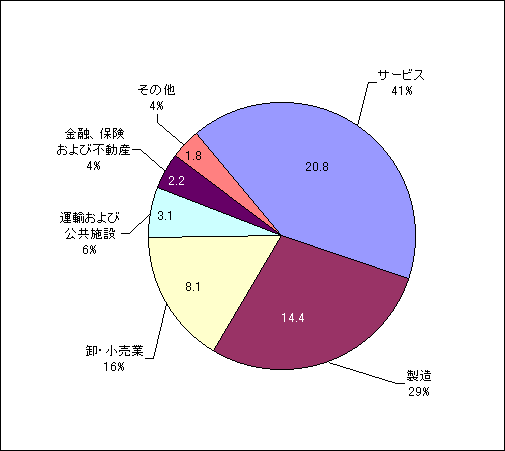 |
| 図5-54 民間産業における主要業界部門別のその他の職業性疾病事例および分布、1997年(出典:1999年度SOII) |