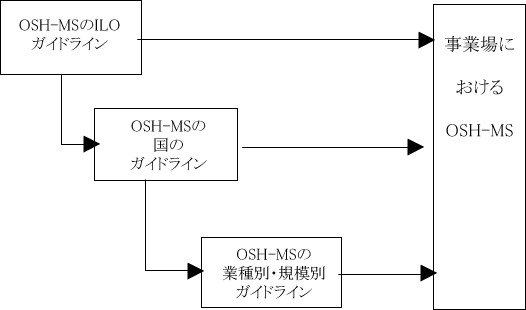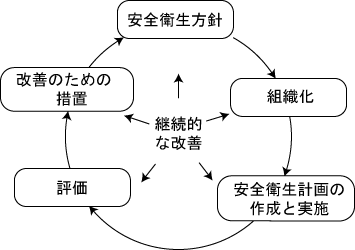|
労働安全衛生マネジメントシステムに係る
ILOガイドラインの要約
資料出所:厚生労働省安全衛生部国際室
ガイドラインは、前文、第1章「目的」、第2章「国のOSHMSの枠組み」、第3章「事業場のOSHMS」及び「用語集」等の参考資料で構成されている。
これらの概要は、以下のとおりである。
前文
事業場レベルでの危険有害要因及びリスクの低減並びに生産性向上に係るOSHMSの導入の積極的な意義は、現在、政府、使用者及び労働者に認識されている。
このOSHMSについてのガイドラインは、ILOの3者構成の各構成員により国際的に合意され、明確にされた原理を踏まえ、ILOにより策定された。この3者構成による対応は、強靱さ、弾力性及び事業場における継続可能な安全文化の育成のための適切な基礎を与えるものである。このように、ILOは、OSHMSについての自主的なガイドラインを策定したが、これは、ILOの存在意義と労働者の安全と健康を確保するにふさわしい手段を提示するものである。
このガイドラインは、労働安全衛生管理に責任を有するすべての者が使用することを意図したものである。また、このガイドラインは、法的な拘束力を持つものではなく、国の法令や基準に置き換わることを意図されたものでもない。さらに、その適用において、認証を求めるものでもない。
使用者は、労働安全衛生について組織的に対応することの責任を負い、また、義務を負う。OSHMSを実施することは、この義務を全うするための一つの有力な手段である。
ILOは、このガイドラインを実際的な手法として設計したが、これは、OSH対策の継続的な改善の達成の手段を提示することで、事業場や権限ある機関を支援しようとするものである。
1 目的
1.1 危険有害要因及びリスクからの労働者の保護や労働災害の根絶等に寄与すること。
1.2 国レベルでの本ガイドラインの目的
- 国のOSHMSの枠組みの確立に使用されること。
- 自主的な仕組みの開発のための手引き(guidance)を提供すること。
- 国のガイドライン及び業種別・規模別ガイドラインの開発のための手引きを提供すること。
1.3 事業場レベルでの本ガイドラインの目的
- 事業場のOSHMSの各要素についての手引きを提供すること。
- 事業場の関係者にOSH管理の原則及び方法を適用することの動機付けを与えること。
2 国のOSHMSの枠組み
2.1 国の方針[national policy]
- 権限有る機関(Competent institution or institutions)が指名され、当該機関が事業場におけるOSHMSの構築及び実施に当たっての一貫した方針の策定、実施及び定
期的な見直しを行うこと。また、この際、次の者の意見を聴くものとすること。
- 最も代表的な労働組合
- 最も代表的な事業者団体
- その他の関係団体等 (2.1.1)
- OSHMSについての国としての方針は、一般原則と手続きを定めたものである
こと。(2.1.2)
- 事業場のすべての管理の一環としてOSHMSの実施及び統合を促進すること。(2.1.2.a)
- 国及び事業場レベルでのOSH活動の体系的な統合、計画、実施及び改善のたの自主的な仕組みを推進し、及び改善すること。(2.1.2.b)
- 事業場レベルでの労働者及びその代表の参加を促進すること。(2.1.2.c)
- 不必要な官僚主義、管理及び費用を避けながら継続的な改善を実施すること。(2.1.2.d)
- 労働監督機関、労働安全衛生サービス機関、その他のサービス機関による、事業場に対するOSHMSの協力支援の仕組みを促進するとともに、これらの活動を労働安全衛生マネジメントの一貫した枠組みの中に組み入れるようにすること。(2.1.2.e)
- 適当な間隔で国の方針及び枠組みの効果を評価すること。(2.1.2.f)
- 適当な方法により、OSHMS及びその実施の効果を評価し、公表すること。(2.1.2.g)
- 事業場に直接雇用されている労働者(臨時の労働者を含む。)に適用される安全衛生の要求事項と同様のものが請負事業者及びその労働者に適用されることを確保すること。(2.1.2.h)
- 権限ある機関は、次の目的のためのOSHMSについての国としての枠組みを確立
すること。(2.1.3)
- 様々な機関の各機能や責任を決定するとともに、各機関の間の必要な協力 を確保するための仕組みづくりを行うこと。 (2.1.3.a)
- 国のガイドラインを公表し、定期的に見直しを行うこと。 (2.1.3.b)
- 業種別・規模別OSHMSガイドラインの準備及び実施に責任の有る機関の指定及びそれぞれの責任内容についての基準を定めること。(2.1.3.c)
- 手引きが事業者、労働者及びそれらの代表に利用できることを確保すること。 (2.1.3.d)
- 権限ある機関は、事業場がOSHMSを実施することを奨励し、支援するため、仕
組みを定め、労働監督機関、労働安全衛生サービス機関等に手引きを提供すること。 (2.1.4)
2.2 国のガイドライン[national guidelines]
- 国の実情や慣習を考慮し、モデル(第3章)に基づき精査されること。(2.2.1)
- ILOのガイドライン、国のガイドライン及び業種別・規模別OSHMSガイドラ
インの間で整合性が確保されるべきであり、事業場レベルで直接ILOのガイドラインを適用すること又は業種別・規模別OSHMSガイドラインを適用することが選択できるように弾力的に設計されること。
(2.2.2)
2.3 業種別・規模別ガイドライン[tailored guidelines]
- 業種別・規模別OSHMSガイドラインは、ILOガイドラインの全般的な目的を反映しながら、国のガイドラインの一般的な要素を含むべきであり、特に、次の事項を考慮しながら、事業場や事業場集団の特殊な実情や必要性を反映するようにして設計されるべきであること。
(2.3.1)
- その規模(大規模、中規模及び小規模)及び構造(2.3.1.a)
- 危険有害要因の型及びリスクの程度(2.3.1.b)
- OSHMSの枠組みについて図示したこと 。(2.3.2)
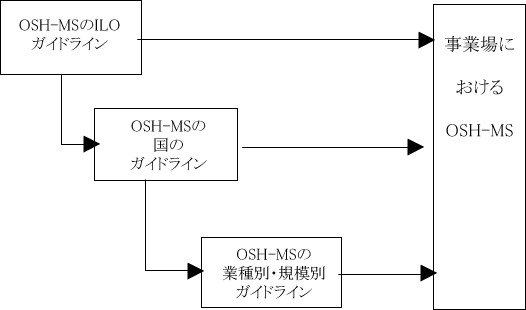
3 事業場におけるOSHMS
労働安全衛生は、使用者の責任であり、義務であること。使用者は、事業場における
OSH活動に強力なリーダーシップと責任を示すとともに、OSHMの確立のための適切な仕組みづくりを行うこと。OSHMSは、主要な要素である「計画・実施・評価・改善」を含むものとすること。
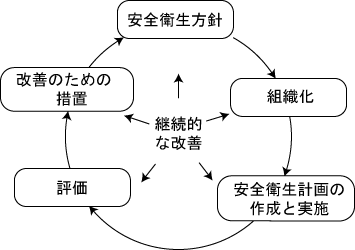
3.1 安全衛生方針[OSH policy]
- 使用者は、文書で安全衛生方針(OSH方針)を定めること。
<OSH方針の要件として5項目を明記>(3.1.1)
- OSH方針は、事業場で認めた次の基本原則及び目的を含んでいること。(3.1.2)
- 作業関連の負傷、不健康、疾病及び事故を防止することにより、事業場のすべての者の安全と健康を確保すること。(3.1.2.a)
- 法令、事業場の自主的安全衛生規程等を遵守すること。(3.1.2.b)
- 労働者及びその代表者が意見を聴かれるとともに、OSHMSのすべての要素に積極的に参加するよう奨励されることを確保すること。(3.1.2.c)
- OSHMSの実施状況についての継続的な改善を行うこと。(3.1.2.d)
- OSHMSは、事業場における他のマネジメントシステムと両立しうるものであるか又はその中に組み込まれものであること。(3.1.3)
3.2 労働者の参加[worker participation]
- 労働者の参加は、事業場におけるOSHMSの本質的な要素であること。(3.2.1)
- 使用者は、作業に関連するOSHのすべての点について労働者や安全衛生代表者が意見を聴かれ、情報を与えられ、教育・訓練を受けることを確保すること。(3.2.2)
- 使用者は、労働者及び労働者代表がOSHMSのすべての過程に積極的に参加するための時間及び資源を保有するような仕組みをつくること。(3.2.3)
- 使用者は、適当な場合、国内法令に従って安全衛生委員会を設立すること、これを有効に機能させること等を確保すること。(3.2.4)
3.3 責任と説明責任[responsibility and accountability]
- 使用者は、労働者の安全衛生の確保の全責任を負い、事業場のOSH活動に強力なリーダーシップを発揮すること。(3.3.1)
- 使用者及び上級管理者は、OSHMSの開発、実施及び運用並びにOSH目標の達成のための責任、説明責任及び必要な権限を担当者に割り振り、組織及び手続きを確立すること。
<組織及び手続きの内容として11項目を明記>(3.3.2)
- 責任、権限及び説明責任を有する上級管理者レベルの者が指名されること。
<目的として3項目を明記>(3.3.3)
3.4 能力及び教育・訓練[competence and training]
- 必要なOSHに関する能力を特定すること。また、すべての者が安全衛生に関する義務と責任を履行するための能力を有することを確保するための仕組みが定められ、維持されること。(3.4.1)
- 使用者は、OSHMSを実施するため、作業に関連する危険有害要因及びリスクを特定し、除去し、管理するための能力を有すること。(3.4.2)
- (3.4.1)に基づき、教育・訓練のプログラムが実施されること。
<教育・訓練のプログラムの要件として6項目を明記>(3.4.3)
- 教育・訓練は、可能な場合は、すべての参加者に対して、費用を求めることなく行
われ、また、就業時間中に行われること。(3.4.4)
3.5 安全衛生マネジメントシステム文書類[OSH management system documentation]
- 事業場の規模及び活動の性格に従って、OSHMS文書が定められ、維持されること。OSHMS文書は、次のものを対象とすること。(3.5.1)
-
-事業場のOSH方針及びOSH目標。(3.5.1.a)
- -OSHMSの実施のための割り振られた鍵となるOSH管理の役割及び責任。(3.5.1.b)
- 事業場の活動から起こりうる重要なOSHの危険有害要因及びリスク並びにそれらの除去及び管理のための仕組み。(3.5.1.c)
- OSHMSの枠組みの中で用いられる仕組み、手順、指示書及びその他の内部文書。(3.5.1.d)
- OSHMS文書は、それを使用する者に理解できるように明確に表現されるとともに、定期的に見直され、必要に応じ改訂され、事業場のすべての関係者に伝達され、容易に入手できるものとなっていること。(3.5.2)
- OSH記録は、作成され、管理され、維持されること。それらは、特定され、後からさかのぼることができ、保存期間が特定されること。(3.5.3)
- その秘密性を尊重されつつも、労働者は、作業環境や健康に関する記録を入手する権利を有すること。(3.5.4)
- OSH記録は、次のものを含むこと。
<OSH記録として5項目を明記>(3.5.5)
3.6 コミュニケーション[communication]
- 次の仕組みと手順が定められ、維持されること。(3.6.1)
- OSHに関連した事業場内外とのコミュニケーションについて、これを受理し、文書化し、適切に対応すること。(3.6.1.a)
- OSHの情報についての事業場内のコミュニケーションを確保すること。(3.6.1.b)
- OSHに関する労働者及びその代表の関心、考え及び情報提供が受け入れられ、検討され、対応されることを確保すること。(3.6.1.c)
3.7 初期調査[initial review]
- 事業場における既存のOSHMS及び関連の仕組みが評価されること。(3.7.1)
- 初期調査は、労働者及びその代表者の意見を聴きながら、能力を有する者により、 実施されること。また、初期調査は、次によるものとすること。(3.7.2)
- 現行の適用される国内法令、国のガイドライン、業種別・規模別OSHMSガイドライン、自主的安全衛生規程等のOSHの要求事項及びその他の要求事項を特定すること。(3.7.2.a)
- 労働者の安全衛生に及ぼす危険有害要因及びリスクを特定し、予知し、及び評価すること。(3.7.2.b)
- 計画されている管理、又は既存の管理が危険有害要因を除去し、又はリスクを管理するために適当であるかどうか決定すること。(3.7.2.c)
- 労働者の健康調査から得られるデータを分析すること。(3.7.2.d)
- 初期調査の結果は、次によるものとすること。(3.7.3.)
- 文書化されること。(3.7.3.a)
- 関係の決定の基礎とすること。(3.7.3.b)
- 事業場のOSHMSの継続的改善が実施されるベースラインを提供するこ と。(3.7.3.c)
3.8 安全衛生計画の作成とその実施[system planning, development and implementation]
- OSH計画の作成の目的は、国内法令の遵守、OSHMSの各要素の実施及びOSHの実施状況の継続的改善に役立てることであること。(3.8.1)
- 初期調査、その後の調査又はその他の利用可能なデータに基づき、適切なOSH計画を作成するための仕組みを確立すること。このOSH計画の仕組みは、作業場の安全衛生の確保に寄与するものであり、次のものを含むこと
<OSH計画の仕組みとして含むべき4項目を明記>(3.8.2)
- 事業場のOSH計画の仕組みは、すべてのOSHMSの要素の開発及び実施を対象とすること。(3.8.3)
3.9 安全衛生目標[OSH objectives]
- OSH方針との一貫性を保ちつつ、初期調査及びその後の調査に基づき、計測可能なOSH目標が定められること。(3.9.1)
<OSH目標の要件として6項目を明記>
3.10 危険有害要因の除去[hazard prevention](3.10)
3.10.1 除去及び管理対策(prevention and control measures)
- 危険有害要因及び労働者の安全と衛生に及ぼすリスクが特定され、評価されること。防止対策(preventive
and protective measures)が一定の優先順位で実施されること。
<対策として4項目を挙げ、その優先順位を明記>(3.10.1.1)
- 危険有害要因の除去及び管理の手順又は仕組みが定められ、次の事項が実施されること。(3.10.1.2)
- 事業場で起こりうる危険有害要因及びリスクに適用されること。(3.10.1.2.a)
- 定期的に見直され、必要に応じ改正されること。(3.10.1.2.b)
- 国内法令に適合し、好事例を反映していること。(3.10.1.2.c)
- 最近の知見を考慮すること。(3.10.1.2.d)
3.10.2 変更に対する管理(management of change)(3.10.2)
- 内部の変更及び外部の変化による影響が事前に評価され、適切な措置が講じられること。(3.10.2.1)
- 作業場の危険有害要因の特定及びリスクの評価が作業方法、物質、工程、機械等の変更または新たな導入に先立って実施されること。(3.10.2.2)
- 変更の決定については、すべての影響を受ける者に知らされ、これらの者に必要な教育訓練が実施されることが確保されること。(3.10.2.3)
3.10.3 緊急事態への対応(emergency prevention, preparedness and response)
- 緊急事態への対応についての仕組みが定められ、維持されること。これらの仕組みは、災害や緊急事態の可能性を特定し、それに関連するリスクの防止に言及されていること。これらの仕組みは、次のように定められること。(3.10.3.1)
- 現場の緊急事態の際にすべての者を保護するため、必要な情報、内部の伝達事項及び協調が提供されることを確保すること。(3.10.3.1.a)
- 関係の当局、近隣の者及び緊急サービス機関に必要な情報及び伝達事項を提供すること。(3.10.3.1.b)
- 応急手当、医療援助、消火及び現場のすべての者の避難について言及すること。(3.10.3.1.c)
- 緊急事態の定例の訓練を含め、情報及び訓練を事業場のすべてのレベルの者に提供すること。(3.10.3.1.d)
- 緊急事態への対応についての仕組みは、外部の緊急サービス機関との協力の下に定められること。(3.10.3.2)
3.10.4 調達[procurement]
- 次の事項が確保されるように調達の手順が定められ、維持されること。(3.10.4.1)
- 事業場の安全衛生の要求事項の遵守が特記され、評価され、及び購入やリ ースの仕様に組み込まれていること。(3.10.4.1.a)
- 国内法令及び事業場のOSHの要求事項が物品やサービスの調達以前に特 定されること。(3.10.4.1.b)
- それらの使用の以前に要求事項に対する適合を達成するための仕組みづく りがなされていること。(3.10.4.1.c)
3.10.5 契約[contracting]
- 事業場の安全衛生の要求事項又は少なくともこれと同等のものが請負業者及びその労働者に適用されることを確保するために、仕組みが定められ、維持されること。(3.10.5.1)
- 作業現場の請負業者についての仕組みが次のように定められること。(3.10.5.2)
- 請負業者を評価し、選定するためのOSHに関する基準を含めること。 (3.10.5.2.a)
- 作業を開始するに当たり事業場と請負業者の適切なレベル間のコミュニケーションと協力関係を構築すること。(3.10.5.2.b)
- 作業関連の負傷、不健康、疾病及び事故の報告の仕組みを含めること。(3.10.5.2.c)
- 作業を開始するに当たり、また、作業の進行に合わせて、請負業者の労働者に作業現場の安全衛生に関する危険有害要因の適切な情報(awareness)及び教育訓練を提供すること。(3.10.5.2.d)
- 現場での請負業者の活動におけるOSHの実施状況を定期的に調査すること。(3.10.5.2.e)
- 現場のOSHの手順及び仕組みが請負業者によって守られることを確保すること。(3.10.5.2.f)
3.11 実施状況の調査及び測定[performance monitoring and measurement]
- OSHの実施状況を調査し、測定し、及び記録する手順が開発され、定められ、定
期的に見直されること。(3.11.1)
- 実施状況についての指標(indicators)が事業場の規模及び活動状況並びにOSH目標に応じて選定されること。(3.11.2)
- 事業場の必要性に応じて定性的で定量的な測定が考慮されること。(3.11.3)
- 測定は、事業場において特定された危険有害要因及びリスク並びにOSH方針及びOSH目標に基づくこと。(3.11.3.a)
- 測定は、マネジメントレビューを含め、事業場の評価の過程に役立つこと。(3.11.3.b)
- 実施状況の調査及び測定(3.11.4)
- 実施状況の調査及び測定は、OSH方針及びOSH目標が実施されリスクが管理されている程度を決定する手段として用いられること。(3.11.4.a)
- 実施状況の調査及び測定は、日常的な調査及び問題点に対する調査の両者を含めたものであり、作業関連の負傷、不健康、疾病及び事故の統計のみに基づくものではないこと。(3.11.4.b)
- 実施状況の調査及び測定は、記録されること。(3.11.4.c)
- 調査は、次のものを提供すること。(3.11.5)
-
-OSHの実施状況のフィードバック。(3.11.5.a)
- 危険有害要因及びリスクの特定並びにその除去及び管理対策のための日々の仕組みが適当であるかどうか、及び効果的に実施されているかどうかを決定するための情報。(3.11.5.b)
- 危険有害要因の特定及びリスクの管理並びにOSHMSにおける改善の決定のための基盤。(3.11.5.c)
- 日常的な調査は、事前の準備に必要な要素を含むとともに、一定の事項を含むこと。
<含めるべき事項として5項目を明記>(3.11.6)
- 問題点に対する調査は、一定の事項を含むこと。
<含めるべき事項として4項目の特定、報告、記録及び調査である旨を明記>(3.11.7)
3.12 作業関連の負傷、不健康、疾病及び事故並びに安全衛生の実施状況に及ぼす影響に
ついての調査
- 作業関連の負傷、不健康、疾病及び事故についての直接原因(origin causes)及び背景原因(underlying
causes)の調査は、OSHMSの不備を特定するものであり、また、これらは文書化されること。(3.12.1)
- この調査は、労働者及びその代表者の参加を得て、能力を有する者により行われること。(3.12.2)
- この調査結果は、安全衛生委員会に伝えられ、安全衛生員会は、適切な勧告を行うこと。(3.12.3)
- 調査結果は、安全衛生委員会からの勧告と併せて、是正措置を担当する適切な者に伝えられるとともに、マネジメントレビューに含まれ、継続的な改善活動のために検討されること。(3.12.4)
- この調査に基づく改善措置は、作業関連の負傷、不健康、疾病及び事故の再発を防止するために実施されるものであること。(3.12.5)
- 監督官及び社会保障機関等の外部の調査機関による報告は、その秘密性を考慮しながら、内部の調査と同様に実施されること。(3.12.6)
3.13 監査[auditing]
- 定期的な監査を行うための仕組みが定められること。(3.13.1)
- 監査の方針及びプログラムが開発されること。これは、監査者の指定、監査の範囲、頻度、方法(methodologies)及び報告を含むこと。(3.13.2)
- 監査は、事業場のOSHMSの各要素の評価を含むこと。
<OSHMSの各要素として19項目を明記>(3.13.3)
- 監査の結論は、実施されたOSHMS、その要素等についての次の事項を勘案して決定されること。(3.13.4)
- 事業場のOSH方針及びOSH目標に対して有効であったかどうか。(3.13.4.a)
- 完全な労働者の参加を推進することについて有効であったかどうか。 (3.13.4.b)
- OSHの実施状況の評価及び以前の監査の結果に対応しているかどうか。 (3.13.4.c)
- 事業場が国内法令の遵守を達成することが可能かどうか。(3.13.4.d)
- 継続的な改善及び最良のOSHの実施といった目的を全うしているかどうか。(3.13.4.e)
- 監査は、監査の対象となる活動から独立し、かつ、能力を有する内部又は外部の者によって行われること。(3.13.5)
- 監査の結果及び結論は、是正措置に責任の有る者に伝えられること。(3.13.6)
- 監査者の選定及び結果の分析を含め、監査のすべての段階において、必要に応じ、労働者の意見を聴くこと。(3.13.7)
3.14 マネジメントレビュー[management review]
- ・マネジメントレビューでの実施事項(3.14.1)
- OSHMSの全般的な戦略が計画された目的に合致しているかどうか決定するためそれを評価すること。(3.14.1.a)
- 事業場及び関係者のすべての必要性を満たすためのOSHMSの能力を評価すること。(3.14.1.b)
- OSH方針及びOSH目標を含め、OSHMSの変更の必要性を評価すること。(3.14.1.c)
- 欠陥を是正するために必要な措置を特定すること。(3.14.1.d)
- OSH計画及び継続的改善のための優先順位の決定を含んだフィードバックの方向性を提供すること。(3.14.1.e)
- 事業場のOSH目標並びに防止及び改善措置に向けての進展を評価すること。(3.14.1.f)
- 以前のマネジメントレビューに対するフォローアップの効果を評価するこ と。(3.14.1.g)
- 使用者又は最も上位の責任者によるOSHMSの定期的なレビューの頻度及び範囲は、事業場の必要性及び実情に従って明確にされること。(3.14.2)
- マネジメントレビューでの考慮事項
<考慮事項として2項目を明記>(3.14.3)
- マネジメントレビューの結果(the findings)は記録され、一定の者に伝えられること。
<伝えられるべき者として2者を明記>(3.14.4)
3.15 防止及び是正措置[preventive and corrective action]
- OSHMSの実施状況の調査及び測定、監査並びにマネジメントレビューに基づく防止及び是正措置のための仕組みが定められ、維持されること。
<仕組みに含まれる事項として2項目を明記>(3.15.1)
- OSHMSの評価又はその他の資料により、危険有害要因及びリスクに対する防止対策が不適当か又は不適当になる可能性が有ると認められるときは、認められた程度に従って対応され、必要に応じ、また、適切な時期に文書化されなければならないこと。(3.15.2)
3.16 継続的な改善[improvement]
- OSHMSの各要素及び全体の継続的な改善のための仕組みが定められ、維持されること。これらの仕組みは、一定の事項が考慮されること。(3.16.1)
<考慮される事項として9項目を明記>
- 事業場の安全衛生の過程及び実施状況は、安全衛生の実施状況の改善のために他の事業場と比較されること。(3.16.2)
(注)・()内の番号は、ILOのOSHMSガイドライン(案)の項目の番号であ
る。
用語集
- 日常的な調査(Active monitoring)
- 監査(Audit)
- 権限有る機関(Competent institution)
- 能力を有する者(Competent person)
- 継続的な改善(Continual improvement)
- 請負者(Contractor)
- 使用者(Employer)
- 危険有害要因(Hazard)
- 危険有害要因の評価(Hazard assessment)
- 事故(Incident)
- 組織(Organization)
- 労働安全衛生マネジメントシステム(OSH management system)
- 問題点に対する調査(Reactive monitoring)
- リスク(Risk)
- リスクの評価(Risk assessment)
- 安全衛生委員会(Safety and health committee)
- 作業環境の監視(Surveillance of the working environment)
- 労働者(Worker)
- 労働者の健康の監視(Workers' health surveillance)
- 労働者及びその代表(Workers and their representatives)
- 労働者の代表(Workers' representative)
- 労働者の安全衛生代表(Workers' safety and health representative)
- 作業に関連した負傷、不健康及び職業性疾病(Work-related injuries, ill health
and diseases)
- 作業現場(Worksite)
- 参考書目録
-
ILO条約及び勧告
ILOコードオブプラクティス
関連の出版物
「ILO Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH
2001)」は下記のページでご覧いただけます。
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/managmnt/guide.htm
|