国際安全衛生センタートップ >
海外安全衛生情報:安全衛生情報誌 >
雑誌「Safety + Health」
NSC発行「Safety + Health」2005年1月号
ワシントン − 2004年12月8日に辞任した労働安全衛生庁(Occupational Safety and Health Administration: OSHA)のジョン・ヘンショー長官(John Henshaw, administrator)に対し、安全業界のリーダーから称賛が寄せられた。ヘンショー長官は、12月31日付で任期を終えた。 まずは、ヘンショーOSHA長官の上司、エレイン・チャオ労働長官(Elain Chao, Labor Secretary)が称賛を寄せた。「ジョン・ヘンショー氏は、アメリカの労働者の安全衛生のために、傑出した統率力、高い見識と誠意を示した」とチャオ労働長官。「より安全で衛生的な職場づくりに、ジョンは貢献した。彼の統率力のもと、労働死亡災害は空前の最低値を記録し、1995年以来増えていたヒスパニック系労働者の死亡災害も、2001年以来、約12%減った」。 ヘンショーOSHA長官のもっとも意欲的なキャンペーンは、おそらく労使との非規制的な関係の拡充であった。自主的保護プログラム(Voluntary Protection Program)は、ヘンショーOSHA長官の統率下、1,100を超える事業場に拡大、今日では、200以上もの戦略的パートナーシッププログラム(Strategic Partnerships Program)とおよそ200の同盟(アライアンス alliance)をも包含するにいたった。こうした協同プログラムのうち、350強は労組の参加を得たもので、これは史上最高の記録である。 「ジョン・ヘンショー氏は、労働安全衛生担当労働副長官(Assistant Secretary of Labor for Occupational Safety and Health)として、米国の労働安全改善のリーダー、先見者、協力者、活動家の役割を担った」と、全米安全評議会(National Safety Council: NSC)のアラン・C・マクミラン会長兼最高経営責任者(Alan C. McMillan, president and CEO)は述べた。「ジョンは、米国の労働安全衛生分野で信任の厚い世話役であり、アメリカの労働安全の向上をめざし、政労使、民間部門間で前例のない共同体を創った功労者である」。 「氏のたゆまぬ統率力と、氏とともに安全衛生へ情熱を傾ける人々の間に幅の広い同盟、パートナーシップ、イニシアチブを創設しようとした試みにより、業務上の死傷は、史上最低値を記録するにいたった」とマクミラン会長。「ジョンは、全米安全評議会のわれわれ同様、労働安全衛生は、企業責任であり、アメリカのビジネス、労働者に対する長期投資であると考えている」。 「彼は、アメリカの安全衛生をめざす傑出した、建設的な活動家であった」と、NSC理事会(board)のジェド・ブラード理事長(Jed Bullard, chairman)は述べた。「彼は、同盟という、OSHA問題の認識を高めるうえで独創的な方法で、大いに功績を残した。彼は、OSHAはビジネスにどう役立つか、示したのである」。 ヘンショー氏は、OSHA入庁前には、化学工業で環境安全衛生プログラムを26年間以上指導し、米国産業衛生協会会長(president, American Industrial Hygiene Association)、米空軍州兵(U.S. Air National Guard)の生物環境エンジニアも務めた。彼はまた、NSCのセントルイス支部(St. Louis Chapter)の前支部長でもある。
ワシントン − 一部の観測筋によると、11月のブッシュ大統領の再選で、今後4年間の安全衛生は、現状路線となりそうである。 2004年12月7日にはジョン・ヘンショーOSHA長官、11月12日にはデイビッド・ローリスキ鉱山安全衛生庁長官(David Lauriski, administrator, Mine Safety and Health Administration: MSHA)がそれぞれ辞任したが、ブッシュ政権のアプローチは変わらず、産業界とのパートナーシップや同盟に重きを置き、規制や基準作成は控えめという路線を引き継ぐと観測筋はみる。エレイン・チャオ労働長官は、ブッシュ大統領の要望で、現職にとどまる。 「私は、ブッシュ政権2期目に重大な変化がたくさん出るとは思わない。私は、たとえばパートナーシップの強調といった、定番プログラムの大半は引き継がれ、拡充路線をとるだろうと予想する」と、ワシントン市の労働弁護士ウィリス・ゴールドスミス(Willis Goldsmith)氏はいう。同氏は、全米エルゴノミクス諮問委員会(National Advisory Committee on Ergonmics)の委員であったが、エルゴノミクス政策でOSHAに助言する2年の任期は、2004年11月に切れた。 オレゴン州消費者商業サービス省(Oregon Department of Consumer & Business Services, Salem、セイラム市)のピーター・デルカ長官(Peter De Luca, administrator)は、州版OSHAプログラムを実施しており、自身は、全米労働安全衛生諮問委員会(National Advisory Council on Occupational Safety and Health)の委員長を務めているが、やはり、ブッシュ政権の2期目に大きな変化は見られないだろうと同意する。 全米安全評議会(NSC)理事会の元理事長で、法律事務所Constangy, Brooks and Smith LLC(アトランタ市)の業務執行社員(managing partner)を務め、労働雇用法を専門とするパトリック・R・タイソン(Patrick R. Tyson)氏は、ブッシュ政権が1期目で敷いた安全衛生路線は、実業界、産業界の幅広い支持を取り付けたと述べた。 「実業界は、今日、どのような問題についても動揺していないし、大規模な変化を引き出そうと政治資金を投入することもおそらくない」とタイソン氏。 実業界は、ブッシュ政権発足まもない2001年初め、論争の的となっていたクリントン政権のエルゴノミクス基準が、連邦議会再検討法(Congressional Review Act)で廃止されたことで、勢いづいた。「実業界は、従来とは違う見方でものごとを見ている」とタイソン氏はいい、エルゴノミクス基準が否決される前は、産業界は「業界好みの」安全衛生規制にするよう、連邦議会の業界支持者に働きかけようと努めたものだと説明した。 「連邦議会再検討法がエルゴ基準を廃した今は、実業界はなんの規制もいらないと考えていると思う」とタイソン氏は付け加えた。 2期目を形づくる未知数は、2つある。まずは、反対派、とくに1期目で政策をめぐり、労働安全衛生庁(OSHA)と鉱山安全衛生庁(MSHA)と大きく袂をわかった労働組合の、闘争の度合いである。もう一つは、鍵となる政府機関が、プログラムの焦点を2期目に変更する度合いである。たとえばOSHAは、ヒスパニック系労働者の安全衛生やエルゴノミクス・ガイドライン、業務上運転のハザードといったアピール度の高いイニシアチブを展開してきた。 一方、組織労働者は、対決姿勢をとっている。1期目には、エルゴノミクス基準の廃止や残業手当に関する連邦規則の変更、新法規の延期や棄却など、数多くの痛手を受け、さらなる痛手も予想される。労組は、1期目は、規制より同盟を優先するヘンショー、ローリスキ両長官と論争が絶えなかった。 「安全衛生面では、かなり厳しい時期を迎えると思う」と、AFL-CIO(アメリカ労働総同盟産業別労働組合会議、ワシントン市)のペグ・セミナリオ労働安全衛生部長(Peg Seminario, director, Department of Occupational Safety and Health)はいう。「OSHAが、安全衛生で指導力を発揮するとは思えない」。 組織労働者は、OSHAやMSHAといった政府機関は、労働安全規則の施行にもっと積極的な役割をはたすべきであると考える。セミナリオ氏は、1期目のOSHAの姿勢は「かなりおとなしかった」と特色づけた。 組織労働者の側からの闘争は、なんであれ、政権との予算攻防をたどる。セミナリオ氏は、過去数年間ほぼ横ばいの連邦安全衛生当局の予算は、ブッシュ政権の財政赤字削減の標的の一つになるだろうと考えている。昨今の予算サイクルでは、労組のリーダーらは、ブッシュ政権は、従来、職場の遵守プログラムに向けられていた予算を、自主的な、事業者寄りの分野に振ろうとしていると非難してきた。 新しいプログラムについて、OSHAやMSHAといった政府機関の長は、政権の政策の枠内で裁量を与えられていると観測筋はいう。新しいプログラムイニシアチブについては、OSHAや国立労働安全衛生研究所(National Institute for Occupational Safety and Health: NIOSH)に助言する全米労働安全衛生諮問委員会(National Advisory Committee on Occupational Safety and Health: NACOSH)などといった諮問委員会で、その兆しが現れるだろう。デルカ氏は、昨夏のヒスパニックサミットの企画を後押ししたNACOSHは、OSHA、NIOSHの長から方向性を与えられるだろうから、その方向性に変化がないか、見守ると言及した。 ヘンショー氏は、任期中、事業者が国の安全法規を遵守するよう、いわゆる「効果的な執行」を強調した。執行とは、教育、アウトリーチや自主的遵守と並び、OSHAのパラダイム(枠組み)の一部をなすとヘンショー氏は言った。ヘンショー氏は、監督件数を増やし続けて、批判をいくぶんかわす一方、悪質な違法件数は減っていったと、タイソン氏はいう。ヘンショー氏は、2004年11月18日の記者会見で、監督件数は、OSHAの2004年度の目標値を上回ったと述べた。 「われわれの目標監督件数は、これまでの水準と同じとなる」と、ヘンショー氏は、2004年度労働監督報告を発表するにあたり、こう述べた。「われわれは、結果をどう改善するか、これにエネルギーを収束させるのである。私は、同じ事業場へなんども戻るのは、資源の無駄づかいだと思う。われわれがやりたいのは、効果的に監督するということであり、つまり、ある事業場に行き、持続可能な変化をもたらして、今度は傷害率や危険度の高い別の事業場へ行くことができるようにするということである。私のいう『効果的』とは、こういうことである」。 ジョンズ・デイ(Jones Day)氏との共同経営者、ゴールドスミス氏は、OSHAは、「ここ数ヶ月内に始められた政策やプログラムに沿って」、監督行政で環境保護局(Environment Protection Agency: EPA)との協力関係を促進させて、費用を節約し、弱腰の監督行政という批判をよりいっそうかわす機会をつくるとよいと述べる。 安全衛生の利害関係者らは、向こう4年間で法改正があるかどうか、連邦議会に注意を向ける。マイク・エンジ上院議員(Mike Enzi、共和党、ワイオミング州)やチャーリー・ノーウッド下院議員(Charlie Norwood、共和党、ジョージア州)は、第108回連邦議会でOSHA関連法案を提出した。エンジ議員は、現在、OSHA、MSHAを所管する雇用安全訓練小委員会(Employment, Safety and Training Subcommittee)の委員長だが、次期議会で委員長交代があれば、衛生教育労働年金委員会(Health, Education, Labor and Pension Committee)の委員長を引き受けるという。エンジ議員は、同委員会の共和党員のなかでは、最年長から二人目である。 タイソン氏は、政府内で重要な法案が浮上するかどうか、ここでも懐疑的である。というのも、現政権内の事業者寄りの関係者らは、すでにことが有利に展開している以上、政治資金を投じようとは思わないだろうからである。 全米安全評議会(NSC)のボビー・ジャクソン全米プログラム担当上級副会長(Bobby Jackson, senior vice president, national program)は、NSCは引き続き、「米国の安全衛生関連の公共政策・計画に影響力を行使する」連邦議会やOSHA、MSHAといった政府機関のリーダーらと緊密な協力関係を築いていくと述べた。
ワシントン − 環境保護局(EPA)は、初の電子版年次有害物質排出目録(Toxics Release Inventory: TRI)で、2003年度有毒化学物質排出データを例年より早く公開した。TRIプログラムは、産業施設に対し、大気、土壌、河川への有毒化学物質の年間排出量を公表するよう、義務付けている。 新しい電子版施設別データ公開(Electric-Facility Data Release)は、化学物質毎にあてがわれた報告用紙で、各施設がEPAに提出した「生の」データを提示している。正確さについては、内蔵の品質チェックで保証していると当局はいう。 内容の質をより徹底し、全米規模の傾向や分析を盛り込んだ従来型の刊行物は、2005年春に発行する予定。 電子版は、www.epa.gov/tri-efdrで閲覧できる。
ワシントン − 労働安全衛生庁(OSHA)のジョン・ヘンショー長官は、11月18日の記者会見で、当局の監督実績は2004会計年度目標を上回ったと述べた。 ヘンショー長官は、2004年の監督件数は39,167件と、目標値の37,700件を上回り、このなかには新しい監督強化プログラム(Enhanced Enforcement Program: EEP)に基づく300件も含まれていると述べた。EEPは、安全衛生義務を再三無視する事業者を対象としている。OSHAはまた、特定事業場監督プログラム(Site Specific Targeting Program)で、ハザードの高い産業のおよそ3,000の事業場を監督した。 これらの監督業務で、OSHAは、安全衛生法規違反86,708件を通告したが、これは2003年の3.8%増、過去5年間でおよそ10%増となった。監督件数は、OSHAの労働安全衛生に対する「均衡のとれた」アプローチを実証するものであると、ヘンショー長官は述べた。このアプローチには、訓練、遵守支援、アウトリーチ、教育、パートナーシップおよび協同プログラム、監督行政が含まれる。 「このアプローチの有効性は、実証された。労働死傷病率が、労働力人口が増大しつづけているにもかかわらず、これまでの最低値を記録しているからである」と、同氏は述べた。
ワシントン − 環境保護局(EPA)は、規制汚染物質から6種類の化学物質を除外し、産業界には毒性の低い溶剤を使用するよう誘導する。 化学物質一つ一つを再検討した結果、「これらの化学物質は、当初考えられたよりもリスクが少なく、これらを規制除外とすることで、公衆衛生にしわ寄せがくるわけでもなく、むしろ、より毒性の高い、環境を破壊する化学物質の代替物として利用された場合、公衆衛生のためになろう」と、EPAは述べた。 6種類の化学物質とは、規制大気汚染物質から外されたエチレン・グリコール・モノブチル・エーテルと、揮発性有機化合物から外された酢酸t-ブチル、HFR-7000、HFE-7500、HFC227ea、ギ酸メチルである。
バージニア州アーリントン − 米国規格協会(ANSI)の高可視性安全服基準最新版によると、高可視性安全服メーカーは、商品が当該ANSI基準の全要件を満たしている旨の書類を最終消費者に提示しなければならない。 ANSI 107-2004基準は、ジャケット、ベスト、つなぎ、ズボン、帽子、転落・墜落防護ハーネス型安全帯などの高可視性安全服のデザイン、性能明細や用途を規定している。 基準の改訂版は、袖なし服は、単独着用の場合、性能3級を満たさないとし、定義を拡充し、車両速度に基づく特定環境下での安全服等級やこうした安全服の利用に言及する箇所を削除している。 基準は、事務局を務める国際保安用品協会(International Safety Equipment Association)で入手できる。
英国ギルフォード(Guildford) − 英国の労働力人口を対象とした新しい調査によれば、業務上のストレスは、筋骨格系障害(musculoskeletal disorders: MSDs)の発症に関わっており、年齢や憂うつな気分は、それほど影響はない。 サリー大学(University of Surrey)の労働システムデザイン専門家であるジェイソン・デベルー(Jason Devereux)氏は、11産業部門、20社の労働者8,000人を3年間余り調査した。同氏は、年齢、性別、神経質や憂うつな気分は、筋骨格系障害の発症にほとんど、あるいはまったく影響を及ぼさないことを突き止めた。 しかし、労働の身体的、心理的側面の両方が、筋骨格系障害の発症に直接関わっていることが、調査で判明した。 調査の最大の所見は、業務上のストレスが筋骨格系障害の発症に関わっていることであった。デベルー氏は、業務上ストレスと筋骨格系障害は共に、作業編成における人間と工程の不均衡の兆候であると述べた。状況を打開するには、意思疎通、組織への信頼、労働者の参加を要する。労働安全衛生規則の単なる適用は、「効果が限定されやすい」とデベルー氏は警告する。
バージニア州アーリント − 2003年には、210人の自動車運転者が、おもに鹿などの動物と衝突して死亡した。道路交通安全保険協会(Insurance Institute for Highway Safety)の調査によると、この数字は、前年比40人増で、1993年の2倍以上であった。ウィスコンシン州では11人が死亡したと記載されているが、10年前は3人であった。 研究所によれば、事故は、11月に最も発生しやすい。というのも、猟師は歩きまわり、鹿は交尾期の最中だからである。この二つの要因が、鹿たちを移動させるのである。衝突事故は、夕暮れ時や夜間にもっとも発生しやすく、制限時速55マイル以上の人里はなれた道路でよく発生する。 「毎年、鹿は増え、路上を行く自動車も増えている」と、11月17日、研究所のアラン・ウィリアムズ主席研究員(Allan Williams, chief scientist)は述べた。「道路で動物に出くわす機会が大幅に増えている」。 動物との衝突死亡事故のおよそ75%は、鹿が占める。昨年、鹿との衝突事故は、あわせて150万件で、13,713人が負傷、11億ドルの車両損害をもたらしたと、研究所はいう。 衝突事故を招くこの他の動物は、馬、アメリカヘラジカ、犬、熊、猫、畜牛やオポッサム(フクロネズミ)などであるが、これらは、大した件数ではない。
ワシントン − 死亡労働災害10人中1人は複数の死亡者を出した労働災害で死亡しており、このうち数件は大規模労働災害であると、労働統計局(Bureau of Labor Statistics: BLS)は、初の調査で報告した。 労働統計局は、1995〜1999年の間、二人以上が死亡した災害すべてのデータを吟味した。調査によれば、死者複数の死亡災害の件数は、全労働死亡災害件数のわずか4%にすぎないが、このような災害での死亡者数は、全労働災害死亡者数の約10%に相当する。死者複数の死亡災害の約4分の3は、死者は二人だが、大規模災害9件では、労働者あわせて266人の命が奪われた。全体でみると、死者複数の死亡災害は、1件あたり平均3人が死亡、年平均222件である。 労働統計局は、この種の死亡災害がどこで発生するかについても調査した。こうした災害に遭遇した労働者の大半は、なんらかの形での業務上の移動の最中に死亡していることが判明した。移動手段から大きく開いて、殺人、火災・爆発が続く。 産業別にみると、死者複数の死亡災害は「やや均等に」分布していると、労働統計局はいう。目立ったところでは、多重殺人が「とくに多い」中古車販売業や、石油・石炭製品業の死者複数の死亡災害のほとんどすべてを占める石油精製業といった産業が挙げられる。 対照的に、死者複数の死亡災害は、「工場のような生産現場の職種では、一般的には主流ではない」ことを、労働統計局は突き止めた。 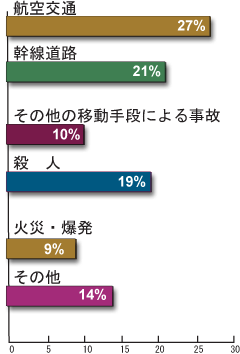 出 所:労働統計局(BLS)、2004年 労働統計局は、死者複数の死亡災害は、大抵の場合、発生状況に潜む致死性の事故・ばく露や、災害が頻発する職種といったなかに、死亡災害の全体像を映すものはないと述べ、これらはすべて「唯一無二の現象である」と結論した。 この調査結果は、月間労働報告(Monthly Labor Review)オンライン版2004 年10月号で報告された。
イリノイ州アーバナ― − イリノイ大学(University of Illinois、アーバナキャンペイン、Urbana-Champaign)の調査チームによれば、運転者は、年齢にかかわらずハンズ・フリー携帯電話の使用中、目の前の危険な状況を認識するのに難儀する。 「Human Factors」誌(Vol. 46, No.2)に掲載された実験は、同大学ベックマン高等科学技術研究所(Beckman Institute for Advanced Science and Technology)のバーチャル・リアリティ空間で実施された。調査チームは、視線追跡技術で、注意散漫の影響を調べた。 実験では、運転免許を保持し、最低1年間の運転経験のある若年運転者14人と、運転経験の豊富な年配の14人に、ハンズ・フリー携帯電話でちょっとした会話に積極的に取り組んでもらった。 被験者は、会話しながら、シカゴ市の移り行く往来や建物をデジタル処理して映し出した6 X 3.5フィートのスクリーンに対面した。画面のちらつきは、目の動きを模しており、この後に続く風景の変化は、運転者にとって重要であったり、重要でなかったりした。 年配者は、色彩が鮮明になってくるなど、顕著な変化を見極めることができた。しかし、運転に重要な変化を認識する能力は、著しく低下した。 |