 |
| 21. 電気による災害防止に関する規制 日本においては感電等の電気災害は激減してきているが、一旦発生すると、致命的な 被害になるので、事業者に次のことを要求している。 |
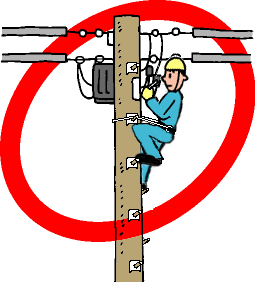 |
| 1.電気機械器具の防護 |
||||||||||
| 電気機械器具の充電部分には、囲い又は絶縁を設ける。 (配電盤室、変電室、電柱上等で電気取扱者だけが接近する場所は除く) |
||||||||||
| 2. 電灯、配線の安全 |
||||||||||
| (1) | 手持ち型電灯等 |
|||||||||
| 移動電線に接続する手持ち型の電灯、仮設の配線(建設現場等)に接続するつり下げ電灯等には、堅固なガードを取り付ける。 |
||||||||||
| (2) | 配線、移動電線 |
|||||||||
|
||||||||||
| 3. アーク溶接作業の安全 |
||||||||||
| (1) | 溶接棒ホルダー |
|||||||||
|
||||||||||
| (2) | 自動電撃防止装置 |
|||||||||
| 次の場所でアーク溶接作業を行なう時には、自動電撃防止装置を使用する。 |
||||||||||
|
||||||||||
| 4. 漏電による感電防止 |
||||||||||
| 次の条件下で使用される移動式または可般式の電動機械器具については、感電防止用漏電しゃ断装置を接続する。 |
||||||||||
|
||||||||||
| 5. 停電作業の安全 |
||||||||||
| 電路を開路して電路またはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等を行う場合、その電路に近接して電路の支持物の敷設等を行う場合、電路に近接する工作物の建設、解体等を行う場合には、次の措置を行うこと。 |
||||||||||
| (1) | 開路に用いた開閉器に、作業中施錠する、通電禁止の表示をする、監視人を配置する。 |
|||||||||
| (2) | 電路に電力ケーブル、電力コンデンサーが接続されていて残留電荷による危険がある場合には、残留電荷を放電させる。 |
|||||||||
| (3) | 高圧(交流600V以上、直流750V以上) または特別高圧(交流、直流とも7,000V以上)
の電路については、検電器具により停電を確認し、短絡接地器具で短絡接地を行う。 なお、高圧または特別高圧の電路の断路器、線路開閉器等については、無負荷であることを示すパイロットランプ等で無負荷であることを確認する。 |
|||||||||
| 6. 活線作業及び活線近接作業 |
||||||||||
| 充電電路の活線作業または活線に近接して作業を行う場合は、次の措置を行うこと。 |
||||||||||
| (1) | 活線作業の場合 |
|||||||||
|
||||||||||
| (2) | 活線近接作業 |
|||||||||
|
||||||||||
| 7. 充電電路に近接して工作物の建設・点検・修理等の作業を行う場合、クレーン等の作業を行う場合には、次の措置を行うこと。 |
||||||||||
| (1) | 充電電路を移設する。 |
|||||||||
| (2) | 囲いを設ける。 |
|||||||||
| (3) | 監視人を置き、監視させる。 |
|||||||||
| 8. 作業指揮者の選任 |
||||||||||
| 停電作業、活線作業、活線近接作業を行うときには、作業指揮者を定めて次のことを行わせること。 |
||||||||||
| (1) | 作業の方法、順序を周知させ、作業を直接指揮する。 |
|||||||||
| (2) | 特別高圧近接作業を行うときは、接近限界距離の標示、監視人の配置の確認を行う。 |
|||||||||
| (3) | 電路の停電の状況、開閉器の施錠、監視人の配置、短絡接地器具の取り付け状況を確認する。 | |||||||||
| (次回は、爆発火災の防止に関する規制を予定) | ||||||||||