![]()
![]()
 �������
������� ����
���� �����
����� �V�����j
�V�����j ����
����  �A�W�A���S�q�� SAKURA �v���W�F�N�g
�A�W�A���S�q�� SAKURA �v���W�F�N�g �X�}�C�� �A�W�A �v���W�F�N�g�T
�X�}�C�� �A�W�A �v���W�F�N�g�T �X�}�C�� �A�W�A �v���W�F�N�g�U
�X�}�C�� �A�W�A �v���W�F�N�g�U
![]()
![]()
![]()
���⍇��
�����J���ЊQ�h�~����i���Жh�j
�Z�p�x����
���ۉ�
TEL 03-3452-6297
FAX 03-5445-1774
E-mail�F kokusai@jisha.or.jp
![]()
���m�点
������̈ϑ����Ƃł�����
 �u���ۈ��S�q���Z���^�[�iJICOSH�j�v
�u���ۈ��S�q���Z���^�[�iJICOSH�j�v
 ��2008�N3�����������Ĕp�~����܂����B
�i�炭�̂����p���肪�Ƃ��������܂����B
���Z���^�[�̃T�C�g�Ɍf�ڂ���Ă����ʂ̏��ɂ��ẮA���ЖhWEB�T�C�g��
��2008�N3�����������Ĕp�~����܂����B
�i�炭�̂����p���肪�Ƃ��������܂����B
���Z���^�[�̃T�C�g�Ɍf�ڂ���Ă����ʂ̏��ɂ��ẮA���ЖhWEB�T�C�g�� �����A
�����A ��������Ƀ����N���Ď�荞��ł���܂��B
��������Ƀ����N���Ď�荞��ł���܂��B
![]()
PDF�`���̃t�@�C���������ɂȂ�ɂ́AAdobe Systems Incorporated�i�A�h�r�V�X�e���Y�Ёj��Adobe® Reader™���K�v�ł��B
 EU-OSHA���u�����Ō��鉢�B�̋؍��i�n��Q�v
EU-OSHA���u�����Ō��鉢�B�̋؍��i�n��Q�v
2010�N8��11��
���B���S�q���@�\( EU-OSHA
EU-OSHA
 )�̃��X�N�Ď�����i
)�̃��X�N�Ď�����i European Risk Observatory-ERO
European Risk Observatory-ERO
 �j���u�����Ō��鉢�B�̐E��X�g���X�v�iJISHA�C�O�g�s�b�N�X
�j���u�����Ō��鉢�B�̐E��X�g���X�v�iJISHA�C�O�g�s�b�N�X 2010�N2��16���Ɍf�ځj�ɑ����č쐬�������B�̋؍��i�n��Q�̏Ɋւ�����̂ł���B
2010�N2��16���Ɍf�ځj�ɑ����č쐬�������B�̋؍��i�n��Q�̏Ɋւ�����̂ł���B
���B�ɂ����āA�؍��i�n��Q�iMusculoskeletal disorders- MSDs)�́A���ׂĂ̎Y�Ƌy�ѐE��̘J���҂ɂ����āA�ł��������݂���E�Ɛ������ł���A�Ⴆ�I�[�X�g���A�A�h�C�c�A�t�����X�̍ŋ߂̕ɂ��A�o�ϓI�ȑ����͈����������傷��X���ɂ���BEU-OSHA�́A2000�N�ɂ��̖������S�q���L�����y�[���Ɏ��グ�Ĉȗ��A���̖��Ɏ��g��ł������A���̍ۂɓ���ꂽ���A����ȍ~�̌X���y�эŋ߂̏��Ɋ�Â��ĂƂ�܂Ƃ߂����ł���B
180�y�[�W�ɂ킽��c��ȕ��ŁA���ʂ̏ڍׂȏ��Ȃǂ��f�ڂ���Ă��邪�A���ɂ���v��̊T�v�݂̂��Љ��B�{���̖ڎ��ɂ��ẮA�v��̌��o���Ƃقڈ�v����̂ŏȗ�����B
�������̑薼�Ə���
 EUROPEAN RISK OBSERVATORY REPORT
EUROPEAN RISK OBSERVATORY REPORT
OSH in figures: Work-related musculoskeletal disorders in the EU-Facts and figures
���ҁF European Agency for Safety and Health at Work
���s�F2010�N5��4��
 View
View
 �j
�j Download the full publication as PDF
Download the full publication as PDF
 9‚704KB 180�y�[�W�j
9‚704KB 180�y�[�W�j���E�ی��@�\�́A�؍��i�n��Q�iMSD���j�́A�����̗v������N�����A��Ɗ��y�э�Ƃ̐������������W���A��������Q�̌����ɂ��āA�s�m��I�ł���Ɩ��֘A���a��1�ł���ƒ�`���Ă���BMSD���Ƃ����p��́A�^���튯�A���Ȃ킿�A�A�F�A���i�A��A���njn�A�x�ыy�ѐ_�o�̌��N�����Ӗ����Ă���B�Ɩ��֘A�؍��i�n��Q�Ƃ́A��Ƃ܂��͂��̐����ɂ��U������A�����������ׂĂ�MSD�����܂ނ��̂ł���B
�ŋ߂̉��B���ɂ����錤���́A���A��A�㎈�̏�Q�̂悤��MSD���́A���債�Ă���d�v�Ȏ��a�ł���A���N���p�ɂ�������ł���؋�����Ă���B���N�A���ׂĂ̐E��y�юY�ƕ���̐��S���̘J���҂���Ƃɂ��MSD���̉e�����Ă���L�͂Ȍ��N���ł���B��ȃO���[�v�́A���ɋy�ыƖ��֘A�̏㎈�̏�Q�A������u�J��Ԃ����ׂɂ���Q�v�ł���B�������A�܂��A�e������B���̎����グ�A�����p���y�ьJ��Ԃ�����́A���̌����ƂȂ�A�܂��A�����̏�Q�͓���̎d����E��ɊW���Ă���B���ÂƉ́A���ɖ����I�Ȍ����̎��a�ɂ��Ė����Ȍ����������邱�Ƃ͏��Ȃ��A�ŏI�I�ɂ́A�ٗp�r�����i�v�J���s�\�ƂȂ�\��������B
�}1�@EU27�J���ɂ����錒�N���̑��݂����Ȑ\�������J���҂̊����i%�j�i2005�j
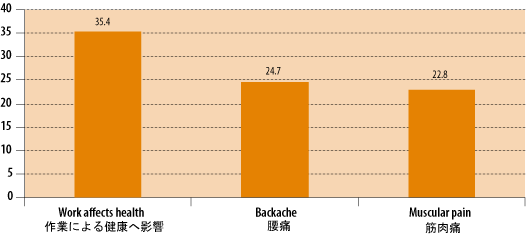
�����o���F���B�J�����������iEurofound: European Working Conditions Surveys- EWCS, 2005�j
ESWC�̍ŋ߂̒������l�ɂ��A���B�̘J���҂�24.7%�����ɂ��A22.8%���ؓ��ɂ�i���Ă���A45.5%���ꂵ���A���₷����Ǝp�����������Ă���A�܂��A35%���d�ʕ�����舵����Ƃ�v������Ă���ƕ��Ă���BEU15�J���ɂ��Ă݂�ƁA���ɂ��ł�������Ɗ֘A���N���ƂȂ��Ă���A��������܂��͌�⍑�ł́A����͑�2�Ԗڂ̖��ƂȂ��Ă���B
�����̌��N���́AESWC�ɂ����ẮA2000�N�ɒ������ꂽ���݂̂̂ł��邱�Ƃ���A�f�[�^�̌X�����͂͂ł��Ȃ��B�������Ȃ���A�}2�Ɍ��邱�Ƃ��ł���悤�ɁA�����̒ɂ݂́A�㎈�̒ɂ݂Ɠ����悤�ɏd�v�ł���悤�Ɏv����B�������̍��̃f�[�^�́A������Q�Ɋւ�����L�͈͂̏�����Ă���B���I�ƌ��N���̊e��̑��ʂ��e���̒������ʂ��猩�邱�Ƃ��ł���B�����̏������Ƃɓ���̐E�Ƃ̓���̃O���[�v�ɂ��ĒǐՒ�������A�����̏�Q�ɒ����Ԃ̗�����Ƌy�ѕ��s��Ƃ����X�N�v���Ƃ��ĊW���邱�Ƃ�����B
�����̏�Q�̎�ނƕp�x�ɂ��ẮA���I���ق�����B�����͒����Ԃ̗�����ƁA���s��Ƃɏ]�����邱�Ƃ���A���ݔF�肳��Ă��Ȃ������̏�Q�ɉe������Ă��邱�Ƃ����肳���B�Ⴆ�A���Ƃɂ����ẮA�j���͂Ђ��̖�肪�ł��傫���A����A�����Ƃƈ�Ê֘A�̏����ɂ��ẮA���A�r�A���ɑ����̖�肪���邱�Ƃ�����Ă���B�ڍׂȉ����̏�Q�̌X���Ƃ����̊W��������ɂ��Ẵf�[�^�����W���A���͂���K�v������ƍl������B
�}2�@MSD��������J���҂̊����i%�j�AEWCS 2005, 2000�y�щ�����⍑�̒���
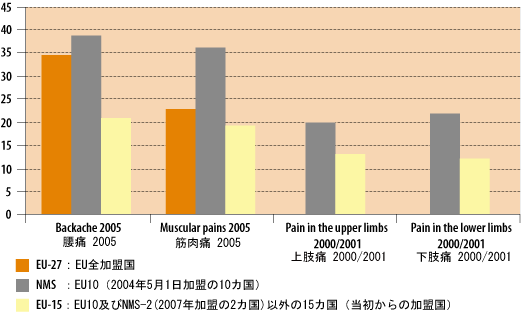
 ���jEU�������̉����������ɂ�镪�� �Q�Ƃ̂��ƁB
���jEU�������̉����������ɂ�镪�� �Q�Ƃ̂��ƁB
�����o���FEWCS, ESCC�iEuropean Survey of Candidate Countries�j
MSD���ɂ́A�����̌������q������A��Q�̌ʂ̎���ɂ��Đ��m�Ȍ������w�E���邱�Ƃ͍���ł���B�܂��A�����̌����́A���̘J�Е⏞�܂��͕��x�ɂ����ĐE�Ɛ����a�Ƃ��Ĉ�ʓI�Ɏ�����Ă�����̂ł͂Ȃ��B���������ŕW�������ꂽ�f�f����g�p���Ă��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A�p��͈̔͂ƌ��N���ɂ��Ă̋L�q�����ɂ���X�ł���B���̂��Ƃ���e���Ԃ̔�r�͍���ł���B�������Ȃ���A�e���̃f�[�^����͋Ɩ��֘A�؍��i�n��Q�͉��B�̍�Ɗ��ɂ������v�Ȍ��N���ł���ƌ��_�t���邱�Ƃ��ł���B�x���M�[�ł́A�@�B�I�U���ɂ�鎾�a�i��ɗA���y�ь��Ƃɂ�����w����Q�j�͍ł������J�Е⏞�\���̎��Ăł���B�`�F�R���a���ł́A�Ɩ���̋؍��i�n��Q�́A���ꂽ�E�Ɛ����a��33%�ƂȂ��Ă���B�X�y�C���ł��Ɩ���̋؍��i�n��Q���ł������E�Ɛ����a�ƂȂ��Ă���B����ɁA���������ɂ����Ă�����Q�́A�����̌X����������B
���B���v�ǂ̐E�Ɛ����a���v�iEuropean Occupational Diseases Statistics, EODS�j�ɂ��A�؍��i�n��Q�͍ł������E�Ɛ����a�ƂȂ��Ă���B�O�q�����悤�ɁAMSD���ɂ��Ă͊e���̘J�Е⏞���x�ɂ����Ă��Ȃ�̑��Ⴊ����B�����A�A�����ɂ��ẮA2�`3�̉������ɂ����Ă̂݁A�܂�����̎��a�݂̂�E�Ɛ����a�ƔF�߂Ă���ɂ����Ȃ��B���������āA�F�肳�ꂽ�Ɩ��֘A�؍��i�n��Q�̉��B���x���̑����I�ȃf�[�^�����W���邱�Ƃ͍���ł���B���̖����ȉߏ��]���ɂ�������炸�AMSD���́A2005�N��EODS�ɂ��E�Ɛ����a���l��39%���߂Ă���B
2005�N�̔F��E�Ɛ�������12��������EODS�ɂ��A�ł������Ɩ��֘A�؍��i�n��Q�́A��r���������i16,054���j�A�����Ŏ�y�ю����F�������i12,962���j�ƂȂ��Ă���B����ɁA17,395���̎��̎荪�Ǐnj�Q�Ɛ_�o�n��Q������B
�E�Ɛ������̉��B�ꗗ�\�ɂ́A�F�A�F���g�D�y���F�t�����̐U���A�Ǖ����y�щߏ�g�p�Ɋ֘A�������̏������f���Ă���B
�}3�@�E�Ɛ������̊����i%�j�iEODS�A2005�j
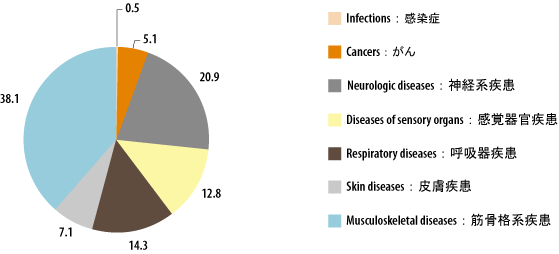
MSD���{�荪�Ǐnj�Q�́A2002�N����2005�N��32%���������i����������39%�j�B MSD���{�荪�Ǐnj�Q�́AEODS�ɂ��J�o�[����邷�ׂĂ̔F��E�Ɛ����a��59%�ɏ���Ă���i�����͖�85%�j�B
���S�Ƃ������ʂɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ����d�Ăȏ�Q�Əd��ȍ�Ɣ\�͂̒ቺ�Ɍ��т��؍��i�n��Q�̂悤�Ȗ����I��Q�ɂ��ẮA���N�̐V�K�̐��l�łȂ��ݐς̐��l�ɒ��ڂ���ׂ��ŁA���\���̘J���҂������̋؍��i�n��Q�ɜ���Ă��邱�Ƃ����肳���B�t�����X�ł́A1996�N����2006�N��10�N�Ԃ�275,000�����F�肳��A�J�Е⏞���Ă���A�܂��A�}���I�ȍ�Ǝp���ɂ�鎾�a��2003�N�̐E�Ɛ����a��68%�ɏ���Ă���B
��Ə�̃A�Z�X�����g�ƒ������ʂ��r����ƃT�[�r�X�Y�Ƃ̘J���҂��傢�ɉe�����Ă��邪�A�Ɩ��֘A���a�Ƃ��Ă̔F�萔�͏��Ȃ��Ƃ�������������B��ÁA�A���Ȃǂ̃T�[�r�X�E��ɂ����ẮA�J���Ғ����ł͌��N��肪�����������߂Ă��邪�A���B�̐E�Ɛ����a���ł͂����̕���ł͂��܂��ɔ�r�I�Ⴍ�A���ς����Ⴂ���l�ƂȂ��Ă���B��O���Y�Ɖ��̐i�W�������̉e���𑣐i���Ă���A��葽���̘J���ҁA���Ȃ킿�����y�ю�N�J���҂������̐E�ƂɏA�����Ƃ������Ȃ��Ă��Ă���B
�F��̎��ۂ̑��l���ɂ�������炸�A�؍��i�n��Q�͒j�����������ɑ����e�����Ă��邪�A�������A�����̎��Ăɑ���F�������@���Ă���悤�ł���B���̂��Ƃ́A�O�q�̐��l�ŗ��t���邱�Ƃ��ł���B�܂��AMSD���͑S�̑��ɂ����Ĕ��ɏd�v�Ȃ��Ƃł���A�����J���҂ɋ}���ɑ������Ă��Ă��邱�Ƃ��킩��B�J�ДF��́A��ɁA���ɁA�㎈�Ǝ�̎����ɏœ_�����ĂĂ��邪�A�������A��������葽���e������鉺���̎����ɂ��Ă͂��܂�d������Ă��Ȃ��B�������A�����J���҂̑����́A������Ƃł���A�Ⴆ�A��ÁA�z�e���A�O�H�Y�ƁA�N���[�j���O�A����A�����ƂȂǂɏ]�����Ă���B
���a�̊Ď��ƔF��ɂ��ẮA�N��w���猟�����邱�Ƃ��d�v�ł���B��N�w�̎��a�̕����Ⴍ�Ă��A�����̔N��w���؍��i�n��Q�ɉe������Ă��钛����B�����x���̐��l�ł́A��N�w�ɂ����đ������Ă���A�X�y�C���Ȃǂ̂������̍��ł͎�N�J���҂��ł��傫���e�����Ă���O���[�v�ƂȂ��Ă���B���̂��Ƃ́A�܂��A��N�J���҂̈��S�q���Ɗe���̐��l�͂����ȑO�̉��B���X�N�Ď�����̕ł��m�F���邱�Ƃ��o����B���̂��Ƃɂ��āA�����A��N�҂̋��㐫�ɂ��ċc�_����邪�A�ł͎�N�҂������Ɠ����悤�ɃT�[�r�X�Y�Ƃɏ]�����Ă���AMSD���̃��X�N�ɉߏ�ɂ��I���Ă��邱�Ƃ�����B
�X�y�C���A�C�M���X�Ȃǂ������̍��ł́A�؍��i�n���̋}�����Ă����́E�ЊQ�̐��l�Ƃ��Ď�舵���Ă���A�Ⴆ�A�d�ʕ��������グ���Ƃ��ɋN���鎖�ĂȂǂł���B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�S�̂̎��́E�ЊQ���ɂ����邱���̎��̗��̊����͑����Ȃ�B�����̋}�����Ă̜늳���́A�E�Ɛ����a�̗����������Ȃ�X���ƂȂ�B�������Ȃ��A��N�A�����A�T�[�r�X�Y�Ə]���҂Ȃǂ̃O���[�v�́A�Ȃ��A�E�Ǝ��a�ɂ��ĉߏ��F�����邱�Ƃ������B
���ʋy�ёS���B�����ɂ��A�؍��i�n��Q�͋Ɩ��֘A���ɑ傫�ȉe����^���A�������̑��������̂����AMSD���ɂ����̂����������ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��m�F����Ă���B���̂��Ƃ́A�E�ꕜ�A�헪�ɂ����ċ�������Ă���B
EU-OSHA�̈ȑO�̐E�ꕜ�A�ɂ����Ė��炩�ɂ��ꂽ�悤�ɁA������Q�̂悤�Ȃ�������MSD���ɂ��ẮA�E�ꕜ�A����ł͎�舵���Ȃ������B����1��OSHA�̌����ł́A��N�J���҂�MSD���Ɋ֘A���Ă��邱�Ƃ����炩�ɂ��ꂽ���A���n�r���ɂ��Ă͌����̑ΏۂłȂ������B���l�ɎЉ�S���I�J�������ɂ��Ă��ߏ��]���ƂȂ��Ă���B
���������āA���a�̗p��A���l������J���l���͈̔͂��܂߁A�E�ꕜ�A�y�у��n�r������ɂ��Ă͊g�傷��K�v������B
�Ɩ��֘A�؍��i�n��Q�́A�X�̘J���҂̌��N�e���݂̂Ȃ炸�A�Ɩ��̌o�ϓI�e���Ɖ��B�e���̎Љ�I�����ɂ�������Ă���B
�O�q��EU-OSHA�ɂ����ďq�ׂĂ���悤�ɁA�����e���S�̂̍�Ə�ɂ�����MSD���ɂ�鑹���̐^�̒l�����ς��邱�Ƃ͍���ł���B����́A�ی����x�ɂ�����g�D�̈Ⴂ�A�W�������ꂽ�]����̌��@�A���ꂽ�f�[�^�̗L�p���ɑ���m���̖R�����ɂ����̂ł���Ǝv����B���錤���ł́A�Ɩ��֘A�̏㎈��MSD���ɂ�鑹���́AGNP��0.5%����2%�ł���Ɛ��v���Ă���B
�ŋ߂̐��l�A�Ⴆ�I�[�X�g���A�A�h�C�c�A�t�����X�ł́AMSD���ɂ�鑹�����������Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B�t�����X�ł́A2006�N�ɂ́AMSD���ɂ�鑹����700���l���A��7��1�疜���[���ɏ�����B
�O�q�����悤�ɁAMSD���̌����͑���ɂ킽��A�܂��A�l�X�ȋ؍��i�n��Q�ɑ��鑽���̃��X�N�v�������炩�ɂ���Ă���B�����ɂ́A�����I�A�o�ϓI�y�юЉ�S���I�v�����܂܂�Ă���B
��r�\�ȃf�[�^�̎�ȏo���͏�q�̘J���������B�����iEWCS�j�ł���B�����ł́AMSD���̔��ǂɂ��ĉ��L�̃��X�N�v�����f���Ă���B
��Ƒ��x�Ȃǂ̍�ƍ\���̃��X�N�v���͊܂ނ��A�g�������X�N�̕��͂��K�肷����̂ł͂Ȃ��A�x�ёg�D�ɗ͂������邱�ƁA�����Ȉړ��A�@�B�I���͂������邱�ƂȂǂ̃��X�N�v�������j�^�[������̂ł͂Ȃ��B
EU���x���ł́A�J��Ԃ���Ƃ͍ł������L���s���Ă���MSD���̔��ǂɌW�郊�X�N�v���ł���BNMS-2(�u���K���A�y�у��[�}�j�A)�̘J���҂̖�74%�AEU15 ��EU10�̘J���҂�61.5%����E�r�̌J��Ԃ���Ƃɏ]���i���I�j���Ă���A���̒����͘J�����Ԃ�4����1�ɏ��ƕ���Ă���B
NMS-2�̘J���҂�52.7%�AEU12�̘J���҂�46.4%�y��EU15�̘J���҂�44.4%���A��ɂ��܂��͔��₷����ƈʒu�ł̍�Ƃɏ]���i���I�j���Ă���B����ɁA�A�J���Ԃ�4����1�ȏ���d�ʕ��戵���ɏ]�����Ă���J���҂́AEU10�̘J���҂�42.8%�AEU12 �̘J���҂�38%�A�y��EU15�̘J����33.9%�ł���B�U���ւ̂��I�́AEU15�J���y��EU12�J���ɂ����āA�d�v�ȃ��X�N�v���ł���B
�}4�@MSD���̃��X�N�v���A�J�����Ԃ�4����1�ȏ�̂��I�J���ҁi%�j�AEWCS (2005)
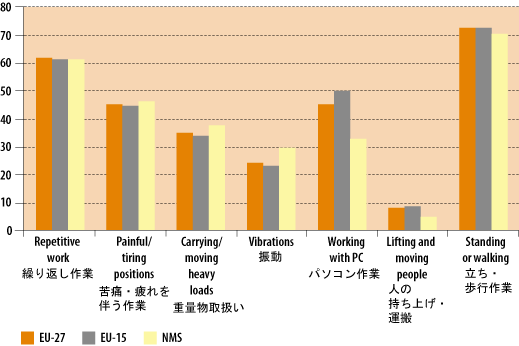
�����o���FEWCS
�������̓���̕���y�ѐE�Ƃɂ��ď������A���ۓI�ɑ����̃��X�N�v���ɂ��炳��Ă���B�Ⴆ�A�d�ʕ��戵����Ƃ́A�S�̂�5.8%�ɉ߂��Ȃ����A�����J���҂�������Ê֘A����ɂ��Č���ƁA�قڔ�����43.4%���߂Ă���B��Ê֘A����ɏ]�������v�ȃO���[�v�͒����N�����ł��邱�Ƃ��l������ƁA���̃O���[�v�ɑ���h�~�K�v�ł��邱�Ƃ����m�ƂȂ�B�����Ƃɂ����鏗�����U���ɂ��炳��Ă��郊�X�N�́A�V�����d�v�Ȃ��̂ł��邪�A�U���ɂ����郊�X�N�̔F�����Ⴍ�܂��A�f�[�^�𐳊m�Ɏ��W���Ȃ��Ƃ��̃��X�N�ɂ��Ă̔�����������Ă��܂��B
�N��ʂɌ���ƁA��N�J���҂́A�ߏ��MSD�����X�N�ɂ��炳��Ă��邱�Ƃ��킩��B���ɁA�T�[�r�X�ƁA�����Ƃ̔�n���J���y�ь��Ƃɂ����Č����ł���B��N�J���҂�MSD�����X�N�̂��I���ɂ���A�؍��i�n��Q�ɜ���Ă���A�X�y�C���Ȃǂ̎��a�֘A�f�[�^����m�F���邱�Ƃ��ł���B
�e���̒������ڍׂɌ�������ƁA�J���҂��ꎞ�ɕ����̃��X�N�ɂ��炳��Ă���A���ɃT�[�r�X�Ƃł̏����ɑ����B
�u���[�J���[�y�уT�[�r�X�Ƃ̘J���҂́A�����I���X�N�ɂ��炳��邱�Ƃ������A�Ⴆ�Ώd�ʕ��戵���A��ɂ܂��͔�J����Ǝp���Ⴕ���͐U���Ȃǂ�����A�J��Ԃ���Ƌy�ё�����Ƒ��x���v��������Ƃ́A���ׂĂ̐E�Ƃɂ����Č�����B�����Ԃ̗�����Ƃ���s��Ƃ́A�_�Ƃ⌚�ƂȂǂ̓`���I�ȕ���ɂ�����T�^�I�ȃ��X�N�v���ł��邪�A�����Ƃ�ڋ��ƂȂǂ̃T�[�r�X�Ƃɂ����Ă����X�N�v���ƂȂ��Ă���A���������������ɂ��Ẵ��j�^�����O�⎾�a�F����ᒲ�ł���B���c�J���҂��ߏ�ȃ��X�N�ɂ��炳��邱�Ƃ������A���Ȃ킿�A��J�y�ы�ɂ���Ǝp���i�J���҂�43.5%�ɑ���54.8%�j�A�d�ʕ��戵���i�J���҂�33.1%�ɑ�44.7%�j�A�J��Ԃ�����i�J���҂�61.7%�ɑ�64.5%�j�A�����Ԃ̗����E���s��Ɓi�J���҂�72%�ɑ�77.3%�j�Ȃǂł���B�������̃f�[�^������ڍׂȏ�c�����邱�Ƃ��o����B
![]()
���jEU�������̉����������ɂ�镪��
���B�����E�J���������P���c�i European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions- Eurofound
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions- Eurofound
 �j�@�̉��B�J�����������i
�j�@�̉��B�J�����������i European Working Conditions Surveys- EWCS
European Working Conditions Surveys- EWCS
 �j�ɂ��ẴT�C�g
�j�ɂ��ẴT�C�g
���̑��ɂ��ẮAJISHA�C�O�g�s�b�N2010�N3��31���̋L���̊֘A���Ɉȉ��̂悤�Ȍf�ڂ����Ă���B
MSDs�́A�J���҂̌��N�m�ۂ̂��߂ɍł��d�v�Ȏ����ƔF������Ă���A�����̏�e�@�֓��̃T�C�g�Ɍf�ڂ���Ă���B�u�d���ւ̓K���E���B�v( Fit for Work Europe
Fit for Work Europe
 )�E�F�u�T�C�g�̃����N�W�i
)�E�F�u�T�C�g�̃����N�W�i Fit for Work Europe Links
Fit for Work Europe Links
 �j�́A�����̃T�C�g�̑������f�ڂ��Ă���B
�j�́A�����̃T�C�g�̑������f�ڂ��Ă���B
��L�̑��̏��@�ւɂ�����MSDs�Ɋւ���E�F�u�T�C�g�̗�Ƃ��ĉ��L������B
 Musculoskeletal disorders
Musculoskeletal disorders

 Musculoskeletal disorders
Musculoskeletal disorders

 Ergonomics
Ergonomics

 Ergonomics and Musculoskeletal Disorders
Ergonomics and Musculoskeletal Disorders
