

 進展と停滞の時代 昭和戦前
進展と停滞の時代 昭和戦前
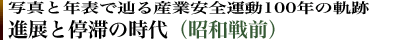
第一次世界大戦後のわが国の景気は、昭和4年のアメリカを発端とする“大恐慌”の世界的な波及によって深刻な打撃を受けた。企業は厳しい合理化を迫られ、人員整理、倒産が相次いだ。
低迷の続いた景気も、昭和6年に勃発した満州事変をきっかけに軍需の増大によってようやく回復に向かった。特に金属、機械などの重化学工業は高い伸びを示した。
この時期は、大正時代に芽生えた安全運動が民間・行政の各分野で一斉に広がりを見せた時期でもあった。安全週間も全国行事となったほか、昭和7年には初の全国産業安全大会が開かれた。
昭和に入って安全活動が盛んになるにつれ、事業場で熱心に安全に取り組むところが、大企業を中心に増えていった。住友伸銅鋼管、住友製鋼所、日本鋼管川崎工場、川崎造船所、八幡製鉄所、国鉄大宮工場、三井三池鉱業所等の企業が作業標準づくり、家庭への呼びかけ、安全委員会の開催、安全競争の実施といったユニークな安全活動を展開していった。
しかしながら、昭和12年に始まる日中戦争以後、次第に戦時色が濃厚となり産業安全運動は長い停滞の時期を迎える。

 |
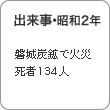
|
||||||||||||
 |
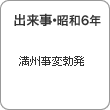 産業安全衛生展覧会が初めて開催解説される。 産業安全衛生展覧会が初めて開催解説される。
|
||||||||||||
 |
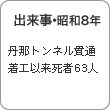 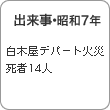 産業福利協会の主催により東京・学士会館で初めての全国産業安全大会が開催解説される。 産業福利協会の主催により東京・学士会館で初めての全国産業安全大会が開催解説される。
|
||||||||||||
 |
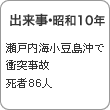 セメント製造業者が集まり、同業種の労働災害防止について研究協議会を開く解説。同業者団体の安全運動の先駆けとなる。 セメント製造業者が集まり、同業種の労働災害防止について研究協議会を開く解説。同業者団体の安全運動の先駆けとなる。
|
||||||||||||
 |
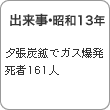 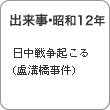 人絹連合会及びスフ工業会両団体傘下の各社を会員とする化学繊維工業保健衛生調査会が発足解説し、業種別衛生活動のモデルとなる。 人絹連合会及びスフ工業会両団体傘下の各社を会員とする化学繊維工業保健衛生調査会が発足解説し、業種別衛生活動のモデルとなる。
|
||||||||||||
 |
昭和14年から16年にかけて日本鋼管、三井、八幡、芝浦、鐘紡等の事業場に産業医学研究所が設置される。 |
||||||||||||
 |
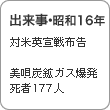 伊藤一郎解説らの寄付により、芝・田町に厚生省産業安全研究所が設置、翌18年に付設の博物館が設置される(初代所長は武田晴爾解説)。 伊藤一郎解説らの寄付により、芝・田町に厚生省産業安全研究所が設置、翌18年に付設の博物館が設置される(初代所長は武田晴爾解説)。
|
||||||||||||
|
|||||||||||||