キャンペーン・募集
令和6年度 化学物質管理強調月間
化学物質管理強調月間に寄せて
昔々のエジプトの話です。ナイル川の畔で、人間は美しい鉱石を見つけました。その鉱石は虹色に輝き、表面からは綿のような繊維が噴出していたのです。その鉱石を加工し、布を作ってみたところ、その布は魔法を付与されているかのように燃えない布でした。人々は、その布を神聖な物とし、ミイラを包むのに使用することにしました。その製法は秘とされましたが、やがてヨーロッパの錬金術師に受け継がれ、彼らはそれを火の精霊・サラマンダーの皮と称し、自らの権威付けに使用しました。
日本においてその布「石綿布」のことが記述されている最も古い文献は、平安前期に書かれた日本最古の物語「竹取物語」であると言われています。月から来たかぐや姫が、婚姻を断るため5人の王子に所望した宝物のひとつ「火鼠の裘(ひねずみのかわごろも、焼いても燃えない布)」がそれです。ちなみに日本で最初に製造された石綿布は、江戸時代に平賀源内が秩父の鉱石から作ったものと言われ、今も現存しています。

このように歴史のロマンを感じさせる石綿布が、産業界で使用されるのは昭和20年代から40年代にかけてです。戦後の高度成長を支えた産業に造船業がありますが、造船の作業工程の中心は溶接業務で、作業員たちは飛び散る火花の「火避け(ひよけ)」として、日常的に石綿布を使用し、寒い時はそれに包まり暖をとることもありました。 石綿布を中心とした石綿の需要はその後急激に高まり、耐火性・摩耗性に優れ資材として建築建材・自動車部品等の産業の場で使用されるようになりました。 この石綿(アスベスト)が、夢の素材ではなく有害物質であることが判明するのは、昭和50年代以降です。1年生存率約50%の中皮腫の原因となり、その潜伏期間は約50年に及び、毎年千件以上が労災認定され、延べ労災認定件数は1万件以上と言われています。
石綿による社会的な損失は甚大です。労働者を使用していた企業の責任が追及され莫大な損害賠償が支払われることはもちろんのこと、解体するビル等から使用されていた石綿を除去するのに建設費用はかさ上げされます。また、回収された石綿は環境に与える影響が考慮され特殊の溶鉱炉で溶解処理され廃棄されています。さらに被害者の救済には多額の費用が必要となります。例えば、厚生労働省は石綿を使用していた労働者には健康管理手帳という手帳を交付し、中皮腫等を早期に発見をするために年2回の特殊健康診断を実施していますが、これはすべて労災保険料から支払われています。人間はまさに、「アスベスト禍での100年戦争」を現在も継続中と言えます。
また、こんな話もあります。メタン、エタン、プロパンは炭素と水素からなる炭化水素系の構造でよく似ており、きょうだいのような物質です。常温ではいずれも気体ですが、水素原子2個を塩素原子2個に置換することで、それぞれ常温で液体のジクロロメタン、ジクロロエタン、ジクロロプロパンとなります。10年ほど以前まではジクロロメタンは第二種有機溶剤、ジクロロエタンは第一種有機溶剤として労働安全衛生法の規制の対象でしたが、ジクロロプロパンは法の規制の対象外でした。そして、3物質とも、それぞれを原料とした塗料が製造されていました(注:3物質とも現在は「特別有機溶剤」に指定されています)。
ある印刷会社に塗料メーカーの営業マンがやってきて、その会社の社長にこう述べたそうです。
「ジクロロプロパンを原料としたインクは、ジクロロメタン、ジクロロエタンを原料としたインクと違い、法の規制がないので、局所排気装置を備えたり、健康診断を実施したり、作業主任者を選任する必要がありません」
社長は営業マンの言うとおりに、何の衛生管理もしないでこの塗料を使い続けたところ、ジクロロプロパン使用を原因とする胆管がんが従業員17名に発症し、そのうち8名が死亡するという事件が起きてしまいました。
この印刷会社は検察庁に書類送検されましたが、その罪名は「衛生管理者未選任」「安全衛生委員会未実施」というもので、「有害物質をばく露対策をせずに使用させた」行為については罪に問われませんでした。
有害指定をしていなかった化学物質により引き起こされたこの事件は、「胆管がんショック」として関係者だけでなく広く社会に記憶されることになります。
我々のような安全衛生担当者は、化学物質の管理について、いろいろな言葉に縛られてきました。 「有機溶剤」「特定化学物質」「鉛」「四アルカリ鉛」「粉じん・じん肺」etc・・・ 新たな化学物質に出会うたびに、どの言葉が当てはまるのかを検討し、対策を立ててきたのです。 言葉はどんどん増えていきました。 「特別有機溶剤」「特定管理物質」「がん原性物質」etc・・・ 「もうたくさんです。これ以上の言葉はもういりません。」我々はそう感じていました。なにより、新しい物質にふさわしい言葉がなかったら、また「胆管がんショック」のような事件が起きてしまいます。
このような状況下、厚生労働省はある決断をします。令和3年7月に発表した「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書」には、「特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害防止規則、四アルキル鉛中毒予防規則(以下「特化則等」という)は、自律的な管理の中に残すべき規定を除き、5年後に廃止することを想定し、その時点で十分に自律的な管理が定着していないと判断される場合は、特化則等の規制の廃止を見送り、さらにその5年後に改めて評価を行うことが適当である」と明記され、新たな方向性が示されました。
さて今、我々は「新しい言葉」に戸惑っています。
「リスクアセスメント」「GHS」「SDS」「コントロール・バンディング」「クリエイトシンプル」etc・・・
でも、この「新しい言葉」を恐れてはいけません。今は「古い言葉」と「新しい言葉」が混在する過渡期なのです。そして、「古い言葉」は我々を縛り付けましたが、「新しい言葉」は我々の武器なのです。
化学物質について、「GHS」で有害性と危険性を明らかにし、「SDS」で融点等の物性を得て、自らの「使用方法」「使用環境」をカスタマイズして入力した「コントロール・バンディング」や「クリエイトシンプル」のツールを使いリスクアセスメントを行い、職場環境にあったリスク削減措置を行うことが可能になったのです。
やがて「新しい言葉」が定着し、「古い言葉」が無くなった時代の未来の安全衛生担当者は、「昔は安全衛生対策に非効率なことやっていたよな」と旧時代の我々を評すると思います。我々はこれから、もっともっと進歩しなければなりません。それが、今まで化学物質の職業病に苦しんできた人たちのためにできる唯一のことなのですから。
さあ、「アスベスト禍」や「胆管がんショック」を乗り越え新しい時代が始まります。用意はいいですか?
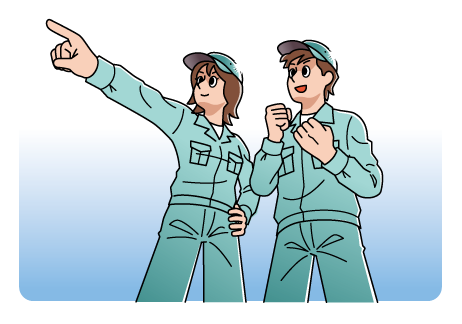
令和6年11月
中小規模事業場安全衛生相談窓口
ご案内
厚生労働省の補助事業として、中小規模事業場が抱える課題や悩みの解決をお手伝いする中小規模事業場安全衛生窓口を設けております。安全衛生の専門的知見やノウハウを持った専門家が無料でアドバイスいたします。お気軽にお問い合わせください。
本コラムおよびイラストの全部または一部の加工や切り取り、商用利用は禁じます。事業場の安全衛生活動にお役立てください。

